グループホームとは?サービス内容や費用をご紹介します!
- 2024年05月27日 公開
- 2024年06月07日 更新

「グループホーム」は、アットホームな環境下で認知症に特化したケアを行う高齢者施設です。この記事ではグループホームの概要やサービス内容・費用などをご紹介します。
他の高齢者施設との違いやグループホームに入居するメリット・デメリットなども合わせて解説します。
この記事の監修者
目次
グループホームとは?

そもそも、グループホームとはどのような施設なのでしょうか。まずは運営目的や施設で提供されるケアの特徴を解説します。
グループホームの運営目的
グループホームは、介護保険サービスのうち「地域密着型サービス」に分類されます。地域密着型サービスは2005年から始まり、高齢になっても住み慣れた地域で生活を続けるためのサポートを目的としています。
地域密着型サービスには、自宅にいながら利用できる小規模多機能型居宅介護・夜間訪問型訪問介護や、施設に入居して介護を受けながら生活するグループホームなどがあります。
そのなかで、グループホームは認知症ケアに特化した施設です。施設とはいっても「ユニット」と呼ばれる少人数での共同生活であり、家庭的な環境が特徴です。見守りや介助などのサポートを受けながら安心して過ごすことができます。
グループホームのケアの特徴

介護保険の入居施設の多くは、食事や清掃などをサービスとして提供しています。しかし、グループホームの目標は「可能な限り自立した生活」にあるため、入居者は自分でできる範囲で家事を行います。必要に応じてスタッフが見守りや声掛け・補助などを行いますが、基本的には入居者が主体です。
また、機能低下を予防するために機能訓練やレクリエーションなどをする時間も設けられています。
加えて、2020年には新たに「サテライト型」が設立されました。本体の事業所と連携をとりながら運営されるサテライト型は、何かあれば本体事業所より駆け付けることができる体制などが整えられており、地域の特性に応じたサービスの整備や提供を促進するために作られた狙いがあります。
グループホームの設備とは?
一般的な「高齢者施設」のイメージとは少し異なるグループホームのケアは、どのような設備のもとで行われているのでしょうか。
居室

居室の広さは、私物の収納を想定したうえで4.5畳以上と定められています。居室の定員は原則1人ですが、利用者のサービス提供上必要と認められる場合(夫婦で入居する場合など)は、2人とすることもできます。
部屋にはベッドが設置されており、布団などは持ち込み可能な場合もあります。しかし施設によっては、介護用ベッドはレンタル必須で、実費で賄わなければならないケースや、逆に自宅からベッドを持参しなければいけないケースなどさまざまなパターンがあります。
また寝具だけに限らず、自宅で使用していたタンスやテレビなど、慣れ親しんだ家具・家電を持ち込める施設も多いようです。
共用設備

多くのグループホームでは、共同スペースを囲む形や事務所を中心に左右やL字で居室が配置されています。これにより、居室の出入り口や共用の食堂・便所・洗面所・浴室にもスタッフの目が行き届きやすく、安全性の高い構造になっています。
高齢者が入居するという目的から段差などは解消する必要がありますが、必ずしもバリアフリー化は義務ではありません。なかには、入居者の身体能力維持のため、あえて段差などを残しながら古民家を改装したグループホームもあるそうです。
立地

グループホームの立地は、「利用者が家族・地域住民と交流する機会が確保できる場所」であることが条件です。全国一律の基準はありませんが、「近隣に所定の軒数の住宅がある地域」などと定めている自治体もあります。
住み慣れた地域の施設に入居するというだけでなく、入居後も外部との交流を続けることで「その人らしい生活」「入居前に近い生活」が保たれるはずです。入居を検討する際は、施設内だけでなく周囲の環境にも目を向けてみましょう。
定員

グループホームに入居できる定員は、1ユニットあたり5~9人までと定められています。1つのグループホームに設置できるユニットは3つまでです。介護保険上、1軒のグループホームに暮らせる高齢者は最大で29人です。
ただし、グループホームを本体としてサテライト型を併設している場合、サテライト型の入居者は本体のユニット型の定員には含まれません。
台所、便所、洗面設備、浴室

グループホームでは、共同施設として食堂のほかに台所・便所・洗面所・浴室などが設置されています。これらの設備はユニット単位で使用するため、同一建物内に3つのユニットがある場合は、ユニットごとに設置する必要があります。
グループホームの入居条件とは?

次に、グループホームの入居条件について確認していきます。
主な入居条件
主な入居条件は以下のとおりです。
- 65歳以上かつ要支援2以上
- 認知症の診断を受けている
- 施設が所在する市区町村に住民票がある
前提として、グループホームを利用するには65歳以上で、要支援2以上の認定を受けている必要があります。
ただし、介護保険法に定められた特定疾病を抱えているために支援が必要と判断された場合は、40歳以上でも認定を受けられる場合があります。なお、現在16種類の病気が特定疾病とされており、グループホームに関連するところでは若年性認知症もその1つです。
また、2つ目の入居条件として「医師から認知症と診断されていること」が挙げられます。「診断はされていないけれど最近忘れっぽくて心配」という段階では入居できません。
さらに、地域密着型サービスという性質から「施設が所在する市区町村に住民票があること」も入居条件の1つです。この条件については、後半の「メリット・デメリット」の項でも詳しく触れるので参考にしてください。
生活保護を受給していてもグループホームに入れる?
グループホームに限らず、生活保護を受給しながら高齢者施設に入居する場合は「生活保護に対応した施設かどうか」を確認する必要があります。まずは、ケースワーカーやケアマネジャーと相談し対象となる施設を探しましょう。
入居した場合、介護サービスは生活保護の「介護扶助」から、賃料は「住宅扶助」から、医療費や水道光熱費は「生活扶助」から支給されるため、それぞれの限度額内でやりくりします。
グループホームの人員基準とは?

認知症の入居者が共同生活を送るグループホームのケアは、どのような職員によって支えられているのでしょうか。グループホームの人員体制について見ていきましょう。
代表者・管理者
グループホームで配置が義務づけられているのは、代表者・管理者・計画作成担当者・介護職員の4職種です。まずは、施設の運営を担う代表者と管理者について解説します。
代表者はグループホーム全体のサービス管理や経営に携わるため、認知症介護の実務経験もしくは医療・福祉サービス事業所での経営経験が必須です。さらに「認知症対応型サービス事業開設者研修」を受ける必要があります。
一方、管理者はユニット内での労務・収支管理を行いながら現場での業務を行うこともあります。そのため、管理者研修の受講に加え高齢者施設での3年以上の実務経験が必須です。
1ユニットに対して配置しなければならない常勤管理者数は1人です。
計画作成担当者

入居者一人ひとりに合わせたケアプランを作成するのが、計画作成担当者です。認知症介護実践者研修・実務者研修基礎課程のいずれかの修了が条件の1つであるため、もちろん介護の知識が必要です。
また、ユニットごとに1人以上の配置が定められているため、1つのグループホームに数人の計画作成担当者が配置されることもありますが、そのうち1人は必ず介護支援専門員(ケアマネジャー)でなければなりません。
介護職員

グループホームの介護職員の配置については、「日中は入居者3人に対して1人」「夜間を通して1人以上」という決まりがあります。一見充実しているように見えますが、ネックは「日中の時間帯は」という条件がついている点です。
「日中」の解釈は各施設に任されており、また「1人」というのも常勤職員の数でなく「常勤換算」の数字でよいとされています。
つまり、施設ごとに定められた「日中」とされる時間帯に働く職員の「合計勤務時間」が、高齢者3人に対して常勤者1人分の勤務時間に達すればよいという決まりしかないということです。
そのため、実際にグループホームへ見学に行くと「入居者は9人なのに介護職員が2人しかいない」という事態が起こり得ます。このように介護職員数は施設によって差があるため、事前の確認が必要です。
グループホームでかかる費用とは?

ここからは、グループホームで暮らすためにかかる費用について内容や相場、注意点などを解説します。
初期費用
入居の契約をすると、実際に住み始める前に初期費用の支払いが発生する場合があります。グループホームの初期費用として一般的なのが「保証金」または「入居一時金」です。
「保証金」
保証金は、居室を破損した場合の修繕費や家賃を滞納した場合の補填など「必要時に使用するための金銭」です。そのため、入居時に一度支払っても使用されなかった分は退去時に払い戻されます。
金額は数カ月分の家賃程度であることが多く、0~30万円が相場です。ただし公的な決まりはないため、施設によって保証金に大きな差が出ることもあります。
「入居一時金」
入居一時金は「入居予定の施設に住む権利を得るために支払う金銭」です。そのため、破損や滞納などがなかったとしても、月々の家賃などとして使用されます。
最初に支払われた入居一時金を事業所が使用し終えるまでの期間を「償却期間」といいます。償却期間内に退去した場合は、まだ償却されていない分の金額が払い戻されます。しかし、償却期間は3年のところがあれば10年以上のところもあるなど施設によってさまざまです。
また、初期費用の名称は施設ごとに異なることがあり、なかには払い戻されず支払った時点で事業者のものとなる費用も存在します。契約前に、初期費用の金額や返金の有無などは確認しておきましょう。
月額費用

月額費用は、入居後に毎月支払うお金のことです。月額費用に含まれる日常生活費・介護サービス費・サービス加算について解説します。
日常生活費
日常生活費はグループホームで生活を送るために必要な費用です。内訳は、賃料・管理費・食費・水道光熱費・理美容代・買い物代行費・おむつ代など。地域や施設により差はありますが、相場は約12万円です。
平均的な金額は、賃料5万円・管理費1万8000円・食費3万8000円・水道光熱費1万8000円前後です。
介護サービス費
1ユニットのみのグループホームの場合、要支援2かつ介護保険の自己負担割合が1割の人の自己負担額は月額2万2800円程度です。介護度が1段階上がるごとに月の自己負担は数百円程度増えていきます。
例えばユニットを2つ設置している施設では介護サービス費の自己負担額が400円ほど安くなります。都道府県により金額は多少変わりますが、元となる点数は介護保険法に定められており、施設による大きな差はないでしょう。
サービス加算
高齢者施設では、所定の要件を満たすことで「加算」を算定できます。費用は多少かさみますが、どのような加算を算定しているかを知ることでグループホームが力を入れているケアの内容が見えてくるかもしれません。
加算対象となるケアの例としては、「専門性の高い認知症ケアを行っている」「医療ケアを充実させるため看護師を常勤としている」「容体の悪い入居者に対して看取りまで行っている」などが挙げられます。
グループホームで受けられるサービスとは?
ここまでの説明は制度面や金銭面が中心でしたが、実際にグループホームではどのようなサービスを受けられるのでしょうか。
生活のサポート

グループホームでは、事業所のスタッフから必要な介護サービスが提供されます。ただし、基本的には「共同生活ができる」という条件での入居のため、入居者は自立度が高い傾向にあります。
そのため、重い介護を必要とする入居者は少なく、提供されるのは主に本人の動きをサポートする軽い介助などです。なかには車いすに対応していないグループホームもあるため、身体介護への対応は入居前に確認しましょう。
また、介護のほかに有料で買い物代行や薬の受け取り・現金出納の管理などを行っているグループホームもあります。有料サービスの内容や費用は施設ごとに差があるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
機能訓練
グループホームでは、認知・身体機能を保つために機能訓練が行われます。ただし、外部サービスは利用できず、リハビリスタッフの配置も義務づけられていないため、介護保険で行うような運動器リハビリは難しいのが現状です。
機能訓練の内容は施設ごとに職員が工夫しており、楽しみながら手先を動かせるレクリエーションや園芸・体操などさまざまです。体操に関しては身体機能に加えて嚥下機能の向上を目指したものも取り入れられています。
地域交流
地域に密着した施設として、グループホームでは住民との交流にも力を入れています。地域と交流を持つことは、周囲に施設のことを知ってもらうだけではなく、認知症を抱える入居者にとっても心身活性化のきっかけとなるでしょう。
入居者が外部へ出向く地域交流としては、地域活動(老人会の活動や公園の清掃、お祭りなど)への参加が挙げられます。こうした活動では、交流を深めるとともに「地域の役に立っている」というやりがいも感じられるはずです。
一方、地域の住民に門戸が開かれる形での交流としては介護予防体操教室や介護相談などが挙げられます。また、グループホームでカルチャースクールなどの慰労公演も行われているそうです。
グループホームが地域に開かれることで、施設だけではなく認知症自体の理解が深まる可能性があります。グループホームがどのようなところかを知るために、こうした催しに参加してみるのもよいかもしれません。
グループホームのメリットとは?

それでは、グループホームに入居するメリットにはいったいどのようなものがあるのでしょうか。ここではメリットを3つご紹介します。
認知症の進行を抑制できる可能性がある
グループホームは認知症の高齢者を入居対象としています。そのため、認知症ケアに関する経験や知識が豊富なスタッフに日常生活の支援を任せることができるでしょう。
また、他の施設と比べると共同スペースも家庭的で、日中は自分でできる家事を行う機会もあります。集団内で役割を持つことは「周りの人の役に立っている」というやりがいや意欲向上のためにも重要です。
このように家庭的な環境のもと、適切なケアや援助を受けながら共同生活を送ることで、病院や他の高齢者施設にいるときよりも、自分で考えて行動することができます。考えて脳を使うことで認知機能の低下を遅らせることができると考えられています。
入居者が少人数のため、コミュニケーションを取りやすい
施設の種類によっては、にぎやかに見えても入居者とスタッフ(1対1)のやり取りがメインとなっている場合もあります。一方、グループホームでは互いに役割を持ち一緒に作業を行うことで、入居者同士が声を掛け合う機会も増えます。
加えて、少人数での生活は相手に対して「大勢のなかの1人」ではなく「同居している仲間」という意識が生まれやすい環境です。その結果、大規模な施設よりも入居者同士のコミュニケーションが取りやすいでしょう。
さらにユニットごとに担当スタッフが決まっているため、入居者の性格や考え方などを把握したうえでコミュニケーションを取ることができます。入居者にとっては安心感もあり、自然と話も弾むのではないでしょうか。
お住まいの地域で生活を送ることができる
入居条件の項目でも紹介したとおり、グループホームは所在地の市区町村に住民票を持つ人が入居対象です。そのため、住み慣れた地域で生活を続けられるメリットがあります。
入居したグループホームに連携医療機関がない場合も、住まいの場所が大きく変わらなければ通い慣れた医療機関を受診できる可能性があります。また、親戚や家族が近くに住んでいる場合はつながりも保ちやすいはずです。
さらに、入居者も同じ地域で暮らしていた人同士のため、共通の話題で盛り上がることもあるのではないでしょうか。そうした話題をきっかけに若い頃の話をすることは、認知症ケアの観点からも重要です。
グループホームのデメリットとは?
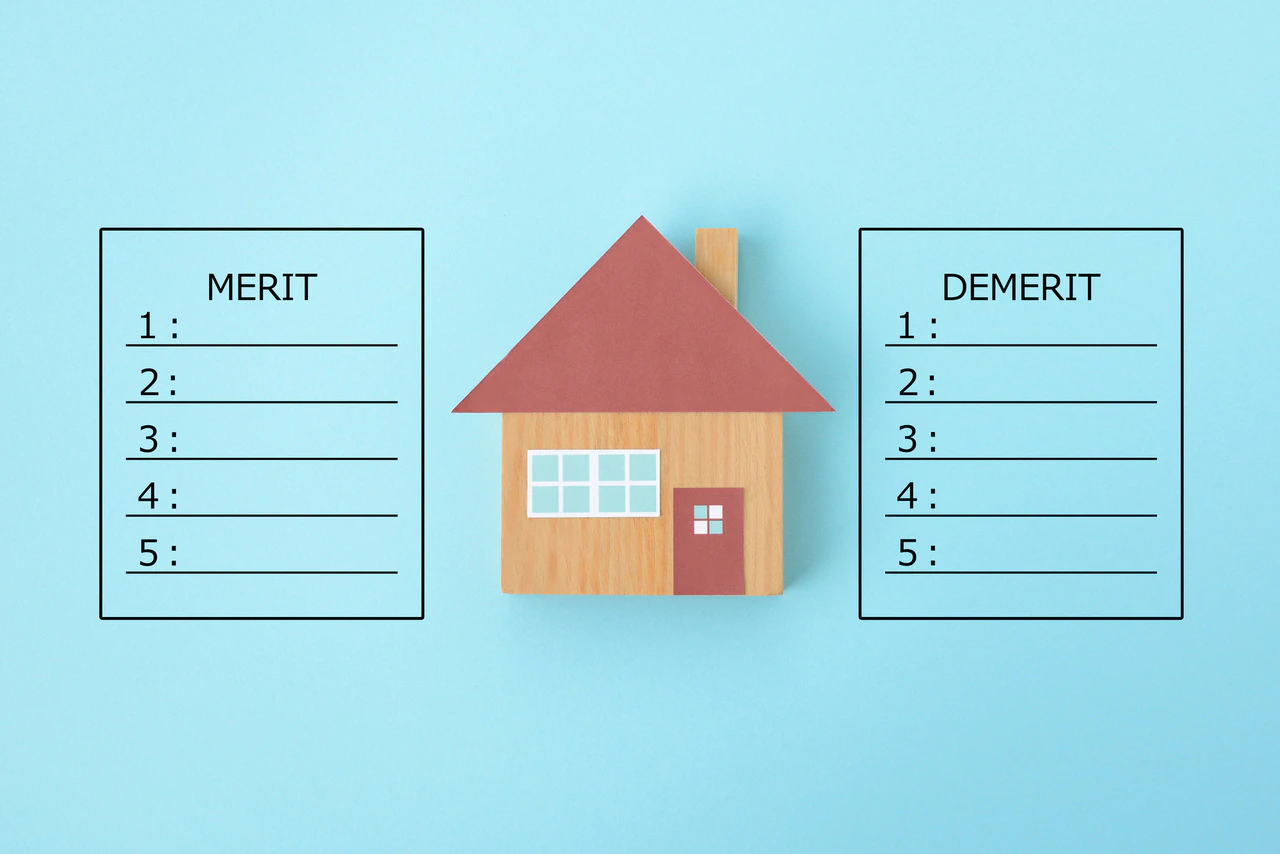
グループホームにはメリットだけではなく、デメリットもあります。入居を検討する際には、デメリット面の把握も大切です。
ここでは3つのデメリットをご紹介します。
入居者の定員が少ないため、簡単に入居できない場合がある
1つ目のデメリットは、待機期間が比較的長いことです。
1軒のグループホームで生活できる高齢者は最大で29人です。他の高齢者施設と比べると定員が少なく、空きがなかなか出ないために入居まで数カ月かかることも珍しくありません。
ただし、待機状況は地域によって差があり、また同じ施設でもタイミングによって大きく変わります。まずは、気になったグループホームに待機人数や平均的な待機期間を確認してはいかがでしょうか。
医療依存度が高まると退去しなければならない場合がある
2つ目のデメリットは、医療的な処置が必要になると退去しなければならない可能性がある点です。
グループホームでは看護師の配置が義務化されていないため、施設によって医療行為への対応は大きく異なります。
また、バリアフリーにつとめているとはいえ居室や浴室の設備などに具体的な基準はありません。そのため、医療依存度のほか身体的な介護度が高まった場合も退去を求められることがあります。
施設がある地域の住民票がなければ入居できない
グループホームは、施設と同じ市区町村に住民票がなければ入居できません。これは、グループホームが地域密着施設という性質を持っているためです。
しかし、居住地域に希望するグループホームがない場合もあるでしょう。そのような際は、本来の趣旨からは外れますが「入居するグループホームの市区町村へ住民票を移す」ことで入居できます。
グループホームと他の介護施設との違いは?

ここからは、グループホームと他の高齢者施設との違いを解説します。比較検討することで、自分にはどの高齢者施設が適しているのかが見えてくるはずです。
|
グループホーム |
介護付き有料老人ホーム |
住宅型有料老人ホーム |
サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|---|---|---|---|
初期費用 |
0~数百万円 |
0~数千万円 |
0~数千万円 |
0~数十万円 |
月額 |
12~20万円 |
15~35万円 |
15~35万円 |
10~30万円 |
入居条件 |
|
|
|
|
サービス内容 |
|
|
※介護は外部サービスを利用 |
※介護は外部サービスを利用 |
医療ケア |
医療者の配置は任意 医療は行えない |
日中は常勤看護師の配置あり |
医療職の配置は任意 近隣の医療機関と連携している場合もある |
医療職の配置は任意 |
費用に大きな差はない
上の表を見るとわかるように、今回比較した4種類の施設では平均的な居住費に大きな差はありません。施設種別よりは地域による料金の差のほうが大きいと考えてよいでしょう。
また、初期費用に関しては有料老人ホームがやや高い傾向にあります。しかし、いずれも0~数百万円と差が大きいため、施設種別にかかわらず入居前に「初期費用はいくらなのか、どのような費用が含まれるのか」をしっかりと確認しましょう。
介護サービス費に関しては、住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅のように外部サービスを使用する場合、多くのサービスを必要とする人ほど費用がかさみます。
その点、グループホームでは職員による介護が提供されるため、サービス費が高額になることはありません。
認知症介護に特化している

グループホームは認知症の方が入居する施設です。認知症介護に特化した施設であり、集団生活に大きな支障がない限り、認知機能を理由に退去を求められることはありません。
一方、住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅はあくまでも「住まい」であり、24時間の介護や見守りを提供する施設ではありません。そのため認知症を患っていると入居できない場合もあります。
すでに認知症と診断を受けている場合は、介護付き有料老人ホームかグループホームを中心に検討すると入居できる確率が高くなるでしょう。
介護・医療ケアは施設により対応力に差

グループホームで提供されるサービスは、主に生活のサポートやレクリエーションです。そのため、重度の身体介護には適さない構造の施設もあり、身の回りのことが自立していない人は入居できないことがあります。
また、介護付き有料老人ホームでは看護師の配置が義務づけられているのに対して、グループホームには配置義務はありません。そのため、看護師がいないグループホームも多く、医療処置には対応できない可能性が高いでしょう。
こうしたグループホームでは、医療依存度が上がると退去を求められることがあります。インスリンの投与など医療行為を必要とする人は、候補をグループホームだけに絞らず看護師が常駐している施設を探すことをおすすめします。
その点、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では、外部サービスで対応できる範囲であれば医療処置も受けられます。
グループホームに入居する流れは?
グループホームに入居する際の流れは以下のとおりです。
①問い合わせ・資料請求

まずは、地域にどのようなグループホームがあるのかを調べましょう。
候補先を絞ったら、実際に資料請求や問い合わせを行います。候補が多い場合はまとめて資料請求を行い、疑問点や確認したいことを整理してから直接施設に問い合わせるとよいでしょう。
②見学
気になるグループホームを3~5軒に絞れたら、見学を予約しましょう。見学後は、それぞれのグループホームの職員配置や設備、雰囲気、費用などをまとめ、比較検討します。
もし入居したいグループホームが決まっていたとしても、他の施設と比べることで見えてくる長所や短所があります。そのため、本命の施設を含めて3軒ほど見学することをおすすめします。
③体験入居(空室がある場合のみ可能)
グループホームに空室がある場合は、体験入居できることもあります。入居者の様子や食事・入浴の状況など、実際に住んでみなければ感じられない部分もあるため、可能な場合は積極的に体験入居をしてみましょう。
④契約

入居したい施設が決まったら、施設と契約を結びます。契約前には、費用の詳細・緊急時や受診が必要になった場合の対応・退去しなければならない要件などをしっかりと確認しておくと安心です。
契約では専門用語や複雑なお金の話も出てくるかもしれませんが、重要な内容のため、わからない点は遠慮せず質問しましょう。こうした場面で納得いく説明をしてくれるかどうかも、入居後のトラブルを防ぐために大切なポイントです。
⑤入居
契約締結後、必要な持ち物や書類などを準備し、施設への入居支度を整えます。契約時に持ち物についても説明があるため、その内容に従って衣類や身の回りの生活用品などを用意します。
準備の際は「持っていくべきもの」「持ち込んではいけないもの」をよく確認しましょう。また、わざわざ新調するのではなく、本人の慣れ親しんだ服や日用品などを持っていくと、新しい住まいでも安心して生活できるはずです。
どの老人ホーム・介護施設にしたら良いかお悩みの方へ
満足のいく老人ホームの生活は、どの施設に入居するかで大きく異なることがあります。
安心介護紹介センターの入居相談員は、高齢者の住まいにまつわる資格を有しており、多くの老人ホームの中から、ご本人やご家族のご希望に沿ったぴったりな施設を選定してご紹介させていただきます。
施設のご紹介から、見学、ご入居まで無料でサポートさせていただいておりますので、ぜひご利用ください。
![有料老人ホーム・高齢者住宅を選ぶなら[安心介護紹介センター]](/shokai/assets/images/logo-ansinkaigo.93b7d14a045ed3d060ab.svg)








