老人ホームの費用は年金だけでまかなえる?相場が安い施設種別と、施設探しのポイントを解説
- 2024年10月04日 公開
- 2025年03月11日 更新

老後の生活資金として多くの方が頼りにしている年金。年金を老人ホームの入居費用にあてたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では「年金のみで老人ホームへの入居が可能か」という観点から、候補となる施設の種類や介護費用の軽減方法、年金のみで入居が難しい場合の対策などを詳しく紹介しています。
老後資金に不安がある方や、年金を老人ホームの入居費用にあてたいと考えている方はぜひ参考にしてください。
この記事の監修者
目次
年金だけでも入れる老人ホーム・介護施設はある!

老人ホームへの入居を考えた際、年金を入居費にあてたいと考えている方もいるのではないでしょうか。
老人ホームの中には、年金のみで入居費をまかなえる施設もあります。ただし、加入している年金の種類によっては条件が厳しくなることは理解しておく必要があります。
たとえば支給される年金が「国民年金(基礎年金)」であれば、公的な介護施設が主な候補先となるでしょう。一方、「厚生年金」に加入していた場合は国民年金に上乗せされて支給されるため、選択肢は広がります。
年金だけで老人ホームに入居できるかを知るためには、自分が加入している年金の給付額や施設ごとの特徴・費用を把握することが大切です。
年金だけで老人ホーム・介護施設に入るのは簡単ではない

年金のみで入居できる老人ホームや介護施設は存在しますが、誰でも簡単に入居できるわけではありません。
まず、低価格帯の施設は競争率が高く、申し込みから入居までに長い期間を要する場合があります。
また、月額費用を年金だけでまかなえたとしても、入居後には日用品費や医療費など、別途かかる費用もあるため注意が必要です。
そのため、年金だけで施設入居を希望する場合は、施設の種類や地域ごとの費用相場を把握したうえで、選択肢を広げる工夫が必要です。
年金だけで老人ホーム・介護施設に入れるか確認する2つの手順

老人ホームや介護施設には複数の種類があり、それぞれの施設によって役割や入居条件、費用などが異なります。
入居にどれくらいの予算をかけられるか、まずは自分の年金受給額を確認する必要があります。そのあとに、老人ホームの種類や特徴をよく理解し、自分の理想や予算にあった施設を選ぶようにしましょう。
手順1:年金額を確認する
日本の公的年金制度には、「国民年金」と「厚生年金」の2種類があります。
日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入するのが「国民年金(基礎年金)」で、会社員や公務員が加入するのが「厚生年金」です。
年金制度は「2階建て方式」で1階部分が国民年金、2階が厚生年金という構造です。つまり、厚生年金の加入者は国民の義務である国民年金の保険料に加えて、厚生年金の保険料も支払っていることになります。
そのため、国民年金と厚生年金では支給される年金額に大きな差があるのです。
厚生労働省年金局の「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、国民年金の支給額は平均月額56,358円、厚生年金の支給額は平均月額144,366円でした。
このように「国民年金」と「厚生年金」では年金額に大きな差があることがわかります。
手順2:老人ホームの2つの種類を知る
老人ホームには大きく分けて「公的施設」と「民間施設」の2つがあります。
公的施設は地方自治体や社会福祉法人、医療法人などが設置・運営しており、「介護保険施設」と呼ばれます。
介護保険施設は国からの補助金などをもとに運営されているため民間施設と比べて安価で入居できますが、人気が高く、入居までに長い待機期間が必要な場合があります。
入居するには年齢や要介護度などの条件を満たしている必要があり、基本的に要介護1~3以上の方を対象としています。
一方、有料老人ホームといった民間の高齢者施設は、企業やNPO法人などによって運営されており、施設ごとに入居条件や費用が大きく異なります。
施設数が多いため比較的入居しやすく、生活の自立度や個々のニーズに合わせた施設選びが可能というメリットがあります。
しかし初期費用として入居一時金を支払うケースが多く、公的施設に比べると入居にかかる費用負担は大きくなる傾向があります。
「公的施設」と「民間施設」における入居費用の違い
施設種別 |
初期費用 |
月額費用 |
|---|---|---|
公的 |
なし |
5~20万円 |
民間 |
0~数千万円 |
10~100万円 |
老人ホームの種類別の費用相場

老人ホームの種類別の費用相場と特徴を表にまとめました。
施設の種類 |
費用相場 |
特徴 |
||
|---|---|---|---|---|
初期費用 |
月額費用 |
|||
公 |
特別養護老人 |
なし |
5~15万円 |
|
介護老人保健 |
なし |
6~16万円 |
|
|
介護医療院 |
なし |
7~17万円 |
|
|
ケアハウス |
一般型:0~30万円 介護型:数十万円 |
一般型:6~13万円 介護型:6~20万円 |
|
|
民 |
介護付き有料 |
0~数千万円 |
10~40万円 |
|
住宅型有料 |
0~数千万円 |
13~100万円 |
|
|
サービス付き |
(敷金) 一般型:15~50万円 |
一般型:10~30万円 |
|
|
グループホーム |
0~数百万円 |
15~30万円 |
|
|
公的施設の費用相場
公的施設は地方自治体や社会福祉法人などが設立・運営しており、民間施設と比べると費用が割安のため、人気の高い施設が多いのが特徴です。
利用した介護サービスには介護保険が適用されるほか、収入や所得に応じた負担軽減措置が設けられており、経済的な理由によって必要なサービスが受けられない事態とならないように配慮されています。
まずは、公的施設である「特別養護老人ホーム(特養)」「介護老人保健施設(老健)」「介護医療院」「ケアハウス」の特徴と入居費用について解説します。
特別養護老人ホーム(特養)
特別養護老人ホームは、常に介護を必要とするなど在宅での生活が難しい方が入居の対象となります。
入居できるのは原則、要介護3~5の認定を受けた方です。
特養では、入居者に対して入浴、排せつ、食事の介助などといった日常生活援助や健康管理、療養上の世話などのサービスが提供されます。 民間が運営する有料老人ホームなどと比べると低料金で利用できることから人気が高く、待機者が多いことでも知られています。
長期的な利用を前提として入居する方が多く、「希望があれば施設内で看取る」という方針の施設が大半を占めているため、終のすみ家としての利用も可能です。
ただし、医師や看護師といった医療従事者の常駐は義務づけられておらず、医療体制は充実しているとはいえません。万が一、入居後に状態が悪化し、医療的なケアが必要となった場合は、医療機関への入院や別の介護施設への転居を求められる可能性があります。
入居一時金などの初期費用は不要で、月額費用は5~15万円が相場です。 利用料のうち、施設サービス費には介護保険が適用されますが、居住費・食費・日常生活費などは全額自己負担となります。
保険適用とならない居室代と食費に関しては、所得に応じた自己負担軽減策が設けられています。
介護老人保健施設(老健)
介護老人保健施設は、 病気などによる入院治療を終えた方が自宅での生活に復帰するためにリハビリを行う施設です。
入居対象となるのは、原則65歳以上で要介護1以上の方です。 医師が常勤しているほか、看護師の配置も義務づけられており、胃ろう管理やたんの吸引といった医療的なケアを必要とする方でも入居できます。
ただし、老健は在宅への復帰を目的としているため、自宅での生活が可能と判断されると通常3~6ヶ月を目安に在宅復帰の判定を行い、その後退居の流れとなるため、長期的な入居先として選択肢にいれることはできません。
初期費用は不要で、月額費用は6~16万円が相場です。
介護医療院
介護保険法に基づき、医療と介護の両方を必要とする高齢者が入居できるのが介護医療院です。2017年に廃止が決定した「介護療養型医療施設」の転換先として設立された施設で、医療依存度の高い要介護者の長期療養先として注目されています。
原則、要介護1~5の認定を受けた方が入居の対象となり、他の介護保険施設と同様、介護サービス費には介護保険が適用されます。
医師や看護師をはじめとした医療スタッフが充実しているため、たんの吸引や経管栄養、点滴管理などにも対応しています。また、看取りケアを行う施設も多く、ほとんどの介護医療院で終身利用が可能です。
初期費用は不要で、月額費用は7~17万円が相場です。
ケアハウス
ケアハウスは「軽費老人ホームC型」とも呼ばれ、自治体や社会福祉法人などによって運営される公的な施設です。
ケアハウスには「一般型(自立型)」と「介護型」の2つがあり、それぞれ入居条件やサービス内容が異なります。
「一般型(自立型)」は、生活に不安を抱えた60歳以上の方が入居の対象で、食事の提供や生活支援サービスを受けられます。入居後に介護が必要となった場合は外部の介護サービスを利用することができますが、要介護度が高くなると退居を求められる場合もあるため注意が必要です。
一方「介護型」は特定施設の指定を受けたケアハウスのことで、原則65歳以上かつ、要介護1~5の認定を受けた方が対象となります。生活支援に加えて介護保険制度に基づく介護サービスが受けられ、介護度が高くなっても住み続けられることが特徴の1つです。
ケアハウスは自治体の助成を受けて運営されているため、有料老人ホームなどの民間施設と比べ、低料金で利用できます。
しかし他の介護保険施設と異なり、初期費用が必要です。
初期費用は一般型で0~30万円、介護型で数十万円〜数百万円かかります。月額費用は一般型で6~13万円、介護型で6〜20万円が相場です。
【公的施設ごとの初期費用・月額費用一覧】
施設種類 |
初期費用 |
月額費用 |
|---|---|---|
特別養護老人ホーム |
なし |
5~15万円 |
介護老人保健施設 |
なし |
6~16万円 |
介護医療院 |
なし |
7~17万円 |
ケアハウス |
一般型:0~30万円 |
一般型:6~13万円 |
民間施設の費用相場
.jpg?fm=webp)
有料老人ホームをはじめとした民間施設は、運営母体や施設ごとのコンセプトによってサービス内容も多彩です。
そのため、利用者の細かいニーズに対応しやすいというメリットがある反面、公的施設と比較するとコスト面の負担が大きくなる傾向があります。
また、施設ごとに入居費用が大きく異なるため、施設による違いや契約内容をよく理解し、比較検討することが重要です。
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームは、介護や生活支援などのサービスがついた高齢者向けの居住施設です。
「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている有料老人ホームだけが「介護付き」と表示できます。
施設スタッフによる介護サービスや生活支援が受けられるため、入居後に身体機能が低下して要介護度が高くなっても住み続けることができ、原則、終身利用が可能です。 入居対象となるのは自立から要介護5までと幅広く、認知症の有無にかかわらず利用できます。
月額費用のうち「介護サービス費」には介護保険が適用されますが、法定基準よりも人員配置が手厚い施設では「上乗せ介護サービス費」などが別途加算される場合があります。
さらに、通常の入浴回数が週3回のところを4回に増やすなど、規定以上のサービスを受ける場合にはオプション料金として追加費用が請求されるしくみとなっています。
このように、公的施設と比較すると入居にかかるコストは総じて高くなる傾向があります。 初期費用として0〜数千万円がかかり、月額費用の相場は10〜40万円です。
住宅型有料老人ホーム
有料老人ホームの中で半数以上を占めているのが住宅型有料老人ホームです。一般企業や医療法人、NPO法人などが運営し、施設ごとにコンセプトや料金体制が大きく異なるのが特徴です。
基本的に自立した生活を送れる方や軽度の介護を必要とする方が入居の対象となっており、入居者に対して食事や生活支援、レクリエーションなどが提供されます。
介護サービスの利用を希望する場合は外部の事業所と別途契約を結ぶ必要があり、多くは提携先事業所のサービスを利用します。
費用に関しても施設による違いが大きく、初期費用0円・月額利用料10万円以内と安価な施設もあれば、初期費用が1億円を超える高級な施設もあります。
住宅型有料老人ホームには人員配置基準がないため、介護体制は施設ごとに異なります。
多くの施設では日常的に介護を必要とする方や中・重度の認知症のある方は入居対象外となり、看取りに関しても対応していないところがほとんどです。 初期費用は0円〜数千万円、月額費用は10〜100万円と利用料金は施設によって様々です。
サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅は、安否確認と生活相談サービスがついたバリアフリーの賃貸住宅です。略して「サ高住」とも呼ばれ、入居対象となるのは原則、自立〜軽度の介護を必要とする方です。
サ高住に義務づけられたサービスは安否確認と生活相談のみで、食事の提供や入浴介助などの身の回りの世話は任意のサービスです。
そのためサービス内容は施設ごとに異なり、多くはオプションを設定することで生活支援を受けられるしくみとなっています。
サ高住には、「一般型」と特定施設の指定を受けた「介護型」の2種類があります。 「介護型」は介護付き有料老人ホームのように、介護保険の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けているサ高住のことで、施設スタッフによって介護サービスが24時間提供されます。
サ高住のほとんどは一般型であり、介護サービスや医療行為に関しては外部事業所と契約を結び、訪問介護や訪問看護を利用する必要があります。
サ高住の契約は住宅の賃貸契約と同様であることから、敷金という形で初期費用を負担します。初期費用(敷金)は一般型で15〜50万円、介護型で15〜40万円、月額費用として一般型で10〜30万円、介護型で15〜40万円が相場です。
グループホーム
グループホームは、認知症の高齢者を対象とした地域密着型サービスの1つで、自治体や福祉法人、NPO法人などが運営しています。
認知症の高齢者5〜9人が1つのユニットとしてグループを作り、専門スタッフのサポートを受けながら共同生活を送ります。利用者数の上限は「1つのグループホームに2ユニットまで」と決められているため、定員は最大で18名と少人数制であるところに特徴があります。
入居対象は、認知症のある65歳以上の方のうち要支援2以上の認定を受けた高齢者で、医師から認知症の診断書が発行されている必要があります。また、地域密着型のサービスのため、施設と同じ市区町村に住民票がある方が利用の対象となります。
グループホームでは、専門スタッフのサポートを受けながら本人の能力を活かした日常生活を送ることができるため、認知症の進行を遅らせる効果も期待されています。
初期費用は0〜数百万円、月額費用は15〜30万円が相場となっています。
【民間施設ごとの初期費用・月額費用一覧】
施設種類 |
初期費用 |
月額費用 |
|---|---|---|
介護付き有料老人ホーム |
0~数千万円 |
10~40万円 |
住宅型有料老人ホーム |
0~数千万円 |
13~100万円 |
健康型有料老人ホーム |
0~数億円 |
10~40万円 |
サービス付き高齢者向け住宅 |
(敷金) |
|
グループホーム |
0~数百万円 |
15~30万円 |
地域によって費用は異なる

老人ホームの費用は、施設の種類だけでなく地域によっても大きく異なります。
都市部では土地や建設コストが高いため、入居一時金や月額費用が高額になりやすい傾向があります。
一方、地方では比較的安価に入居できる施設も多く、費用を抑えたい場合には地方の施設を検討するのも一つの選択肢です。
都道府県ごとの老人ホームの費用相場について解説します。
【一覧】都道府県別の費用相場
以下の表では、都道府県ごとの入居一時金と月額費用の平均値および中央値を示しています。
都道府県 |
入居一時金 |
月額費用 |
||
|---|---|---|---|---|
平均値 |
中央値 |
平均値 |
中央値 |
|
北海道 |
50.4万円 |
10.0万円 |
14.0万円 |
13.3万円 |
青森県 |
1.9万円 |
0万円 |
10.7万円 |
9.9万円 |
岩手県 |
66.2万円 |
0万円 |
15.0万円 |
13.6万円 |
宮城県 |
2.5万円 |
0万円 |
9.9万円 |
10.0万円 |
秋田県 |
1.8万円 |
0万円 |
9.9万円 |
9.1万円 |
山形県 |
4.0万円 |
0万円 |
11.1万円 |
10.2万円 |
福島県 |
24.2万円 |
0万円 |
13.9万円 |
13.1万円 |
茨城県 |
126.3万円 |
10.0万円 |
13.0万円 |
11.6万円 |
栃木県 |
18.1万円 |
4.9万円 |
14.4万円 |
13.9万円 |
群馬県 |
3.7万円 |
0万円 |
12.3万円 |
12.4万円 |
埼玉県 |
10.9万円 |
10.3万円 |
15.4万円 |
14.7万円 |
千葉県 |
14.2万円 |
11.1万円 |
12.7万円 |
12.4万円 |
東京都 |
572.3万円 |
128.2万円 |
29.7万円 |
23.4万円 |
神奈川県 |
18.9万円 |
12.0万円 |
14.0万円 |
14.0万円 |
新潟県 |
22.5万円 |
11.0万円 |
15.9万円 |
16.2万円 |
富山県 |
7.0万円 |
6.0万円 |
15.7万円 |
14.3万円 |
石川県 |
11.4万円 |
10.0万円 |
12.3万円 |
11.5万円 |
福井県 |
17.5万円 |
10.0万円 |
13.2万円 |
12.3万円 |
山梨県 |
25.1万円 |
10.0万円 |
14.5万円 |
14.2万円 |
長野県 |
33.8万円 |
14.4万円 |
13.7万円 |
12.7万円 |
岐阜県 |
8.4万円 |
9.4万円 |
12.8万円 |
12.3万円 |
静岡県 |
52.7万円 |
0万円 |
15.9万円 |
14.2万円 |
愛知県 |
15.8万円 |
6.0万円 |
16.6万円 |
14.7万円 |
三重県 |
5.2万円 |
2.5万円 |
11.2万円 |
11.3万円 |
滋賀県 |
4.6万円 |
0万円 |
16.0万円 |
6.6万円 |
京都府 |
179.6万円 |
16.0万円 |
18.9万円 |
16.5万円 |
大阪府 |
6.4万円 |
3.6万円 |
12.5万円 |
12.2万円 |
兵庫県 |
19.4万円 |
0万円 |
15.2万円 |
13.4万円 |
奈良県 |
38.1万円 |
6.5万円 |
13.9万円 |
11.9万円 |
和歌山県 |
11.2万円 |
11.1万円 |
11.8万円 |
10.4万円 |
鳥取県 |
18.0万円 |
9.0万円 |
13.7万円 |
13.8万円 |
島根県 |
12.1万円 |
2.5万円 |
13.8万円 |
14.1万円 |
岡山県 |
7.4万円 |
8.0万円 |
12.1万円 |
11.3万円 |
広島県 |
8.1万円 |
1.5万円 |
12.4万円 |
12.4万円 |
山口県 |
4.2万円 |
1.5万円 |
12.1万円 |
12.2万円 |
徳島県 |
1.5万円 |
0万円 |
10.5万円 |
10.2万円 |
香川県 |
6.1万円 |
0万円 |
12.9万円 |
12.5万円 |
愛媛県 |
2.2万円 |
0万円 |
10.1万円 |
9.4万円 |
高知県 |
3.1万円 |
0万円 |
11.4万円 |
9.3万円 |
福岡県 |
3.5万円 |
0万円 |
9.8万円 |
9.5万円 |
佐賀県 |
2.5万円 |
0万円 |
10.8万円 |
10.0万円 |
長崎県 |
5.9万円 |
0万円 |
12.1万円 |
11.5万円 |
熊本県 |
10.4万円 |
9.5万円 |
11.4万円 |
11.1万円 |
大分県 |
6.1万円 |
0万円 |
10.0万円 |
8.4万円 |
宮崎県 |
1.2万円 |
0万円 |
7.7万円 |
7.2万円 |
鹿児島県 |
0.6万円 |
0万円 |
8.3万円 |
7.7万円 |
沖縄県 |
3.0万円 |
0万円 |
9.9万円 |
9.3万円 |
平均月額費用が高い都道府県トップ5
- 東京都 (29.7万円/月)
- 京都府 (18.9万円/月)
- 愛知県 (16.6万円/月)
- 滋賀県 (16.0万円/月)
- 静岡県・富山県 (15.9万円/月)
都市部では土地や施設運営のコストが高く、月額費用が割高になる傾向があります。
特に東京都や京都府では、月額費用18万円以上で、入居一時金も数百万円単位になることが多いです。
平均月額費用が安い都道府県トップ5
- 宮崎県 (7.7万円/月)
- 鹿児島県 (8.3万円/月)
- 福岡県 (9.8万円/月)
- 宮城県・秋田県・福岡県 (9.9万円/月)
- 大分県 (10.0万円/月)
地方では土地や運営コストが低いため、月額費用も抑えられる傾向にあります。
都市部と比べて大幅に低く、入居一時金も少額または不要な場合が多いです。
このように、老人ホームの費用は、施設の種類だけでなく地域によっても大きく異なります。
都道府県によって平均月額費用で20万円以上もの差があるため、地方の施設に入居することで費用を抑えることができます。
老人ホームの費用として年金のみをあてにするデメリット3つ

老後の収入源のメインともいえる「年金」ですが、老人ホームの入居にかかる費用すべてを年金でまかなおうとすると、いくつかのデメリットが生じる可能性があります。どのような点に注意すべきなのか、しっかり把握しておきましょう。
年金受給額が減ってしまう可能性がある
年金の支給は通常65歳から開始されますが、希望すれば60歳から70歳の範囲で受給開始時期を設定できます(2022年4月から繰り下げ期間は75歳まで延長可能)。
年金受給の開始時期を早めることを「繰り上げ受給」といいます。繰り上げ受給とは、1カ月支給を早めるごとに年金額が0.5%ずつ減額されるしくみです。なお、一旦繰り上げ請求をすると取り消しはできず、減額された年金額が一生涯続きます。(2022年4月以降は減額率が0.4%へと変更)。
たとえば60歳から年金受給を開始した場合の減額率は、 0.5%×(12カ月×5年)=30% となり、基本の年金額が100万円だとすると70万円に減額されます。
反対に、年金の受給開始を先延ばしにすることを「繰り下げ受給」といい、一カ月支給を遅らせるごとに年金額が0.7%ずつ増額されます。たとえば70歳まで受給開始を遅らせた場合の増額率は、 0.7%×(12カ月×5年)=42% となり、基本の年金額が100万円だとすると142万円に増額されます。
老人ホームの入居費用にあてるために繰り上げ受給を選択した場合は、もらえる年金額が減ってしまうことを念頭に置いておきましょう。
一方、老後資金に余裕があれば繰り下げ受給を選択して年金額を増やすのも1つの方法です。
医療費など施設以外の出費の可能性がある
老後生活に必要な費用として、介護サービス費や食費、居住費といった毎月の支出とは別に医療費の負担が大きくなる可能性があります。
一般に、年を重ねるほど医療機関にかかる機会は増えていきます。2018年に実施された厚生労働省の「生涯医療費」に関する調査によると、一人当たりの医療費は2700万円とされており、その約半分は70歳以降にかかるといわれています。
つまり、収入が減少する70歳以降に1,300万円ほどの医療費がかかる計算になります。
実際に支払う金額は自己負担の部分で済むため130~390万円ほどですが、それでも老後の家計には大きな負担となります。
一定以上の収入がある75歳以上の高齢者の医療費については、すでに2022年10月から窓口負担を1割から2割に引き上げる方針が示されており、今後さらなる医療費の負担増が予測されるため、医療費をはじめとした予備費を準備しておくと安心です。
自分のタイミングで入居できない可能性がある
年金を老人ホームの入居費用にあてようと考えた場合、年金額から割り出した予算から入居できる施設を探すことになります。
多くの方が、できるだけ低コストの介護施設に入居したいと考えるため、比較的安価に利用できる介護保険施設は競争率が高くなり、待機期間が長くなる傾向があります。
そのため、自分が希望するタイミングで入居できない可能性も十分考えられるでしょう。
費用を抑えた施設選びのポイント4つ

老人ホームの入居費用には「公的施設」と「民間施設」といった運営主体や役割の違いのほかにも、立地条件や築年数、居室タイプの違いなどによる差があります。
ここでは、老人ホームの費用を抑えるためのコツを4つ紹介します。
郊外や地方の施設に目を向ける
1つ目は、料金の安い地方の施設を候補に入れることです。同じようなサービスを提供する老人ホームでも、地域によって料金は大きく異なります。
その理由は、土地の価格や立地条件、物価などの影響を受けるためです。 たとえば、東京都や神奈川県などの都市部では入居費用が高く、佐賀県や三重県などの地方では比較的入居費用が安い傾向にあります。
老人ホームへの入居費用を安く抑えたい場合には、相場の安い地域にある施設を候補とするのも1つの方法です。料金が安価である以外にも、都市部に比べて待機者数が少なく、入居しやすいといったメリットもあります。
個室ではなく多床室も検討する
2つ目は、居室タイプの違いによる料金の違いに注目し、低コストの多床室を選ぶことです。
老人ホームは、居室のタイプによって利用料金が異なります。居室タイプには、多床室、従来型個室、ユニット型個室的多床室・ユニット型個室の4種類があり、ユニット型個室と多床室では料金に大きな差があります。
居室タイプは居室費そのものにも影響しますが、介護保険が適用される施設サービス費にも関係しています。
一番安価なのは1部屋2~4人で生活する多床室ですが、プライバシーを保つことが難しいなどのデメリットもあることは理解しておきましょう。もし、本人の性格や希望条件に合えば、多床室タイプを選択することで費用を抑えることが可能です。
アクセスが悪い施設も検討する
3つ目は、交通アクセスの悪い施設を選択することです。
老人ホームの費用は、一般的な住宅と同様に土地の価格や立地条件に影響を受けるため「駅から遠い」「車でしか通えない」など交通アクセスが不便な施設は居住費を抑えられる可能性があります。
郊外にある施設だからといって、サービスの質が落ちるわけではありません。
アクセスが不便な場所にあっても、自然豊かな環境が入居者にとっての癒しとなる可能性もあるでしょう。
ただし、「緊急時に駆けつけることができない」「家族が面会に通いづらい」などのデメリットが生じる可能性があるため、入居後の生活を想定して検討することが大切です。
築年数が古い施設も検討する
4つ目は、築年数が経過して価格が安くなった施設を検討することです。
老人ホームの費用は、「建物の豪華さ」や「立地の違い」「サービス内容の違い」などによって差が生じます。 当然、建物が豪華で新しい方が料金は高く、築年数の経過した古い施設は低めに料金が設定されています。
また、設備の充実したきれいな施設に入りたいと考える方が多いため、築年数の経った老人ホームでは料金が安価でも定員割れを起こしているケースがあります。
そこで、あえて築年数の経過した施設を選択することで、入居費用を抑えることが可能です。
年金だけで老人ホームに入居できない場合の対処法5つ

年金だけで老人ホームに入居するのが難しい場合、生活保護や低所得者向けの助成制度の利用が可能です。
年金額が少なく、入居できる施設が見つからないという方に向けて、老人ホームの入居費用を抑えるための対処法について5つ紹介します。
生活保護を利用する
生活保護は、生活に困窮している方の最低限の生活を保障して自立をサポートする制度です。生活保護では最低限の暮らしを営むために必要なサービスを受けることができます。
介護サービスは「介護扶助」として自己負担額0円で受けられます。ただし、要介護度別に定められた介護サービス費の支給限度額を上回った場合や、介護保険適用外のサービス費用は自己負担となるため注意が必要です。
介護保険サービスの助成制度を利用する
「介護保険サービスの助成制度」とは、要支援・要介護の認定を受けて介護保険サービスを利用する方のうち、経済的な理由で利用料の負担が困難な場合に利用料の一部を助成するしくみです。
制度を利用できるのは基本的に市町村民税非課税世帯の方ですが、高額介護サービス費の支給対象になった部分については対象外となります。
また、介護保険サービスの助成制度は各自治体によって定められているため、対象となるサービスや利用条件、費用の軽減額は自治体ごとに異なります。
高額介護サービス費
1カ月の介護サービス利用者負担額が一定の金額(負担限度額)を超えた場合に差額が払い戻されるしくみを「高額介護サービス費制度」といいます。
要支援・要介護認定を受けた方が対象で、利用者負担限度額は所得に応じて決められています。たとえば、生活保護を受けている方であれば、1世帯あたりの利用者負担限度額は月額15,000円です。
つまり、介護サービス利用料が負担限度額を超えた場合、上回った金額が払い戻されることになります。
ただし、支給限度額を超えたサービス利用料や住宅改修費、福祉用具購入費、食費、居住費、日常生活費などは対象に含まれないため注意が必要です。
特定入所者介護サービス費
「特定入所者介護サービス費」とは、介護保険が適用される施設に入居している方で所得や資産が一定以下の場合に適用される低所得者のための負担軽減制度です。負担限度額を超えた分の居住費と食費が介護保険から支給されます。
利用者負担段階は、本人や配偶者などの所得や資産によって5段階に分けられています。たとえば、最も負担の少ない第1段階では食費が300円、居室費は多床室で0円、ユニット型個室で820円といった具合に1日あたりの負担限度額が決められています。
高額介護合算療養費制度
「高額介護合算療養費制度」は、1年間(8月~翌年7月)の医療費と介護サービス費の自己負担額を合算し、所得に応じた上限額を超えた場合に超過分が払い戻される制度です。医療の「高額療養費」と、介護の「高額介護サービス費」だけでなく、医療と介護の費用を合算して負担を軽減することができます。
対象となるのは介護保険や医療保険が適用される費用のみで、施設の居住費や食費などは対象外です。
申請は健康保険組合や国民健康保険など、医療保険の加入先に行います。
家族ができることなら家族が助ける
家庭環境や就労状況などにもよりますが、家族のサポートによって自宅で暮らし続けることによって介護費用の負担を軽減できます。
要介護度の軽いうちは、身の回りの世話などを家族が手助けすることによって、自宅での生活を続けられる可能性があります。
とはいえ、日本では核家族化や少子化が進み、共働きの世帯も増えているため、介護にかけられる時間や介護者の人数が減少しているのも事実です。
要介護度や認知症の重症度などによっては、介護負担の増加により共倒れとなってしまう可能性もあるため、無理は禁物です。
在宅介護サービスを検討する
在宅介護サービスは、自宅で療養生活を送る要支援・要介護者が利用できる制度です。このサービスは、介護保険制度上の居宅介護サービスにあたり、訪問、通所、短期入所の3種類があります。
訪問系で代表的なサービスは、訪問介護(ホームヘルプサービス)です。訪問介護は介護ヘルパーが自宅を訪れ、体調観察やオムツ交換などの身体介護、調理や掃除などの生活援助といった個々のニーズに応じたサービスを提供します。
そのほか、デイサービスやショートステイも在宅介護を支える重要なサービスです。 これらの在宅介護サービスを活用して在宅生活を継続することができれば、施設に入居するよりもコストを抑えることができます。
世帯分離を検討する
世帯分離とは、住民票に登録されている同一世帯を2つ以上の世帯に分けることです。
たとえば、親と子が同居している世帯でも、それぞれの収入源が異なる場合は同じ住所に世帯主を2人置くことができます。
介護にかかる費用は個人ではなく世帯としての所得を算定基準としているものが多く、世帯分離を行うことで介護サービス費用を節約できる場合があります。
しかし、国民健康保険に加入している世帯の場合は各世帯主がそれぞれ保険料を支払うことになるため、負担額が大きくなる可能性があるなど、マイナス面も理解した上で選択すべきでしょう。
年金以外で老人ホームの資金を捻出する3つの方法
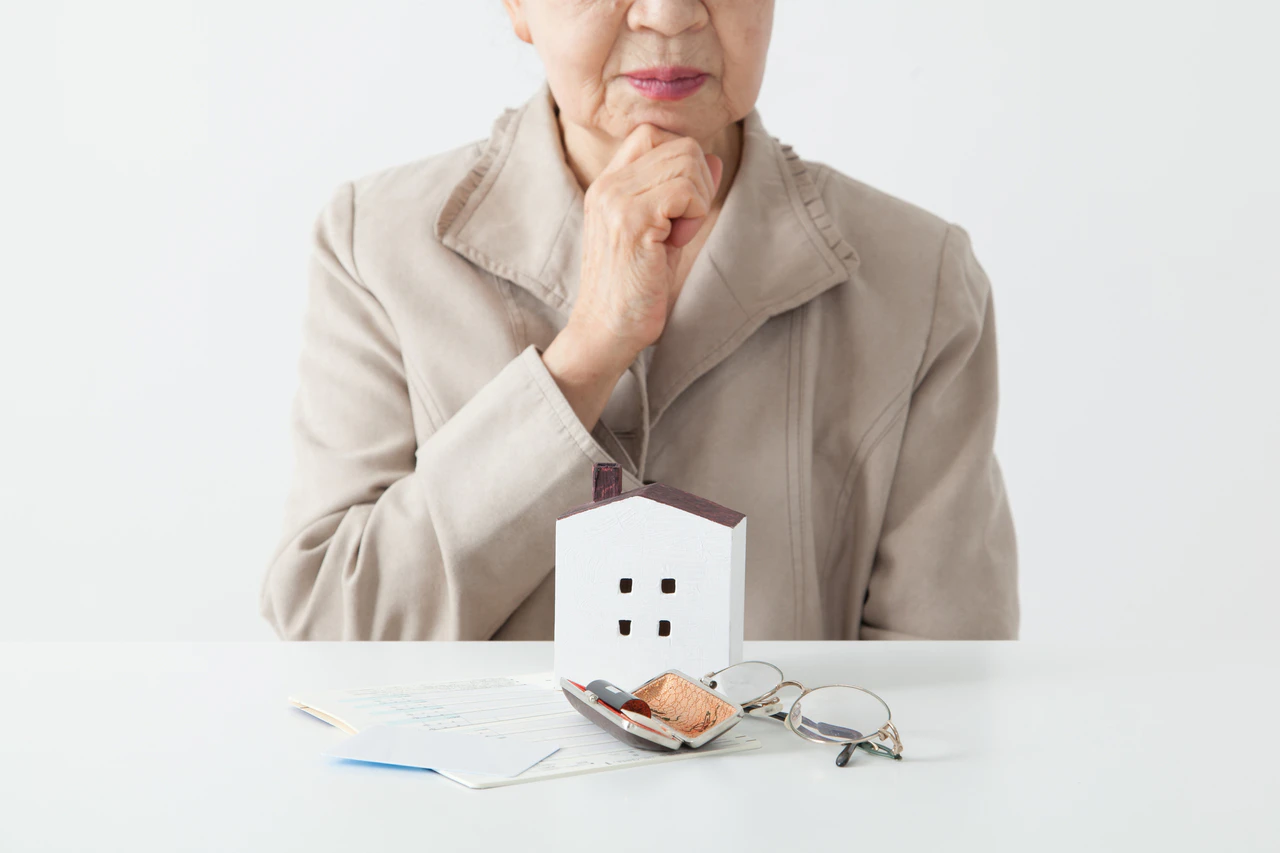
厚生労働省が発表した「国民生活基礎調査(2018年)」によると、高齢者世帯の約半数が「生活が苦しい」と回答しています。老後の生活に困窮する高齢者は増加しており、年金を老人ホームへの入居費用にあてたいと考える方もいるでしょう。
しかし、年金のみで入居できる施設を探すとなると選択肢は限られてしまいます。早い段階から計画的に老後の資金対策を行うことで、老後の生活を送る場所の選択肢も広がります。 ここでは年金以外で資金を捻出する3つの方法を紹介します。
生活費を見直して貯金する
1つ目は、日々の生活費を見直して支出を減らすことです。老後の支出が抑えられない原因の1つは「生活レベルを落とせない」こと。現役時代と同じ感覚でお金を使ってしまうと、収入が減っている分、家計が赤字へと傾きやすく、あっという間に老後資金が底をついてしまいます。
生活費の中で、とくに大きな割合を占めるのが毎月・毎年必要になる固定費です。家賃や通信費、光熱費、保険代などの固定費を見直すことで、支出を抑えられる可能性があります。
できるだけ長く働き貯金する
2つ目は、定年後も再雇用・再就職によってできるだけ長く働くことです。現役時代と比較すると収入は下がりますが、働き続けることで収入源を増やし、年金の受給期間を短くすることが可能です。
国としても、少子高齢化や老後の生活資金対策として「希望すれば仕事を続けられる環境づくり」を推進する動きがあり、総務省統計局の労働力調査でも65歳以上の就労人口は年々増加しています。
厚生年金は70歳まで加入することができるため、会社員として働き続ければ年金の受給額を増やすことができ、さらに配偶者を扶養に入れることで社会保険料の節約にもつながります。
給与収入がある間は、年金に頼ることなく生活できることも大きなメリットです。また、年金の受給を遅らせる繰り下げ受給を選択することで、受け取る年金額を増やすこともできます。
不動産売却前提ローンを利用する
3つ目は「不動産売却前提ローン」を利用して自宅を売却し、老人ホームへの入居資金にあてる方法です。
「不動産売却前提ローン」は売却予定の不動産を担保に資金を調達し、不動産の売却代金を返済にあてるローンのこと。買い手が決まる前に融資が受けられるというメリットがあります。自宅が売れるまでの期間は利子部分のみを支払い、買い手が決まったら自宅を売却した資金でローンを返済するしくみです。
不動産売却前提ローンの主な目的は、不動産の買い手が決まるまでのつなぎ融資です。
そのため、ローンの返却期限が2年程度と短期間に設定されている場合が多く、延長できないというデメリットがあります。
また、万が一買い手がつかなかった場合には、返済日までに融資額を一括返却しなければなりません。利用に際してはメリットとデメリットの両方をよく理解して利用しましょう。
老後の生活に必要な費用
.jpg?fm=webp)
老後の生活費は、現役時代と大きく変わるわけではありませんが、医療費や介護費の増加が懸念されます。
住居費や生活費はほぼ維持される一方で、年齢を重ねると通院が増え、介護が必要になった場合の支出が大きくなるため、事前の資金準備が重要です。
ここでは、「介護が必要な場合」と「介護が必要でない場合」の費用について解説します。
介護が必要な場合の費用
介護が必要になると、在宅介護か施設介護のどちらかを選ぶことになります。
介護保険を利用すると費用を抑えられますが、所得に応じた自己負担が発生するため、どの程度の資金が必要か把握しておくことが大切です。
在宅介護の費用
- 住宅改修費(手すり設置など):1万~6万円
- 訪問介護:5,000円~1.5万円/月(週1~3回)
- デイサービス:8,000円~2万円/月(週2~3回)
- 福祉用具レンタル:500円~3,000円/月
施設介護の費用
- 特別養護老人ホーム(特養):5万~15万円/月
- 介護付き有料老人ホーム:10万~40万円/月
- グループホーム:12万~20万円/月
介護が必要でない場合の費用
介護が不要でも、住居費や生活費、医療費などの支出が継続します。
特に年齢とともに通院や薬、検査なども多くなるため、医療費の負担が増えます。
計画的な準備が必要です。
自宅で暮らす場合の費用
- 生活費(食費・光熱費・通信費など):12万~20万円/月
- 医療費(通院・薬代など):5,000円~2万円/月
- 住居費(持ち家の維持費・賃貸の家賃):5,000円~10万円/月
高齢者向け住宅に入居する場合の費用
- サービス付き高齢者向け住宅
- 入居一時金:15万~50万円
- 月額費用:10万~30万円
- シニア向け分譲マンション
- 購入費:500万~数千万円
- 管理費・修繕費:5万~10万円/月
老後の生活費は、介護が必要ない場合でも月15万~30万円、介護が必要な場合は月20万~50万円以上になる可能性があります。
介護保険を利用しても自己負担は発生しますので、医療・介護にかかる費用を見越した資金計画が重要です。
住居費や趣味・交際費も考慮し、自分がどんな老後を送りたいかを踏まえて準備を進めましょう。
老後の資金計画を立てておくことが大切

老後の生活を安心して送るためには、年金以外の資金準備が必要です。
貯蓄や投資、保険など、さまざまな方法があり、それぞれ特徴が異なります。
ここでは、老後資金を準備するための代表的な手段を紹介します。
-
個人年金保険
保険会社が提供する私的年金制度。
一定期間保険料を支払い、老後に年金として受け取る。
契約内容により、確定年金や終身年金など、受け取り方を選択できる。
税制優遇があり、公的年金の補助として活用されることが多い。 -
NISA
投資の運用益が非課税になる制度。
株式や投資信託を運用しながら資産形成を目指せる。少額から始められ、長期運用向けの「つみたてNISA」は老後資金作りに適している。
非課税期間や投資枠に制限があるため、計画的な運用が必要。 -
iDeCo
自分で積み立てる私的年金制度。
掛金は全額所得控除の対象となり、運用益も非課税となるため節税効果が高い。
60歳以降に年金または一時金として受け取る。
年金額を自分で増やせる一方、60歳まで引き出せない点に注意が必要。 -
投資信託
複数の資産に分散投資できる金融商品。
運用はプロが行い、個人でも少額から投資できる。
NISAやiDeCoと組み合わせることで、効率的な資産形成が可能。
価格変動によるリスクがあるため、長期運用向け。 -
個人向け国債
政府が発行する債券で、元本が保証される低リスクの資産運用方法。
最低1万円から購入でき、満期まで保有すれば確実に利息が受け取れる。
安全性が高いが、金利が低いため大きな利益は期待できない。 -
民間の介護保険商品
将来、介護が必要になった際に給付金を受け取れる保険。
要介護状態になると一定額が支給されるものや、介護サービス費用を補助するタイプがある。
介護費用の負担を軽減できるが、支払う保険料が高めな場合もある。 -
ハウス・リースバック
自宅を売却し、そのまま賃貸として住み続ける仕組み。
持ち家を現金化できるため、老後資金を確保しつつ生活環境を変えずに済む。
売却価格が市場相場より低くなる傾向があるため、利用前に十分な検討が必要。
老後の資金を準備する方法には、保険・投資・貯蓄など多様な選択肢があります。
どの手段を選ぶかは、ライフスタイルによって異なるため、早めに計画を立てて準備を進めることが大切です。
どの老人ホーム・介護施設にしたら良いかお悩みの方へ
満足のいく老人ホームの生活は、どの施設に入居するかで大きく異なることがあります。
安心介護紹介センターの入居相談員は、高齢者の住まいにまつわる資格を有しており、多くの老人ホームの中から、ご本人やご家族のご希望に沿ったぴったりな施設を選定してご紹介させていただきます。
施設のご紹介から、見学、ご入居まで無料でサポートさせていただいておりますので、ぜひご利用ください。
![有料老人ホーム・高齢者住宅を選ぶなら[安心介護紹介センター]](/shokai/assets/images/logo-ansinkaigo.93b7d14a045ed3d060ab.svg)








