介護老人保健施設の選び方ー失敗しないポイント
- 2024年10月04日 公開

後悔しない老人保健施設(老健)選びで大切なのは、事前に条件を整理し、情報をしっかり集めることです。
今回は老健への入所を考えた時、押えておくべき老健の特徴やサービス内容、費用といった老健の選び方のポイントについて詳しく説明します。
この記事の監修者
老人保健施設を選ぶ前の事前準備
高齢者施設にはたくさんの種類があり、自分に適している施設がわかりづらいという方も多いのではないでしょうか?
今回は、公的な高齢者施設の一つである老人保健施設(老健)の選び方のポイントについてご紹介します。
老健への入所を検討する際に大切なのは事前に施設側に求める条件を整理することです。
しかし「急に退院が決まった」など、施設の選定に充分な時間をかけられないケースもあります。
「定員に空きが出たから」と焦って入所を決めてしまったために「こんなはずではなかった」と後悔してしまう方もいます。
後悔のない施設選びのために、老健への入所を考えた時に押えておくべきポイントについて詳しくみていきましょう。
老健に希望する条件を整理

自分にあった入所施設を選ぶ第1ステップは、施設に求める条件を整理することです。
はじめに、老人保健施設(老健)の特徴や強み、費用や立地条件、受けられるサービスなどをチェックしていきましょう。
月額費用

老人保健施設(老健)は、介護保険が適用される公的な高齢者施設であり、初期費用の入居一時金は不要です。
利用には居住費や食費、介護サービス費、サービス加算、その他費用などがかかり、月額費用の平均は約8~15万円程度となっています。
民間の有料老人ホームなどと比較すると、経済的な負担は少なく済むでしょう。
立地条件

どのような環境が入居施設として好ましいかは、その方がこれまで暮してきた環境によっても異なります。
緑に囲まれた静かな環境が落ち着く方もいれば、都会で長年暮してきた方にとっては静かすぎる環境が逆にストレスとなるかもしれません。
入居者が心穏やかに過ごせる立地条件の施設を選ぶのが理想的です。
また、施設と自宅の距離やアクセスのしやすさも重要だといえます。
施設への入所は、慣れ親しんだ自宅とは別の環境で、新しい生活がスタートするということです。
環境になじむまでは精神的に不安定になったり、淋しい想いをしている方も多くいます。
遠方でめったに面会にいけない、何かあった時でもすぐには駆けつけらないという状況は避けた方が良いでしょう。
また、買い物や洗濯といった生活援助が介護サービスに含まれない場合、家族による援助か業者に代行してもらう必要があります。
家族による生活援助が必要となる可能性も考えると、通いやすい立地条件の施設を検討するのがおすすめです。
介護内容

老人保健施設(老健)では、入所者100人に対し25人以上の介護職員の配置が義務付けられています。
介護サービスの内容は、一人ひとりの身体状況やニーズに合わせた食事介助や排泄介助、入浴介助といった身の回りの世話など、日常生活全般のサポートや安否確認などです。
そのほか、居室の掃除や洗濯といった生活支援サービスが受けられます。
(施設によって生活支援サービスの内容は異なります)
医療・リハビリ体制

スタッフ配置基準に関して、老健に常駐する医師は入所者100人の定員に対して1人以上と決められています。
看護師の配置基準は、入所者3人に対し看護師または介護職員が1人以上、看護師と介護職員の総数の7分の2、つまり、入居者100人に対して看護師が9人、介護職員は25人配置される計算です。
また、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士といったリハビリ専門スタッフは入所者100人に対して1人以上配置することが義務付けられています。
一概にリハビリスタッフといっても、それぞれによって専門とする分野やアプローチ方法が異なるため、簡単に説明します。
理学療法士は、起き上がる、立ち上がる、歩くといった日常生活の基本となる動作の回復や維持、悪化の予防を目的とし、運動療法や物理療法を行う動作の専門家です。
作業療法士は運動や認知機能等の基本的動作や、家事や更衣等の日常行う様々な活動である応用的動作、社会的適応能力の維持や改善に加えメンタルケアの支援も行います。
言語聴覚士は「しゃべれない」「食べられない」といった言語障害や嚥下障害などを持つ方を対象にリハビリを行い、自分らしい生活を構築できるように支援する「話す、聞く、食べる」のプロフェッショナルです。
このように、医療スタッフやリハビリスタッフが充実しており、機能訓練のための器具や設備も整っています。
そのため「専門的知識に基づいたリハビリがしたい」という方に適した施設と言えるでしょう。
情報を収集する

施設に求める条件を大まかに整理できたら、情報を集めていきましょう。
ここでは、老人保健施設(老健)の情報収集の方法についてご紹介します。
インターネットで調べる
まず、気軽に情報を得られる方法として、インターネットを活用した情報収集があります。
すでに候補となりそうな老健があれば、施設を運営する医療法人や社会福祉法人のホームページをのぞいてみましょう。
施設のホームページには、運営方針やイベントなどが紹介されている場合が多く、大まかな雰囲気を掴むのに役立ちます。
また、実際に施設を利用した方や家族による口コミ投稿やユーザー評価が閲覧できるサイトなどからも広く情報を集め、施設の比較検討に活用しましょう。
近隣にどのような老健があるかわからない段階では、一覧で近隣施設を調べられる自治体のホームページなども役立つでしょう。
資料請求を行う
候補の施設が絞られてきたら資料請求を行い、パンフレットなどから情報を得る方法もあります。
最近では、ホームページから簡単に資料請求できる施設も増えています。
見学に行く
入所施設を決めるにあたって、事前の施設見学は必須です。
ある程度情報が集まり、候補が絞られてきたら、数カ所の施設を見学し比較すると良いでしょう。
見学では、ホームページやインターネット上の口コミではわからない、実際の雰囲気や職員・入居者の様子といった生の情報を得られます。
見学の際は事前にアポイントをとってから訪問しましょう。
見学時に注目すべきポイントについては、後ほど詳しくご紹介します。
専門家に相談
介護保険を利用している方は、担当ケアマネージャーや地域包括センターが相談窓口となります。
担当のケアマネージャーは介護保険制度を熟知し、地域の高齢者施設などに関しての情報にも詳しい可能性が高いです。
また、個別的な身体状況や人柄、家庭状況なども把握しており、相談相手として頼りになる存在といえます。
病院に入院中の方で、退院後すぐに在宅での生活が難しい場合には、病院の医療ソーシャルワーカーに相談することも可能です。
老人保健施設の生活とは

この章では、老人保健施設(老健)に入所した場合の生活についてご紹介します。
一日の流れ
老健に入所している利用者はどのような生活を送っているのでしょうか?
とある老健の一日の流れについて時系列で見ていきましょう。
介護保険を利用している方は、担当ケアマネージャーや地域包括センターが相談窓口となります。
担当のケアマネージャーは介護保険制度を熟知し、地域の高齢者施設などに関しての情報にも詳しい可能性が高いです。
また、個別的な身体状況や人柄、家庭状況なども把握しており、相談相手として頼りになる存在といえます。
病院に入院中の方で、退院後すぐに在宅での生活が難しい場合には、病院の医療ソーシャルワーカーに相談することも可能です。
老人保健施設の生活とは

この章では、老人保健施設(老健)に入所した場合の生活についてご紹介します。
一日の流れ
老健に入所している利用者はどのような生活を送っているのでしょうか?
とある老健の一日の流れについて時系列で見ていきましょう。
7:30 |
朝食 |
|---|---|
9:00 |
健康チェック |
9:30 |
リハビリテーション |
10:00 |
入浴 |
11:30 |
昼食 |
13:00 |
リハビリテーション・レクリエーション |
15:00 |
おやつ |
18:00 |
夕食 |
20:00 |
就寝(ナイトケア) |
入居者は、このようなスケジュールで生活します。
居室の種類
老健の居室の種類には、従来型個室、多床室、ユニット型個室、ユニット型個室的多床室の4つがあり、老健の入所費用は居室の種類によっても変わります。
従来型個室は、1つの部屋に対し、1人が利用する個室タイプ。
多床室は、大部屋を2~4人が共同で利用する相部屋タイプ。
ユニット型個室は「ユニット」とよばれる10名程度の少人数のグループで、1つの共同スペースを共有する居室のタイプです。
それぞれの居室は個室となっており、共有スペースから各個室へと移動できるように設計されています。
ユニット型個室的多床室は、ユニット型個室と同様に共同スペースを共有しますが、それぞれの個室を利用するのではなく、大部屋を間仕切りでわけて、準個室という扱いでそれぞれに部屋が用意されます。
介護サービスについて
老健では、24時間常駐する介護スタッフによって必要なサービスが提供されます。
介護サービスの内容は、食事介助、排泄介助、入浴介助や衣服の着脱などの身体介護や環境整備などの日常生活の援助などです。
介護サービスは、介護職員によって提供されます。
機能訓練について
老健に求められている主な役割は、積極的にリハビリを行い、在宅での生活を可能にすることです。
そのため、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士といったリハビリ専門スタッフの配置が義務付けられており、身体状況に合わせた専門的なリハビリが実施されます。
老健で行われるリハビリテーションは、それぞれの身体状況に応じて立案されたリハビリテーション計画書をもとに、週2回以上20~30分程度の時間で実施されます。
なお、最初の3カ月間は週3回以上のペースでリハビリを受けられる場合もあります。
リハビリの内容は、起き上がり動作や車いすに乗り移る練習、歩行訓練など、日常生活に欠かせない動作練習や食事や更衣等の日常生活で行う応用的動作、言語コミュニケーションや嚥下機能等、個人の状態に応じた内容で行われます。
老健選びの失敗しない4つのポイント

老健選びの際に、チェックしておくべき4つのポイントについて見ていきましょう。
入居の費用
公的な高齢者施設である老健は入居一時金などの初期費用は必要ありません。
入所後に介護サービス費、食費、居住費(家賃)、サービス加算、その他の費用を毎月負担します。
施設によって異なるサービス内容や居室のタイプによっても料金には違いがあり、手厚いサービスを受けられる施設ほど負担も大きくなるといった特徴があります。
ここからは、それぞれの費用にわけて解説したあと、利用者の負担軽減のために利用できる制度についてご紹介します。
介護サービス費
食事介助や排泄介助など身の回りの介護にかかる費用を介護サービス費といい、介護度が高くなるほど負担額も増加します。
介護サービス費は、介護保険が適用され、所得に応じて1~3割の自己負担分を支払います。
介護保険でまかなえる費用の上限額は要介護認定によって異なり、要介護5が最も高額です。
食費
食費とは、一日3食の食事提供にかかる費用で、食材費や調理費などが含まれます。食費は一日当たり300円〜1,445円で所得に応じて定められた負担段階によって異なります。
食費は介護保険が適用されませんが、自己負担分は医療費控除の対象です。
老健では、所得に応じて国によって定められた食費の基準額を支払いますが、低所得の方がサービスを受けられなくなる事態に陥らないように、負担軽減のため所得に応じて負担限度額が定められています。
居住費
居住費(部屋代)は、居室のタイプにより料金に違いがあります。
費用は多床室が一番安く、従来型個室、ユニット型個室的多床室、ユニット型個室の順に金額が高くなります。
プライバシーを確保したい方には個室タイプがおすすめですが、大部屋と比較すると費用は割高です。
例えば、第一段階の生活保護受給者の場合、負担の一番少ない従来型多床室の利用が基本になり、居住費の負担は0円となります。
軽減措置などを行うことで、ユニット型個室にも入居可能ですが、あまり一般的ではありません。
食費と同様に居室費についても介護保険は適用されず、全額自己負担です。
ただし、こちらも医療費控除の対象となり、低所得者のための負担軽減策も設けられています。
サービス加算
老健における介護サービス加算とは、職員の配置や体制、提供されたサービス内容によって上乗せされる追加料金を指します。
サービス加算には、排泄支援加算や短期集中的リハビリテーション実施加算、認知症ケア加算、サービス体制強化加算などがあります。
これらは、利用者の状況に応じたサービス提供や施設の体制に対して支払う追加料金で、介護サービス費と同様に介護保険が適用されます。
手厚いサービスを提供している施設ほどサービス加算がプラスされるため、利用者の負担は増加します。
これらのサービス加算は、利用した分を所得に応じて定められた負担割合によって月額費用に上乗せし、請求されます。
生活支援サービス
老健は、介護サービスが受けられますが、一方で洗濯や買い物といった生活支援サービスが十分に提供されない場合があります。
そのため、家族が遠方でなかなか面会に来られない場合には、業者に代行してもらうための費用が別途発生します。
医療費控除
老健の利用で負担する費用の中には、医療費控除の対象となるものがあります。
対象となるのは、介護サービス費、食費および居住費に関して自己負担額として支払った金額です。
次に紹介する高額介護サービス費として払い戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除額を計算します。
なお、医療費控除を受けるには確定申告が必要です。
高額介護サービス費
高額介護サービス費とは、介護保険が適用される介護サービスを利用した際の自己負担額が高額になった場合に利用者の負担を軽減する制度です。
高額介護サービス費制度の対象となるのは、自治体から「要支援・要介護認定」を受けた方のみで「自立」と判定された方は対象になりません。
支給対象となる介護サービスは、食事、排泄、入浴介助などで、食費や居住費などは高額介護サービス費の支給対象外となります。
なお、自己負担限度額は所得により6区分にわけられています。
高額医療合算介護サービス費
高額医療合算介護サービス費とは「医療機関で支払った医療費の自己負担額」と「介護サービス利用で支払った自己負担額」どちらも高額になった場合に利用できる制度です。
合算した場合の限度額は年額(毎年8月1日~翌年7月31日)で決められています。
なお、これらの負担軽減制度を利用するためには申請が必要です。
医療費控除や高額医療合算介護サービス費に関しては、加入している健康保険の種類によって申請方法や窓口が異なります。
詳しくは、基準日に加入している健康保険の担当窓口に問い合わせてみましょう。
老健へのアクセス

老健を選ぶ際、施設のサービス内容や雰囲気と同様に重要となるのが、施設と自宅間の距離とアクセス方法です。
何かあった場合に「すぐに駆け付けられる距離にあるか」「面会は負担にならないか」という点についてしっかり検討する必要があります。
老健では、多くの施設で買い物や洗濯などの生活援助は施設でのサービスには含まれず、家族によるサポートが求められます。
そのような事情も踏まえて、日常的に通いやすい距離やアクセスの良い施設を選ぶことが大切です。
生活支援サービスについて

老健では、食事や入浴の世話やオムツ交換などの身体介護やリハビリといったサービスを受けることができます。
しかし、洗濯や買い物といった生活支援については充分なサービス提供がない施設も多くみられます。
例えば、洗濯物は家族が持ち帰り自宅で洗濯するなどです。
家族が忙しくてなかなか面会に来られない場合には、業者と契約を結んで代行してもらう必要があります。
老健での生活支援サービスの内容については、施設による違いもあるため、事前に確認しておきましょう。
見学時はここを見て

施設選びに失敗しないために見学は必須です。
ここでは、見学でチェックしておきたいポイントについてご紹介します。
入居者の表情や様子
施設環境やスタッフの対応は、入居者の表情や施設全体の雰囲気に反映されます。
はじめに見てほしいのは「入居者が生き生きとしているか」という点です。
入居者同士の会話や入居者とスタッフ間のコミュニケーションは盛んに行われていますか?
普段から話しやすい雰囲気づくりに取り組んでいて信頼関係が良好であれば、入居者からスタッフに話しかける場面が多くみられるはずです。
ちょっとした要望が伝えられる関係かどうかは、施設での生活への満足度を左右する重要なポイントとなります。
職員の対応
職員は笑顔で気持ちの良い挨拶をしていますか?
気配りができるスタッフは、周囲の状況をよく見てサービスを行っています。
入居者に対しての言葉遣いや誠実に対応しているかもチェックポイントになります。
職員同士がギスギスした関係では質の良いサービスの提供は難しいものです。
会話や表情をよく観察し、職員同士のチームワークなども確認しましょう。
施設の清潔感
施設を訪れてはじめに感じるのが臭気です。
施設内の臭気は衛生管理や安全管理とも関係しており、施設による差が出やすいポイントです。
施設内の清掃が行き届いていない場合には、人手不足の可能性もあり、サービスの質にも結びつく問題といえます。
施設の建物や設備自体が古くなっていても、日々の清掃が行き届いてる施設では清潔感があり、臭気対策もしっかり行われています。
つまり、施設の善し悪しは建物や設備の新しさだけでは判断できないということです。
設備の安全性
設備の安全性のチェックでは、生活する上で危険な箇所がないか確認します。
ドアの向きや開き方、机や洗面台の位置、高さや形状を確認し、無理なく安全に使用できるかといった視点でチェックしましょう。
新しい施設が安全性が高いとは一概に言えず、設立から時間が経過していたとしても、工夫次第で安全性の確保は可能です。
老健入居が向いている人、老健入居が向かない人
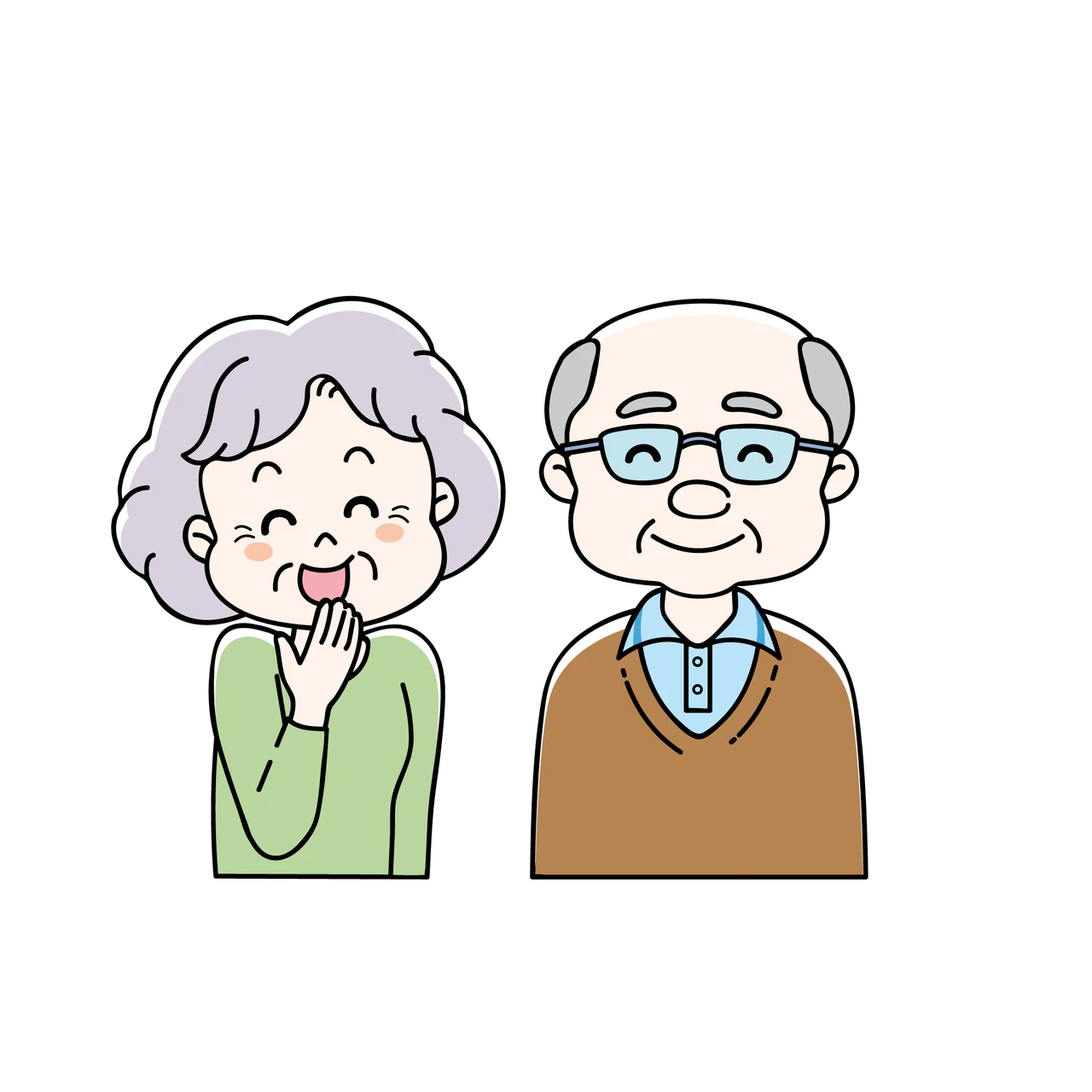
この章では、老人保健施設(老健)の特徴を踏まえ、老健への入所が向いている人と向かない人について詳しく説明します。
老健入居がおすすめの人
集中的にリハビリを受けたい人

老健は、基本的に3~6カ月という短期間で集中的にリハビリに取り組み、在宅生活に戻ることを目的とした施設です。
そのため、リハビリ専門職スタッフの配置や充実した器具や設備が整った環境で、専門的知識に基づいた機能訓練を受けることができます。
リハビリの内容は、立つ・座るなどの基本動作から、ベッドから車いすへ乗り移る訓練や歩行訓練、トイレでのズボンの上げ下ろしといった日常生活、コミュニケーションなどの社会適応能力に関わる内容が中心となります。
つまり、在宅復帰に意欲的で集中してリハビリを受けたい人のニーズに合った施設と言えるでしょう。
期間が決まっている人
老人保健施設(老健)は、入所までの待機期間が申し込みから3~6カ月程度で入所できるケースが多く、入所のハードルはそれほど高くありません。
また、入所期間は原則3~6カ月程度と制限されているため「再び自宅での生活を送るための準備が整うまでの間利用したい」といった方にも向いている施設です。
在宅復帰に意欲的な方にとっては、入居期間が限定されていることがリハビリへのモチベーションにも繋がるでしょう。
費用を抑えたい人
高額な入居一時金が必要となる民間の有料老人ホームなどと比較して、公的な施設である老健は入居一時金は不要で、月額費用のみで入居が可能です。
費用のうち、介護サービス費には介護保険が適用され、1~3割の自己負担で利用できます。
また、低所得者の方にも対応できるように所得に応じた減免措置も設けられているため、経済的に不安があり、入居にかかる費用を押えたいという方にも向いている施設です。
老健入居が負担に感じる人

リハビリを苦痛に思っている人
繰り返しお伝えしてきたように、老健は在宅復帰を目指してリハビリに力を入れている施設です。
楽しみや娯楽を目的としたレクリエーションや催し物はほとんど実施されない施設もあります。
そのため、リハビリに対して消極的な方には不向きな施設と言えるでしょう。
長期の入所を希望している人
老健は在宅復帰を目的としたリハビリ施設です。
最終的には、施設を退所して自宅での生活復帰を目指しており、入居期間は基本的に3~6カ月の期間限定といえます。
施設の方針によっても違いがありますが、原則3カ月ごとに評価を行い、在宅での生活に復帰できると判断されると退所を求められます。
そのため、特別養護老人ホームのように終の棲家としての利用はできません。
充実した医療を受けたい人
老健には、定員100人に対し1人以上の医師が常駐し、看護師も配置されます。
そのため、胃ろう管理や酸素投与など日常的な医療ケアや健康管理・緊急時の対応を受けられます。
しかし、あくまでも老健は高齢者施設であり、病院やクリニックといった医療機関とは異なります。
もし、専門的な治療や検査が必要となった場合、提携する医療機関で診察を受ける流れになるため、病院のような充実した医療を目的とした人にはおすすめの施設とはいえないでしょう。
老健の賢い選び方

老人保健施設(老健)の選び方で大切なのは、施設側の条件に自分が合わせるのではなく、どのような施設に入居したいかといった考えや条件、優先順位などを事前に整理し、情報を集めておくことです。
これらの準備によってポイントを押えた施設選びが可能となり、後悔のない施設の選択に繋がります。
どの老人ホーム・介護施設にしたら良いかお悩みの方へ
満足のいく老人ホームの生活は、どの施設に入居するかで大きく異なることがあります。
安心介護紹介センターの入居相談員は、高齢者の住まいにまつわる資格を有しており、多くの老人ホームの中から、ご本人やご家族のご希望に沿ったぴったりな施設を選定してご紹介させていただきます。
施設のご紹介から、見学、ご入居まで無料でサポートさせていただいておりますので、ぜひご利用ください。
![有料老人ホーム・高齢者住宅を選ぶなら[安心介護紹介センター]](/shokai/assets/images/logo-ansinkaigo.93b7d14a045ed3d060ab.svg)








