終末期ケア(ターミナルケア)とは?具体的なケアの内容や費用、看取り看護との違いについてご紹介します!
- 2024年10月07日 公開
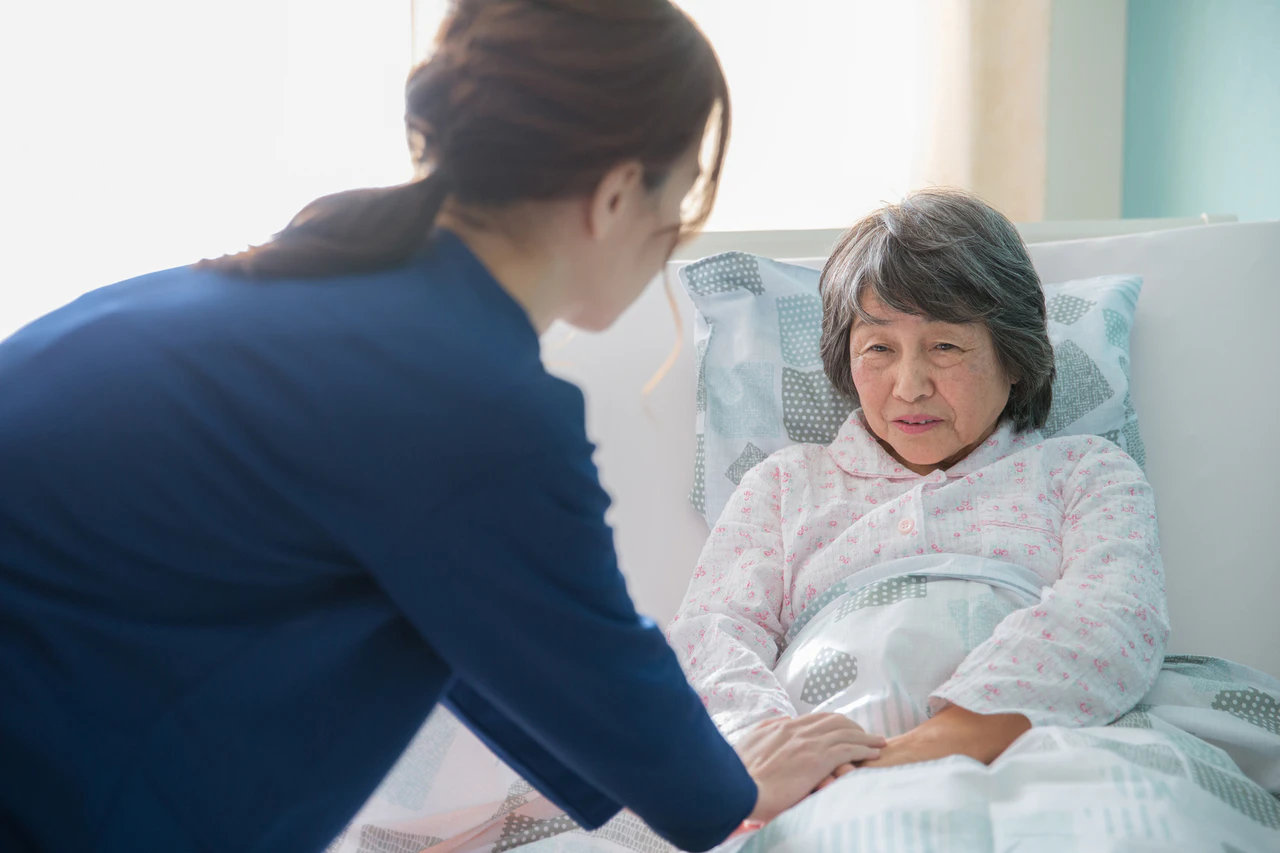
人生の最期の時である終末期に、無理な延命治療を行わず、できる限り苦痛を和らげて自然な形で過ごすことを希望する方は少なくありません。
この記事では、終末期ケア(ターミナルケア)の内容や費用、看取りケアとの違いをご紹介します。
この記事の監修者
目次
終末期ケア(ターミナルケア)とは?
終末期ケア(ターミナルケア)は、無理な延命治療を行わずに人間らしく最期を迎えることを支えるための医療やケアです。病気の種類にかかわらず、がんや神経難病、老衰などさまざまな状況で適用されます。
まずは、終末期ケア(ターミナルケア)の具体的な内容について説明します。
身体的なケア
身体的なケアでは、主に痛みの緩和を目的とした投薬が行われます。がん末期の方は痛みだけでなく「せん妄」という症状が出ることが珍しくありません。
せん妄では、突然大きな声を出したり、意味もなく手足を動かしたりするなどの様子が見られます。痛みやせん妄に対し、苦痛を緩和する目的で鎮痛剤をはじめとする薬物療法が行われます。
また、食事や入浴、排せつの介助などのケアを行い、清潔で安楽な状態で過ごせるようサポートすることも身体的ケアに含まれます。
精神的なケア
終末期は、身体の苦痛がある場合、死への不安や恐怖が強くなります。また、家族を残してしまうことへの心配な気持ちを感じている方は少なくありません。
そうした不安や恐怖を大きくしないためには、家族や友人と話す時間を作ったり、趣味を楽しめるように工夫したりする精神的なケアが有効です。
また、本人がリラックスできるようにベッド周りの環境を整えたり、香りや音楽によるリラクゼーションを取り入れたりすることもあります。
社会的なケア
社会的ケアでは、本人や家族のさまざまな不安に対応します。治療費への不安がある方へは、医療ソーシャルワーカーが医療費の軽減や支援制度について情報を提供します。
介護について困っていることがある方は、ケアマネジャーからサービスの調整や入居施設の紹介が受けられます。
遺品相続は、遺産相続人全員が行うことが原則ですが、終末期に遺品の整理や遺産相続について話し合うことが難しい場合もあるでしょう。
このような不安のある方は、あらかじめ成年後見制度を利用して後見人を立てておくことで、遺産相続や遺品整理について一任できます。
また、家族や身寄りのない方の遺産相続や遺品整理については、担当の医療ソーシャルワーカーやケアマネジャーが自治体と協力して手続きを行う場合が多いようです。
スピリチュアルペインに対するケア
終末期には、人生の意味や過去の出来事への後悔、生きる目的について考えることがあります。死が迫っている状況で、健康なときには意識していなかったことに苦悩してしまう方も少なくありません。
このようなスピリチュアルペインは、言葉に表現することが難しい痛みとされています。
「自分の人生に意味はあったのだろうか」「早く死んだほうが家族に迷惑をかけずに済むのではないか」など、スピリチュアルペインの内容は価値観や信念によってさまざまです。
終末期には、このような解決の難しい苦しみを聞き、本人の苦悩を理解するスピリチュアルペインに対するケアが重要です。
尊厳死のためのケアには他にどのようなものがあるのか?

人間らしい最期を迎える「尊厳死」を実現するためのケアには、終末期ケアの他にも「緩和ケア」「ホスピスケア」「看取りケア」などがあります。
それぞれについてご紹介します。
緩和ケア
緩和ケアは、痛みや苦痛を取り除くことをメインに行い、命の危機に直面する疾患にかかったときから始められます。
そのため、他のケアと違い、回復していくケースもあります。前述のように、がんの終末期を迎えている方は痛みを伴う場合が多く、なかには「不安が強く眠れない」方も少なくありません。
そのような患者には、適切な薬剤調整を行って痛みや苦痛を緩和する治療が有効です。なお、緩和ケアは全国のがん診療連携拠点病院で受けられます。
ホスピスケア
ホスピスは、余命わずかな患者が最期の時を過ごす入院施設です。
完治や延命を目的とした治療はなく、診断のための検査など苦痛を伴うことをほとんど行いません。不安によりそうケアとともに身体的、社会的ケアが行われます。
ホスピスケアは、緩和ケア病棟が設置されている病院などの施設型ホスピスや、シェアハウス型ホスピス住宅で受けられます。
看取りケア
看取りケアでは、終末期の患者の身体や精神の苦痛を緩和しつつ、人としての尊厳を残したまま最期を迎えるための生活支援を提供します。
自宅や介護施設などの生活の場で行われる看取りケアにおいては、医療や看護よりも介護や生活支援がメインとなります。近年では、看取りケアに対応している介護施設が増えています。
行政は終末期ケア(ターミナルケア)についてどのような取り組みをしているのか?

本人の意思が確認できなかったり、家族で情報の共有ができていなかったりすると、本人の気持ちが考慮されずに治療や無理な延命措置が行われてしまいかねません。
本人の意思に沿った医療が行われることを目指し、厚生労働省は「人生の最終段階における医療の決定プロセスのガイドライン」を作成しました。
このガイドラインは、終末期を迎える方の意思を尊重した医療やケアが行われるために、意向を確認する方法について明示されています。
さらに、厚生労働省は医療従事者・介護職員を対象に研修を行い、ガイドラインに沿って本人や家族の相談に対応できるような人材の育成を行っています。
「人生会議」というキーワードを耳にしたことのある方も少なくないでしょう。
人生会議とは、人生の終末期について、健康なうちから家族や身の回りの人と話し合い、最期をどのように迎えたいかを話し合うことです。
人生会議を行ったことのある方は40%程度という調査結果があり、国は本人の意向が反映される終末期ケア(ターミナルケア)が実現するような社会を目指して、ガイドラインの普及・啓発を行っています。
終末期ケア(ターミナルケア)を受けるタイミングは?

終末期ケア(ターミナルケア)は、病気の症状が悪化して余命が短い場合や治療によって回復する見込みがない場合に受けることになります。
期間は病気の種類や状態によって異なりますが、人生最後の数カ月ないしは数年です。
認知症や老衰のように緩やかに状況が変化する方は、寝たきりの状態が続いている場合や、介助をしても食事ができない状態になると、終末期ケア(ターミナルケア)を受けることが多い傾向にあります。
がんの方は、抗がん剤などの効果が確認できなくなり、これ以上の治療は望めないことを医師から告げられた段階が、終末期ケア(ターミナルケア)を受けるタイミングです。
終末期ケア(ターミナルケア)はどこで受けられるのか?

終末期ケア(ターミナルケア)が受けられる医療機関や施設は以下の通りです。
- ホスピスや緩和ケア病棟などの医療機関
- 介護老人保健施設
- 特別養護老人ホームなどの介護施設
- 自宅
それぞれの特徴やメリット・デメリットについてご紹介します。
医療機関での終末期ケア(ターミナルケア)
医療機関における終末期ケア(ターミナルケア)は、緊急な対応が必要となったときにも医師や看護師に迅速に対応してもらえるメリットがあります。
たとえば、急に痛みが強くなった方へは鎮痛剤をはじめとする薬剤の調整、不安が強くなった方へは安定剤の処方などです。
また、24時間体制でスタッフが常駐しているため、家族のケアの負担が少ない点もメリットのひとつです。
しかし一方で、入院期間が長引くと費用が割高になりやすく、経済的な負担が大きいことや、施設と比較して面会などに制限があるデメリットもあります。
とくに、新型コロナウィルスの状況によって、面会の人数や時間を制限している医療機関は珍しくありません。終末期に家族に会えないことで、不安を募らせてしまう方もいるでしょう。
介護老人保健施設での終末期ケア(ターミナルケア)
介護老人保健施設は、常勤の医師や看護師、栄養士が配置されている施設です。
緊急の場合にも医師や看護師の指示のもと、介護職員が対応できる連携体制がとられています。
夜間は医師が不在な施設が多い傾向にありますが、看護師が常駐もしくはオンコールで介護職員と連携し、24時間体制でサポートを受けられる安心感があるでしょう。
ただし、介護老人保健施設の利用期間は原則3カ月と定められているため、長期間の入居が見込まれる方の場合には利用が難しくなってしまうデメリットがあります。
特別養護老人ホームなどでの終末期ケア(ターミナルケア)
特別養護老人ホームなどの介護施設は、長期的に入居が可能な介護施設です。
介護老人保健施設ほど医療体制は充実しておらず、常勤の医師の配置はありません。
医療機関とは連携体制をとっていますが、緊急の場合には往診や受診を依頼する必要があるため、迅速に医療処置が行われる可能性は低いといえます。
特別養護老人ホームは、費用が割安なため人気が高く、入居するまでに長い待機期間があることで知られています。
一方、入居が叶えば長期的に過ごせるため、住み慣れた環境で慣れ親しんだ介護職員のケアを受けながら最期を迎えたいと考える方には適した施設であるといえるでしょう。
在宅での終末期ケア(ターミナルケア)
在宅においても、訪問診療や訪問看護、訪問介護を利用しながら終末期を過ごすことが可能です。医療機関と同様に、麻薬の点滴や酸素吸入などの医療処置を自宅でも受けられます。
在宅での終末期ケア(ターミナルケア)のメリットは、住み慣れた家で家族と過ごせるため、病院や施設よりも本人がリラックスできるところです。また、費用も割安です。
一方、家族に介護の負担がかかってしまう点はデメリットです。最期まで見守ることに不安や精神的な負担を感じる方も多いでしょう。
また、容体が急変しても、医師や看護師がすぐに駆けつけられない場合がある点も覚悟しなければなりません。
終末期ケア(ターミナルケア)や看取り看護にはどれくらいの費用がかかるのか?

終末期ケア(ターミナルケア)や看取り看護にかかる費用は、医療機関や施設の種類によって異なります。
それぞれどのくらいの費用がかかるのかを見ていきましょう。
医療機関での終末期ケア(ターミナルケア)にかかる費用
⽇本慢性期医療協会の調査によると、終末期の入院患者一人にかかる医療費は、日額2万8,500円です。
この医療費に加えて、差額ベッド代や食事代、おむつ代、パジャマ・タオルなどのレンタル費用などがかかります。
病院の看護体制や行われる治療によって費用は異なりますが、健康保険の負担割合が3割の場合、入院費用は30~50万円程度です。
介護老人保健施設での終末期ケア(ターミナルケア)にかかる費用
介護老人保健施設は、施設によって多床室や個室、ユニット型など居室のタイプが異なり、それによって利用料金も異なります。
利用者の介護度も料金に影響し、介護度の高い方は利用料金が高くなります。部屋のタイプと介護度によって利用料金は大きく変動しますが、おおむね月6~17万円が目安です。
さらに、介護老人保健施設で終末期ケア(ターミナルケア)を受ける場合には「ターミナルケア加算」の支払いが必要です。
これは、複数の医師を配置するなどの体制を整備し、早朝や夜間にも必要に応じて診療が行える体制をとっている施設に入居している場合に必要な費用です。
ターミナルケア加算は死亡日より30日前から算定され、最大で7万円程度かかります。
在宅での終末期ケア(ターミナルケア)にかかる費用
在宅で終末期ケア(ターミナルケア)を受ける場合、訪問診療や訪問看護、訪問介護の利用料金、薬代、福祉用具のレンタル代などがかかります。
電動ベッドなどの福祉用具は、介護保険制度を利用すると月数千円の料金でレンタルできます。
通常、訪問診療は月2回で8,000円程度、訪問看護は1回1時間を週1回で月額5,000円程度、訪問介護は1回50分を週2回で月額3,000円程度です。
しかし終末期には、状態によって医師や看護師、介護職員の訪問が増えるので利用料金が高くなることは珍しくありません。
訪問看護は1回1時間を週5回で月額1万8,000円、訪問介護は2時間程度の訪問を毎日2回で月額3万5,000円程度になります。
訪問診療の回数も月4回程に増えるため、在宅での終末期ケアにかかる費用をまとめると、ひと月あたり8万円ほどかかることが一般的ですが、それでも病院や施設よりも割安な傾向にあります。
なお、在宅で終末期ケア(ターミナルケア)を受ける場合にも、訪問診療と訪問看護の利用料金にターミナルケア加算が追加されます。
介護老人保健施設以外の介護施設では終末期にどのようなケアをするのか?

常勤の医師が在籍している介護老人保健施設以外で終末期を迎える場合、どのようなケアが受けられるのかについてご紹介します。
特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホームの多くには常勤の医師は在籍しておらず、医療機関と連携体制をとっています。
また、看護師の配置も24時間体制でない施設は珍しくなく、利用者のケアを行うのは主に介護職員です。
そのため、介護施設では終末期ケア(ターミナルケア)ではなく、シャワー浴や清拭、体位変換など、介護職員が行う身体的・精神的苦痛を緩和する看取りケアが中心です。
ただし、多くの特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設が看取りケアに対応してきているものの、まだすべての施設が対応しているわけではありません。
看取りに対応している施設かどうかについては、施設選びをする際に確認する必要があるでしょう。
終末期ケア(ターミナルケア)を受けるために準備すべきことは?

終末期ケア(ターミナルケア)を受けるためには、本人が延命を希望せず、終末期には痛みや苦痛を緩和するケアを望むかどうかを確認しておくことが重要です。
しかし、急に体調が急変したり認知症が進行したりすると、意思の確認が難しくなってしまいます。そのような場合には、本人の希望を確認できないまま、家族がケアの方針を決めることになります。
家族の意見が合わなかったり、責任を強く感じてなかなか決断できなかったりするなど、本人以外の家族が治療の方針を決めるのは難しいでしょう。
そのため、あらかじめ「終末期」に備えて、本人と話し合って意思を確認しておく必要があります。
終末期ケア(ターミナルケア)について本人と話し合うべきこと
終末期ケア(ターミナルケア)について本人の意思を確認する際には、「延命処置を希望するか」「どこで最期を過ごしたいか」「代理人は誰にお願いしたいか」について具体的に話し合う必要があります。
延命治療を受けるか
延命治療と聞くと、心臓マッサージや電気ショックを思い浮かべる方は少なくないでしょう。
実際には、このような救命措置以外にもさまざまな延命治療があります。
たとえば、食事が口からとれなくなってしまったときに行う点滴や経管栄養、痰が詰まりそうな場合の喀痰吸引、呼吸が苦しい場合の酸素吸入なども、延命治療に含まれます。
「酸素吸入はしたいが、点滴や経管栄養は希望しない」など、終末期ケア(ターミナルケア)を受けるときの治療方針については、具体的な医療処置を挙げて確認しておきましょう。
終末期ケア(ターミナルケア)を受ける場所はどこにするのか
近年、医療機関や施設、自宅など、さまざまな環境で終末期ケア(ターミナルケア)が提供されています。
前述のように、それぞれにメリット・デメリットがあるため、本人が安心できる環境はどこなのかについて話し合っておきましょう。
どのような場所で終末期ケア(ターミナルケア)を受けたいと思っているのかを把握しておき、必要に応じて、事前に終末期は施設で過ごしたい意向を担当のケアマネジャーに伝えておくことをおすすめします。
代理の意思決定者を誰にするか
代理の意思決定者とは、本人に代わって意思表示をする人を指します。
あくまでも「本人の推定意思」を表明することが原則であり、代理人が本人の意向を無視して治療方針を決めるものではありません。
終末期になり、自分で意思決定や意思表示をすることが困難になったときに自分の生に関わる判断を委ねられる人は誰かについて決めておくことは重要です。
終末期の苦痛を和らげるために適切なケアを受けるためには?

医療機関や介護老人保健施設、特別養護老人ホームでは、専門のスタッフが終末期ケア(ターミナルケア)を提供しています。
しかし「最期を住み慣れた自宅で過ごしたい」と、在宅での終末期ケアを希望する方が多いという調査結果があります。
在宅では家族がケアをする必要があり、終末期の体調が安定しない方を24時間サポートすることに身体的・精神的な負担を感じてしまう方もいるでしょう。
「在宅で介護をしようと考えていたが、思っていた以上にうまくケアできない」「介護以外の時間を作れずに疲れてしまった」と感じ、最終的には医療機関や施設を選択する方は珍しくありません。
自宅のような環境で最期の時を過ごしたいと考える方は、介護施設での看取りケアを検討してはいかがでしょうか。
看取り体制が充実している介護施設を見つける方法は?

施設によっては、看取りケア体制が整っていないところがあります。
充実した看取りケアを提供している施設を見つけるためには、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談することをおすすめします。
ただし、ケアマネジャーや地域包括支援センターが提供する介護施設の情報は地域が限定されてしまうため、紹介できる施設数が少ないことが一般的です。
また、立場上「施設の評判」について教えてもらえない可能性もあります。
看取り体制が充実している介護施設をお探しの方には、オンラインで介護施設の入居相談に対応している「安心介護紹介センター」がおすすめです。
安心介護紹介センターでは、介護の専門知識を備えたオペレーターが、看取り体制が充実している施設を提案します。
全国の施設データを持っているため、ケアマネジャーや地域包括支援センターより多くの施設の紹介が可能です。オンラインで土・日・祝日にも相談が可能なため、自分のスケジュールに合わせて気軽に相談できます。
どの老人ホーム・介護施設にしたら良いかお悩みの方へ
満足のいく老人ホームの生活は、どの施設に入居するかで大きく異なることがあります。
安心介護紹介センターの入居相談員は、高齢者の住まいにまつわる資格を有しており、多くの老人ホームの中から、ご本人やご家族のご希望に沿ったぴったりな施設を選定してご紹介させていただきます。
施設のご紹介から、見学、ご入居まで無料でサポートさせていただいておりますので、ぜひご利用ください。
![有料老人ホーム・高齢者住宅を選ぶなら[安心介護紹介センター]](/shokai/assets/images/logo-ansinkaigo.93b7d14a045ed3d060ab.svg)








