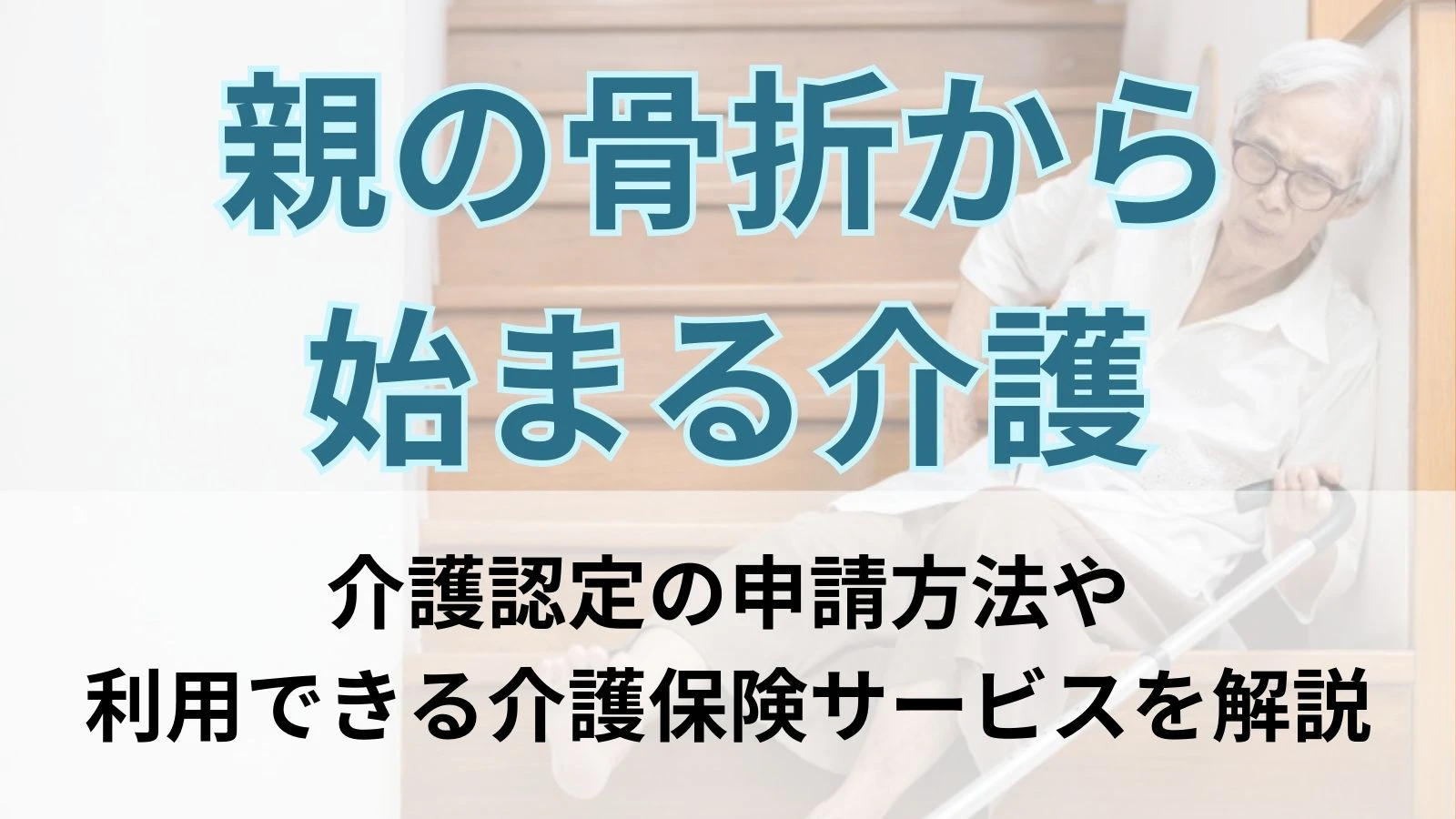親の介護にかかる費用|費用の目安と、介護費用捻出&費用軽減の方法を紹介
- 2024年05月27日 公開
- 2025年03月11日 更新

一般的に、親の介護にはどのくらいの費用がかかるのでしょうか。
「老後資金は2,000万円必要」と言われる中、介護費用に不安を抱える方も多いかもしれません。
この記事では、介護費用の目安や在宅介護・施設介護の費用、さらに費用を軽減するための方法について詳しく解説します。
この記事の監修者
目次
親の介護にかかる費用は?

介護にかかる費用は、在宅介護か施設介護か、または持病や認知症の有無など、さまざまな条件によって大きく異なります。
ここでは、公共財団法人生命保険文化センターの調査データを参考にしながら、介護費用の目安を詳しく解説します。
参照:公共財団法人生命保険文化センター「介護にはどれくらいの費用・期間がかかる?」
一時的な費用の平均は74万円
介護を始める際には、平均約74万円の一時的な費用がかかるとされています。
この一時費用の中には、介護ベッドなどの福祉用具の購入費用、住宅のバリアフリー改修費用、さらには施設入居時に支払う初期費用などが含まれます。
特に介護施設を利用する場合、一時的な費用は数十万円から数千万円に及ぶこともあり、事前に十分な準備が必要です。
在宅介護に関しても、必要な設備や居住環境を整えるための出費がかかります。
一方で、「掛かった費用はない」という回答も15.8%あることから、介護の方針やその状況によって費用は大きく異なることがわかります。
月々の費用平均は8.3万円
調査結果では、介護にかかる月々の費用は、平均で約8.3万円とされています。
この金額には、訪問介護やデイサービスなどの介護サービス利用料だけでなく、医療費やおむつ代、食費などの日常的な支出も含まれています。
8.3万円という金額はあくまで平均であり、さまざまな要因によって変わります。
特に大きいのが、家族がどれだけ介護を担えるかという点です。
家族を中心に介護を行う場合は、サービスの利用は最小限になり、費用も少なくなります。
介護費用が「1万円未満」という回答が4.3%あることからわかるように、家庭の経済状況に合った計画を立てることも可能です。
要介護度によって介護費用は変わる

介護費用は、要介護度によって大きく変化します。
調査結果では、要支援1の費用平均が4.1万円なのに対し、要介護5の費用平均は10.6万円となっており、介護度によって大きな差があることがわかります。
要介護度が低い場合は、介護サービスの利用頻度が少なく、費用が抑えられる傾向がありますが、要介護度が高くなるにつれて必要なサービスの種類や頻度が増加し、それに伴い費用も上昇します。
特に、デイサービスやショートステイの利用にかかる料金は、要介護度が上がることで段階的に単価も上昇します。
同じサービスを利用していても、介護度によって料金そのものが変わるため注意が必要です。
また、特別養護老人ホームなどの介護施設も同様に介護度によって費用が変動します。
要介護度によって費用が変わることも意識し、ケアプランを見直すことが必要です。
在宅介護・施設介護でも介護費用は大きく異なる
介護費用は、在宅介護と施設介護のどちらを選ぶかによって大きく異なります。
調査結果によると、在宅介護にかかる月々の平均費用は約4.8万円、一方で施設介護の場合は約12.2万円とされています。
このように、施設介護は在宅介護に比べておおむね2.5倍の費用がかかるとされています。
また、施設介護にかかる費用は、施設の種類によっても大きく異なります。
例えば、特別養護老人ホームなどの公的施設は比較的費用が抑えられる一方、介護付き有料老人ホームなどの民間施設では、入居時の費用や月額費用が高額になるケースがあります。
これらの施設介護の費用については、後の章で詳しく解説します。
在宅介護と施設介護では、費用はもちろん、家族を含めた生活全体に大きく影響します。
本人の意向に加え、経済状況や介護の負担などを踏まえ、慎重に検討することが重要です。
在宅介護の費用
在宅介護の場合、1か月あたりの平均費用は約4.1万円とされています。
この内訳は、ホームヘルパーや訪問看護、デイサービスといった介護サービス利用料、さらにおむつ代や医療費などの介護サービス以外の費用に分かれます。
在宅介護は施設介護と比較して、一見すると費用が安いように思われるかもしれません。
しかし、家賃や管理費、食費や光熱費などの費用は含まれていないため、在宅介護と施設介護の費用を単純に比較することはできません。
また、在宅介護では家族の肉体的・精神的負担も大きくなります。
介護を行うことで消費する時間や、仕事と両立している場合は介護のために取得する休暇による機会損失、腰痛などの身体的負担や夜間の介護による不眠など、さまざまな影響が生じます。
介護に伴う生活の変化により、目に見えない負担・コストが多く伴うのが在宅介護です。
介護施設での介護費用

介護施設は、施設によって入居時に支払う費用や月額費用が異なります。それぞれの施設の入居時の費用と月額費用の相場は以下のとおりです。
施設種類 |
入居時にかかる費用の相場 |
月額費用の相場 |
|
|---|---|---|---|
民間施設 |
介護付き有料老人ホーム |
0円~数千万円 |
12~35万円程度 |
住宅型有料老人ホーム |
0円~数千万円 |
12~35万円程度 |
|
サービス付き高齢者向け住宅 |
0円~数百万円 |
5~25万円程度 |
|
グループホーム |
0円~数百万円 |
15~20万円程度 |
|
公的施設 |
特別養護老人ホーム |
0円 |
10~14万円程度 |
介護老人保健施設 |
0円 |
8~14万円程度 |
|
ケアハウス |
0円~数百万円 |
4~15万円程度 |
特別養護老人ホームや介護老人保健施設は、公的支援を受けられるため入居時の費用がかからず、月額利用料も比較的低額です。
低所得者を対象とした減免制度も充実しているため、費用負担を抑えて利用することが可能です。
しかし、費用が安いため入居希望者が多く、入居までに長い待機期間が発生することが一般的です。
民間の介護施設は、施設ごとに料金やサービス内容が大きく異なります。
例えば、介護付き有料老人ホームは24時間体制で手厚い介護が受けられる一方、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では、自立生活が可能な方向けに設計されており、外部の介護サービスとの契約が必要な場合もあります。
認知症の方を対象としたグループホームや、比較的費用の安いケアハウスなど、さまざまな選択肢があるため、状況に合った適切な施設選びが重要です。
特に民間施設では、施設ごとに初期費用や月額費用が大きく異なるため、費用の差が大きいと言えます。
入居を検討する際は、複数の施設の料金や契約内容を比較し、適切な施設を選ぶことが重要です。
親の介護費用、誰が負担すべき?

介護には費用がかかることについて説明しましたが、この費用を誰がどのように負担するか。
家庭状況や経済状況によっても異なりますが、基本的な考え方について解説します。
介護費用は親が負担するのが望ましい
原則として、親の介護費用は親自身が負担するのが基本です。
親が現役時代に蓄えた貯蓄や年金を活用し、介護費用に充てます。
子どもには子どもの生活があり、教育費用や住宅ローンをはじめ、さまざまな費用が発生します。
そのため、子どもに十分な費用があったとしても、親の介護費用については、親自身の口座を使用し、親自身で負担することが望ましいとされています。
認知症などによりお金の管理が難しい場合には、家族が管理する方法や成年後見制度を活用することもできます。
親自身での負担が難しい場合
親の収入や資産で費用を賄うことが難しい場合、家族や親族で不足分を補うことが必要になります。
家族間で協力し、無理のない分担方法を話し合いましょう。
それぞれの経済状況もあるため、金額だけでなく、家庭での介護の役割分担も考慮しながら、不公平感を少なくすることが重要です。
また、地域包括支援センターや専門家に相談することで、家族だけでは解決しにくい課題の解決につながります。
特別養護老人ホームなどの施設では、低所得者向けに食費や居住費を軽減する減免制度が用意されています。
費用の負担軽減に使える制度は積極的に活用しましょう。
親の介護費用は長期的に発生することが多いため、経済状況から許容される範囲を超えて費用負担が大きい場合は、介護の継続が困難になります。
無理のない計画を立てて、家族全体で支え合う仕組みを整えることが大切です。
親の介護費用を確保するためにも、家族で話し合うことが大切

介護費用については家族間でしっかり話し合い、資産状況が把握できるようにする必要があります。
介護費用を確保し、適切に管理する方法について解説します。
介護に関する親の希望を確認する
「老後は施設に入居したいのか、それとも在宅で生活したいのか」、まずは親の意向を確認しましょう。どちらを希望するかで介護費用は大きく変わってきます。希望を100%実現することが難しくても、早い段階で本人の意向を確認しておくと、家族間の意見の食い違いやもめごとを防げるでしょう。
施設を希望している方の中でも、「手厚いケアが受けられる介護付き有料老人ホームがよい」「家庭的な雰囲気のあるグループホームやケアハウスが好ましい」「自由度の高いサービス付き高齢者向け住宅で気楽に生活したい」など、施設に求めることはさまざまです。
心配だからといってサービスが充実している施設を候補に挙げても、自由な生活を希望している方には窮屈に感じることもあります。金額だけではなく、希望する生活スタイルや人生の最期をどのように過ごしたいのかについても聞いてみると、施設の候補を絞りやすくなるでしょう。
施設に入居する場合に保証人が必要な場合や在宅介護を希望する場合には、家族の負担を考慮しながら役割分担も含めて話し合っておく必要があります。
親の経済状況・資産を把握する
介護費用は、介護を受ける当事者である親の資産から支払うことを前提に準備しましょう。
介護が必要になった場合、希望する生活は親の資産で実現可能なのか、もし足りない場合にはどのくらい不足しているのかを把握することが重要です。
預貯金のほかにも株や保険などの金融資産を確認し、さらに施設に入居する場合は持ち家の売却も念頭に置く必要があります。これらの資産と年金を合わせた金額が、介護にかけられる費用です。
また、両親の年金を確認する場合は、夫と妻のどちらかが亡くなると年金の受給金額が大きく変わる可能性があることも認識しておきましょう。
介護費用の負担を配分する
資産を確認して親の介護費用が足りないと分かった場合は、安価で利用できる公的な施設の利用や在宅介護は可能かなど、介護費用の負担を少なくする方法について検討してみましょう。
どうしても費用を減らせない場合は、介護費用の分担について家族で話し合うことをおすすめします。家族で話し合って課題を共有しておくと、さまざまな情報や知恵を持ち寄ることにつながるからです。
お金が原因で家族がもめてしまうと、いざというときに助け合うのも難しくなってしまうかもしれません。介護の準備をすすめる段階から、費用面での課題がないか家族で認識しておくと安心です。
資産管理者・管理方法を決める
親の介護費用を確保するためには、親の資産や収入を誰が管理するのかを明確にする必要があります。
親自身が資産を管理する場合でも、家族が定期的に状況を確認し、必要に応じて助言やサポートを行うことが大切です。
また、親が認知症などで金銭管理が難しくなる場合に備え、事前に資産管理を担当する家族を決めておくことが大切です。
管理を担当する人は毎月の支出を確認します。
介護に関する費用の支出は同じ口座に統一することにより、資金管理を明瞭化することができます。
家族で管理することができない場合は、成年後見制度や社会福祉協議会の日常生活自立支援事業を活用することで、親の意向を尊重しつつ適切な管理が可能になります。
親の介護費用が足りないときの対処法

親の介護は長期的に続くことが多く、急な状態悪化や入院などの突発的な出費もあり得ます。
介護費用が不足する事態に陥った時、適切な対処法を知っておくことで、経済的な負担を軽減できます。
介護費用が足りないときの対処法を3つ解説します。
専門家や相談窓口に相談する
介護費用についての問題は、専門家や相談窓口を活用するのが有効です。
まずは担当のケアマネジャーに介護費用について相談してみましょう。ケアマネジャーもさまざまなことを考慮して、介護サービスの回数などを決めていますが、話し合いで減らせる可能性もあります。家族だけでなく、民生委員や地域の人の力を借りることも検討してもらえると介護費用の負担も軽減できます。
地域包括支援センターは、介護に関する総合的な相談窓口で、介護保険サービスの費用を軽減するための利用方法や減免制度についてアドバイスを受けることができます。
介護の体制を総合的にフォローするケアマネジャーとは別に、地域包括支援センターの視点を生かすことでサポートの幅が広がります。
また、資金の運用の専門家であるファイナンシャルプランナーに相談することで、介護費用だけではなく家計全体の見直しについてアドバイスを受けることが可能です。
第三者の視点を取り入れることで、状況に合った適切な対処法を見つけることができます。
所有している資産を活用する
親や家族が所有している資産を活用することも、介護費用を確保する有効な手段です。
たとえば、親が所有している株式や骨董品、貴金属などの資産を売却することで現金化できる可能性があります。
もちろん、親自身の意向も大事ですが、家族で相談して何を優先すべきかを決めることも必要です。
不動産を所有している場合は、売却して現金化したり、リバースモーゲージを利用して融資を受けることが考えられます。
リバースモーゲージは、高齢者が自宅を担保にして融資を受け、毎月の生活費や介護費用に充てる仕組みです。
親が持ち家で生活している場合でも、家を売却せずに資金を確保できる点がメリットです。
ただし、制度の内容や条件は金融機関等によって異なるため、詳細は事前に確認することが重要です。
生活福祉資金貸付制度を利用する
生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯を対象とした貸付制度で、介護費用や生活費の負担を軽減するための支援策です。
この制度を活用することで、介護サービス利用に必要な費用などに対する資金が「福祉資金」として貸し付けられます。
利用条件や貸付金額は申請する内容や連帯保証人の有無などによって異なりますが、無利子または低い利子で利用できるため、経済的負担を抑え、生活を立て直せます。
制度を利用する際には、必要書類や手続きの流れを事前に確認し、家族内で十分に検討することが必要です。
親の介護費用の負担を減らすための制度は?

介護の費用負担を減らすために、さまざまな公的な制度が設けられています。それぞれの制度の対象者や利用するまでの流れについて詳しく解説します。
介護保険制度
介護保険制度は、介護を社会全体で支えるために2000年に創設された制度です。2020年時点で約674万人が要介護または要支援認定を受けて介護サービスを利用しています。利用料金は収入によって異なりますが、介護サービスを1割〜3割負担の費用で利用することが可能です。
介護保険制度を利用できるのは65歳以上の要介護認定または要支援認定を受けた方です。また、40〜64歳の方でも末期がんや難病など、厚生労働省が定める特定疾病が原因で介護が必要と認められた場合には要介護認定を受けた上で介護サービスを利用できます。
自宅で入浴や排せつの世話を受ける訪問介護や、医療的ケアを受ける訪問看護、電動ベッドや車いすなどの福祉用具のレンタルなど、介護保険制度によって利用できるサービスは多岐にわたります。
日帰りで施設を利用するデイサービスや通所リハビリテ―ション、施設に短期間入居するショートステイなども介護保険サービスの一部です。さらに、特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)、民間の介護付き有料老人ホームなどにおいても、日常生活上の支援や介護サービス費については介護保険制度が適用され自己負担金額が少なくなります。
それでは、介護保険制度を利用するためにはどのようにすればよいのでしょうか。
まずは「要介護認定」を受ける必要があるため、自治体の窓口もしくは地域包括支援センターで介護保険制度の申請を行いましょう。認定調査員が自宅を訪問する聞き取り調査や自治体が行う審査会を経て、要支援1~2、および要介護1~5の要介護度によって決定します。通常、認定結果が出るのは認定調査から30日程度かかるため、介護保険制度の利用を検討している方は早めの申し込みが必要です。
要介護もしくは要支援の認定を受けたら、サービスを調整するケアマネジャーと契約することによって介護サービスを利用できます。ケアマネジャーは自分で選んで契約できますが、とくに候補の方がいない場合には地域包括支援センターや居宅介護支援事業所で紹介してもらうことも可能です。
高額介護サービス費
介護サービスを利用する際には自己負担割合に応じた利用料を負担しなければなりません。高額介護サービス費は、1カ月の利用者負担の合計が負担限度額を超えた場合に超過分の費用の払い戻しが受けられる制度です。
高額介護サービス費の負担上限額
対象者(目安の年収) |
負担の上限額 |
|---|---|
課税所得690万円以上 |
140,100円(世帯) |
課税所得380万円~690万円 |
93,000円(世帯) |
市町村民税課税~課税所得380万円 |
44,400円(世帯) |
世帯の全員が市町村民税非課税 |
年金金額や所得により 15,000円(個人)24,600円(世帯) |
生活保護を受給している方など |
15,000円(世帯) |
参考:厚生労働省「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」
表にあるように、所得に応じて介護サービス費の負担上限額は異なります。この制度に該当する方には、介護サービスの利用から数カ月後に自治体から申請書が郵送されます。申請書に必要事項を記入して窓口に提出すれば払い戻しが受けられます。なお、一度手続きが完了するとその後は継続的に払い戻しが行われるため、再申請の必要はありません。
ただし、高額介護サービス費制度は介護サービスにのみ適用される点には注意が必要です。介護サービスとは、介護保険制度における介護や看護などのケアを指します。ショートステイ先の食費や理美容代、住宅リフォームなど介護サービスに該当しない金額は払い戻しの対象にはなりません。
高額介護合算療養費制度
高額介護合算療養費制度とは、世帯における年間の医療・介護負担金額の合算が、決められた限度額を500円以上超えた場合に超過分が返金される制度です。
高額介護合算療養費制度の基準額
年齢 |
所得 |
高額介護合算療養費上限額 |
|---|---|---|
70歳未満 |
一般的な所得の方 |
60万円 |
市町村住民税非課税の方 |
34万円 |
|
75歳以上 |
一般的な所得の方 |
56万円 |
市町村住民税非課税の方 |
31万円 |
※後期高齢者でも現役並みの所得がある方はこの限りではありません
自己負担限度額は年齢や世帯年収によって異なります。医療と介護サービスにかかった金額を合算し、上の表の自己負担上限額を上回っている場合は払い戻しが受けられます。
制度の申請先は、加入している医療保険の窓口です。国民健康保険や後期高齢者医療被保険に加入している方は市区町村窓口で申請が可能ですが、会社員など健康保険組合から保険証を発行されている方は勤務先を経由して申請する必要がある点に注意しましょう。
医療保険の「高額療養費制度」や、前述の「高額介護サービス費」は月々の自己負担額を軽減する制度ですが、高額介護合算療養費制度は年ごとの自己負担額を軽減する制度です。なお、この制度は高額療養費制度や高額介護サービス費による払い戻しを受けている方は限度額を上回ることがないため対象となりません。
特定入所者介護サービス費
特定入所者介護サービス費とは、対象となる介護施設に入居している所得や資産が少ない方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費を軽減する制度です。対象となる施設は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設、介護医療院などに限られ、グループホームや有料老人ホームは対象外です。
介護保険施設に入居する方は、介護サービス費用の1割〜3割負担に加えて食費や居住費、おむつ代、理美容代の負担があります。中には、制度を知らずに入居をあきらめてしまう方もいるでしょう。しかし、特定入所者介護サービス費の制度を利用することで食費や居住費の負担が軽くなるため、施設入居のハードルが下がることが期待できます。
特定入所者介護サービス費の制度は、市区町村へ申請して所得や資産の確認を受けなければ利用できません。制度の対象として認められるためには、本人を含む同一世帯の人が市町村民税非課税者であることや、貯金額が一定以下である必要があります。制度に該当するか心配な方は、自治体の窓口で相談してみましょう。
申請が通ると、月ごとの負担上限金額が記載されている「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。負担限度額は所得だけでなく、入居している施設の種類や部屋のタイプによって異なります。なお、認定期間は8月1日~翌年の7月31日の1年間のため、更新手続きを忘れずに行うようにしましょう。
社会福祉法人による利用者負担軽減制度
社会福祉法人による利用者負担軽減制度は、低所得者世帯が福祉サービスを利用しやすくするための支援策です。
この制度では、対象者の負担する介護サービス費用の一部が軽減されます。
対象者には、世帯全員が住民税非課税であることや、預貯金額が一定以下であることなどが求められます。
ただし、費用減額対象のサービスは、社会福祉法人が提供する介護サービスのみで、営利企業やNPO法人などが提供するサービスは該当しません。
この制度を利用するためには、各自治体の窓口で申請を行い、条件を満たしているか確認を受ける必要があります。
家族介護慰労金
家族介護慰労金は、在宅で高齢者を介護している家族の経済的負担を軽減するため、自治体が支給する金銭的支援制度です。
支給額や条件は自治体によって異なり、対象者の条件には、介護者が低所得世帯であることや、要介護高齢者が介護保険サービスを利用していないことなどが含まれる場合があります。
例えば、東京都新宿区では、要介護4または5に認定された高齢者を在宅で介護する家族に対し、年額10万円が支給されます。
その他の自治体でも、同様の支援制度を設けているところが多くあります。
家族介護慰労金を活用することで、在宅介護に伴う経済的負担を軽減することができます。
ただし、介護サービスを利用しないことで介護者が抱える介護負担は大きくなり、孤立するきっかけとなることから、制度自体を廃止する自治体も増えているのが現状です。
お住まいの自治体サイトなどで、制度の有無を確認することをおすすめします。
【覚えておきたい】親の介護に関する税金のポイント

親の介護にかかる負担を軽減するには、税金の知識を活用することが重要です。
介護費用に関連する主な税金制度について解説します。
介護費用も医療費控除の対象になる
介護費用の一部は、医療費控除の対象となります。
訪問看護やリハビリなどの医療系サービスだけでなく、訪問介護(生活援助中心型サービスはのぞく)や医療系サービスと同期間に利用したデイサービスなどの費用の自己負担分は医療費控除の対象となります。
また、介護保険施設の利用料金も医療費控除の対象です。
控除を受けるためには、1年間に支払った費用の明細書を添付して確定申告を行う必要があります。
条件を満たせば紙おむつ代なども医療費控除の対象になります。
医療費控除は税金を軽減する効果が大きいため、対象となる費用を確認し、明細書を保存しておきましょう。
親を扶養に入れると扶養控除が受けられる
親を扶養に入れることで、所得税および住民税で控除を受けられる可能性があります。
親の年間所得が48万円以下の場合は扶養控除を適用することで税負担を軽減できます。
一方で、親が別世帯であることや、世帯を分ける「世帯分離」をすることで、親が低所得者向けの減免制度や介護保険料の軽減を利用しやすくなります。
これらのメリット・デメリットもよく理解した上で、費用負担の軽減効果が大きい方法を選択しましょう。
どの老人ホーム・介護施設にしたら良いかお悩みの方へ
満足のいく老人ホームの生活は、どの施設に入居するかで大きく異なることがあります。
安心介護紹介センターの入居相談員は、高齢者の住まいにまつわる資格を有しており、多くの老人ホームの中から、ご本人やご家族のご希望に沿ったぴったりな施設を選定してご紹介させていただきます。
施設のご紹介から、見学、ご入居まで無料でサポートさせていただいておりますので、ぜひご利用ください。
![有料老人ホーム・高齢者住宅を選ぶなら[安心介護紹介センター]](/shokai/assets/images/logo-ansinkaigo.93b7d14a045ed3d060ab.svg)