遠距離介護の交通費はどれくらい?介護帰省の際に利用できる助成制度もご紹介します!
- 2024年10月07日 公開
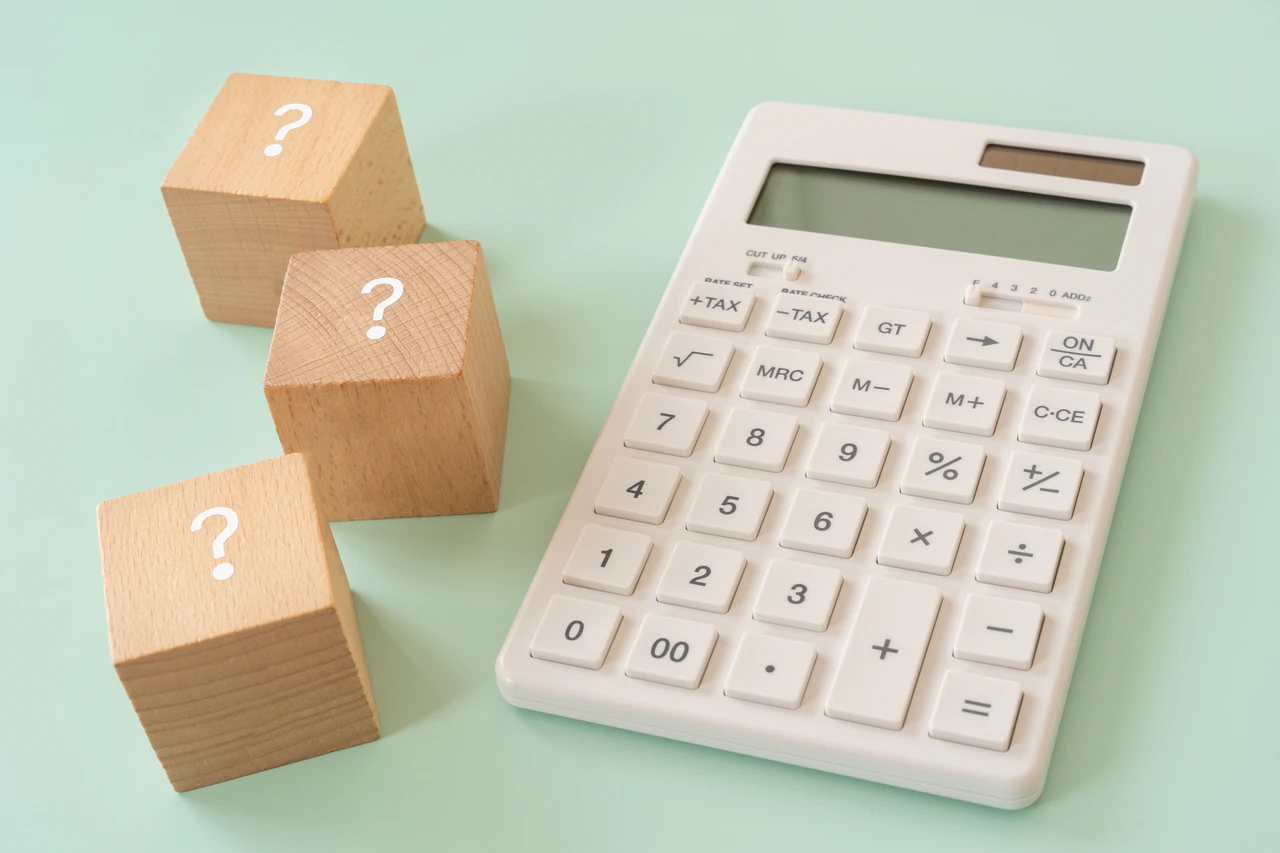
遠方に住む家族のもとに通って介護を行う場合、緊急時に即座に駆けつけられないだけではなく、交通費が大きな負担になり得ます。
この記事では、遠距離介護にかかる交通費や、交通費の負担を減らす方法などについて解説します。
この記事の監修者
遠距離介護の交通費はどれくらいなのか?
まず、遠方に住んでいる老親の家に定期的に通うとしたら1カ月にどれくらいの費用がかかるのかをシミュレーションしていきます。今回は、距離や頻度ごとに数例ご紹介します。
移動区間 |
交通費(片道) |
隔週(月2回) |
毎週(月4回) |
|---|---|---|---|
東京⇔前橋(群馬) |
電車 1,980円 |
7,920円 |
1万5,840円 |
東京⇔広島 |
新幹線 1万9,640円(指定席) |
7万8,560円 |
15万7,120円 |
東京⇔鹿児島 |
鉄道 3万1,460円 |
12万5,840円 |
25万1,680円 |
移動距離が長くなると、単純に区間が長くなるだけでなく移動手段も変わってきます。
今回は、新幹線での移動が必要となる東京・広島間や、飛行機での移動も考えられる東京・鹿児島間も例として挙げました。
上の表を見ると、同じ関東圏で、新幹線を使わないルートを選択すると、費用はそこまで高額にはならないものの、週に1度通う場合には1カ月で1万6,000円程度の負担。
もし新幹線を利用すれば、1カ月4万円程度かかってしまいます。
一方、東京・鹿児島間の運賃を見ると、飛行機を使わず鉄道・新幹線のみの場合であっても片道3万円以上。もし1カ月に何度も往復しなければならないとしたら、かなり大きな負担になるでしょう。
航空機を利用した場合、大手航空会社では片道のみで5万円近くかかります。LCCなどを利用すれば片道3万円程度の場合もあるため、この後で紹介する助成制度と合わせて利用の検討をおすすめします。
遠距離介護にかかる交通費を減らす方法とは?

遠距離介護は精神的・体力的な負担だけでなく、金銭的な負担も大きくなる傾向にあります。それでは、交通費の負担を少しでも減らす方法はあるのでしょうか。
ここでは、遠距離介護にかかる交通費を減らす方法について解説します。
航空会社の助成制度を活用する
前述のように、飛行機を利用すると大きな経済的負担となります。そのため、航空会社の中には家族の介護を目的とした移動に対して独自の助成制度を設けている場合があります。
制度の対象は航空会社ごとに差がありますが、被介護者が「要支援または要介護認定を受けていること」と「二親等以内の親族または三親等以内の姻族であること」を条件としている場合が多いようです。
例として、大手A社での通常運賃と介護割引の片道運賃を下記で比較しました。
移動区間 |
通常運賃 |
介護割引運賃 |
|---|---|---|
東京(羽田)⇔関西(大阪) |
2万4,600円(普通運賃) |
1万5,050円 |
東京(羽田)⇔九州(福岡) |
4万800円(普通運賃) |
2万1,300円 |
助成制度の利用には事前に必要書類の準備や申請が必要となるため、詳細な必要書類・申請方法・制度対象者等は各航空会社のホームページをご確認ください。
鉄道会社の割引制度を活用する
航空会社には遠距離介護者を対象とした割引制度がある一方で、2022年現在、大手鉄道会社では介護に限定した割引制度は設けられていません。
しかし、早期に切符を予約することで料金が安くなる「早割」や、年齢など一定の条件を満たしている方が会員登録をすることで通常料金よりも割安に鉄道を利用できるメンバーシップを設けている場合があります。
また、各地の私鉄などでは大手鉄道会社にはない割引制度や支援制度が整っていることもあります。
各社で利用できる割引制度や適用条件・適用区間・利用方法などはホームページをご確認ください。
高速バスを利用する
他県への移動には鉄道を使用する人が多いかもしれません。しかし、移動距離が長い場合は交通手段を高速バスに変更することで交通費を抑えられます。
たとえば、先ほど例に挙げた東京・広島間は新幹線(ひかり)を利用した場合、もっとも安い料金を選択したとしても1万9,440円ですが、高速バスなら1万3,000円。
移動時間が9時間ほど増えるものの、往復で1万円以上価格が変わるため大きな差といえるでしょう。
見守りサービスを充実させる
交通費を節約する方法としては、助成制度の活用や交通機関の変更だけでなく「頻度を減らす」という方法があります。
ですが、多くの人にとって援助が必要な老親の訪問回数を減らすのは、何かと心配なはずです。
そこで、「見守りサービス」の利用をおすすめします。身体介護を必要とする場合は難しいですが、安否や様子の確認のために訪問しているという場合はサービスの利用も検討してみましょう。
自分で設置可能な見守り用の機材には、カメラを利用して映像を確認する「カメラ型」、センサーで生活動作を感知して安否確認をする「センサー型」などがあります。
また、調理やゴミ出しなど日常生活に支援が必要な場合には、食事の宅配・ゴミ出しの代行などと同時に安否確認をする「訪問型」の見守りも検討してみましょう。
こうしたサービスは各自治体や民間事業者が提供しています。
同居して在宅介護をする
交通費がかさむだけでなく、被介護者の生活を一部しか見守ることができない遠距離介護。
介護する側とされる側がお互いの生活を大切にすることも重要ですが、負担が大きい場合は同居の検討も必要かもしれません。
同居することで、これまで見えにくかった問題点や必要となる援助を知るきっかけにもなるでしょう。また、コミュニケーションが増えることで双方の安心感も増すと考えられます。
ただし、親の家に介護者が住む場合、遠方への転居や介護を理由として現在の仕事を辞めざるを得ない可能性もあります。
こうした「介護離職」には経済的リスクが伴う点には注意が必要です。
介護離職の対策として、同居を考える場合には被介護者を自宅に呼ぶことをおすすめします。その場合、高齢者にとって環境の変化は大きなストレスであり、慣れるまでには時間がかかる点に配慮しましょう。
介護施設に入所する
遠距離介護を続けてきた家庭でも、被介護者の介護度が上がり、訪問回数が増えたことで交通費が負担になってくる場合があります。
もし週に1度以上の訪問が必要になったら、介護施設への入居検討も必要かもしれません。
移動距離や入居施設の種別によりますが、介護者が頻繁に往復している場合、交通費・在宅での介護サービス費・通信費などを合わせると、月々の費用は施設の入居費と同等、またはそれ以上にかさんでいる可能性があります。
介護施設への入居を検討するときの注意点は?

現状を変えずに交通費を抑えるには、交通機関の割引制度の利用が有効です。しかし、被介護者の状況や移動の距離・頻度に応じて、同居や施設入居を視野に入れる必要性もあるでしょう。
このような経緯で施設への入居を検討する際には、被介護者の安心の確保・介護者の経済的な負担軽減のために注意しておきたいポイントが2つあります。
1つ目は、介護者宅から施設への通いやすさです。
せっかく入居したにもかかわらず、施設の費用に加えて交通費がかさめば経済面での負担は軽減されません。可能な限り、自宅から通いやすい施設を検討していきましょう。
2つめは、定期的に面会を続けることです。
ケア自体は施設職員から提供されるため在宅介護に比べて家族がしなければならないことは減りますが、関係性の維持や精神的な安定のためにコミュニケーションは大切です。
遠距離介護をしていて仕事が忙しい方でも施設選びができる方法とは?

介護や高齢者に関する相談としては、地域包括支援センターが有名です。また、すでに介護認定を受けている場合には、居宅介護支援事業所に相談してもよいかもしれません。
こうした窓口と合わせて、現在介護をしている方が「自分で施設を探したい」「地域や入居条件から複数の施設を検索したい」「休日に相談できる窓口が知りたい」という場合におすすめなのが「安心介護紹介センター」です。
安心介護紹介センターでは全国の施設を扱っているため、県をまたいでの検索も可能です。また、土・日・祝日でも入居相談員が施設探しや介護の相談を受けつけています。
どの老人ホーム・介護施設にしたら良いかお悩みの方へ
満足のいく老人ホームの生活は、どの施設に入居するかで大きく異なることがあります。
安心介護紹介センターの入居相談員は、高齢者の住まいにまつわる資格を有しており、多くの老人ホームの中から、ご本人やご家族のご希望に沿ったぴったりな施設を選定してご紹介させていただきます。
施設のご紹介から、見学、ご入居まで無料でサポートさせていただいておりますので、ぜひご利用ください。
![有料老人ホーム・高齢者住宅を選ぶなら[安心介護紹介センター]](/shokai/assets/images/logo-ansinkaigo.93b7d14a045ed3d060ab.svg)








