高齢者の一人暮らし対策は?起こり得る問題やその対処法をご紹介します!
- 2024年10月07日 公開

近年、一人で暮らす高齢者の割合が増えているといわれています。しかし高齢者の一人暮らしにはさまざまなリスクがあるため、問題が起こる前に何らかの対策をする必要があります。この記事では、一人暮らしの高齢者が抱える問題やその対策方法などについて解説します。
この記事の監修者
一人暮らしの高齢者が増えている原因とは?
現在、65歳以上の5人に1人は一人暮らしだといわれています。同居家族がいないと体調や防犯面などで心細いと感じる人もいるかもしれませんが、 そもそもなぜ一人で生活する高齢者が増えているのでしょうか。
ここでは一人暮らしの高齢者の数が増えている原因について解説します。
少子高齢化が進んでいるため

2000年から2020年までの推移を見ると、既婚率・出生率ともに減少傾向にあります。 その影響から、一人暮らしや子どもを持たない夫婦の世帯、未婚の子と老親が同居する世帯が増えています。
未婚の人が一人暮らしのまま高齢者になったり、それまで同居していた両親や配偶者を亡くしたことをきっかけに一人暮らしとなり、 生活のサポートを任せられる相手がいなくなったりするケースも珍しくありません。
こうした場合に兄弟と同居を始める人もいますが、出生率の低下とともに兄弟姉妹の数も減っているのが現状です。 そのため、配偶者や親が亡くなった時点で身寄りがなくなってしまう人もいるでしょう。
核家族化が進んでいるため

日本では、世帯数は増えている一方で1世帯あたりの居住人数は減っています。 核家族化が進むなか、配偶者を亡くしたあとも子どもと離れて一人暮らしをしている人は多いのではないでしょうか。
また、一人暮らしになった親を心配して子どもが同居を提案しても「子には子の生活がある」という遠慮や、 「住み慣れた家がよい」などの理由から一人暮らしを続ける高齢者も少なくありません。
高齢者の一人暮らしで生じる問題とは?
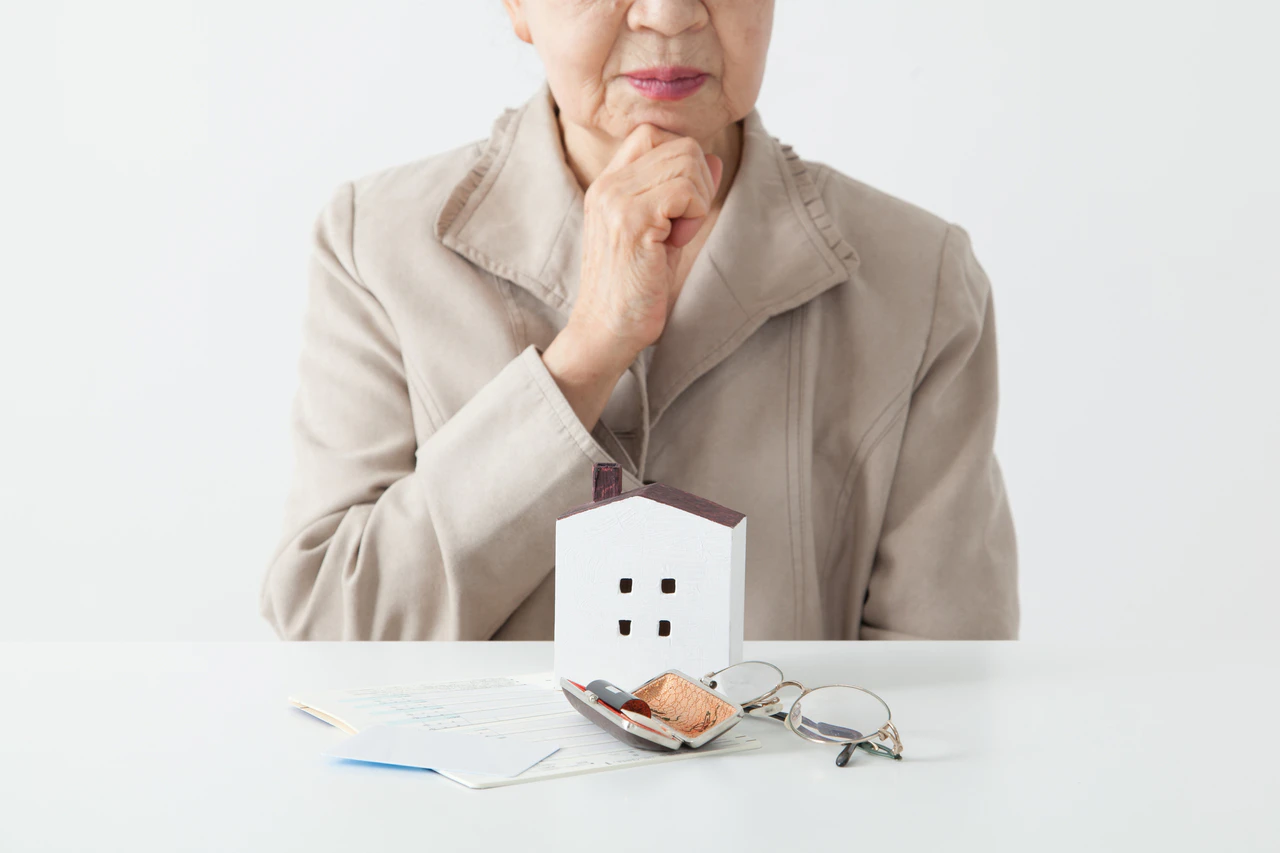
それでは、高齢者の一人暮らしではどのような問題が発生しやすいのでしょうか。体調面や金銭面などの観点から、いくつかのリスクをご紹介します。
自己管理が不十分になる
高齢者の一人暮らしでは、体調の自己管理が課題の1つとして挙げられます。 まず、食生活についてはスーパーやコンビニエンスストアのお弁当やお総菜のみで済ませてしまうことが増え、塩分過多・栄養バランスの偏りなどに陥りがちです。
その背景には、体力面などから調理が大変になった、配偶者に任せていたため家事があまりできない、自分一人分だけなら簡単に済ませたいなどの理由があるようです。
また、一人で生活することで外出頻度が下がったり、食事や就寝時間も日によってまちまちになってしまったりという人もいます。 こうした生活リズムの崩れやすさも、一人暮らしをするデメリットの1つです。
また、高齢になると温度やのどの渇きといった感覚が弱くなる傾向にあるといわれています。一人暮らしの場合は家族からの声掛けもないため、熱中症や脱水症のリスクが高まるでしょう。
緊急時の対応ができない
.jpg?fm=webp)
全国で1年間に救急搬送された人の内訳を見ると、約半数が高齢者です。 自宅から急病や事故で搬送される場合も多く、その際は家族が本人の異変に気がついて救急要請している割合が高いでしょう。
体調不良や事故で本人が外部との連絡を取れない状況に陥ってしまった場合、一人暮らしでは発見や通報が遅れる可能性が高く、最悪の場合は孤独死につながってしまうことも考えられます。
高齢者の不安を解消できない
体調面に加えて、高齢者自身の不安がなかなか解消されない点も一人暮らしのデメリットです。身体・認知機能が低下するなかでの一人暮らしには若いとき以上にさまざまな不安があるでしょう。
しかし、外出や生活のなかでの不安などを相談できる家族が身近にいないため、同居家族のいる高齢者に比べて家族の支援や外部のサービス利用にも結びつきにくいのが現状です。
また、こうした不安だけでなく人との交流の少なさ、地域とのつながりの希薄さなど、一人暮らしの高齢者は生きがいを感じにくい要因を抱えた状態に陥りやすいと考えられます。
認知症の進行に伴うトラブルを防げない
厚生労働省「国民生活基礎調査(2019)」において、介護認定を受けている人の「介護が必要になった原因」の1位は認知症です。
認知症では身体機能は年相応に保たれていることも多く、また本人が「分からない」ことを取り繕おうと努力している場合もあるため、 離れて住んでいる家族は症状の進行に気がつきにくいようです。
家族が「まだ一人で暮らせる状態」と考えていても、症状が想像以上に進行しており、 徘徊での行方不明や事故・ボヤ騒ぎ・詐欺などの被害に遭うリスクが生じやすくなっているかもしれません。
同居していればこうした事態が起きても早期に発見できる可能性がありますが、離れて暮らしていて訪問やコミュニケーションの頻度が低いほど認知症の悪化や被害に気づかず対応が遅れがちです。
高齢者の一人暮らしで起こる問題の対策方法とは?

ここからは、高齢者の一人暮らしにおける不安や問題を解決するために利用できるサービスや制度などをご紹介します。
成年後見制度を利用する
認知症により判断力が低下すると、適正な財産管理が困難になるだけでなく詐欺の被害に遭う可能性も高くなります。こうした場合に役立つ制度の1つに、成年後見制度があります。
成年後見制度は、疾患などにより判断力が不十分とされる人が不当な契約で不利益を被らないために、後見人が本人の財産管理や契約を支援し、また必要に応じて代理する制度です。
成年後見制度の申請条件は?
金銭的な管理は重要なため「認知症が進行してから知らない人に管理されるのは抵抗がある」「元気なうちに自分で手続きを済ませておきたい」と考える人も多いのではないでしょうか。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」という2種類の制度があります。 認知症が進行してすでに一人での判断が難しい場合も、まだまだ自分での判断が十分に可能という場合も手続きが可能です。
成年後見制度の申請方法は?
- 法定後見制度の場合
すでに認知機能や判断能力の低下が見られる場合は、法定後見制度の手続きを行います。 法定後見制度では、まず配偶者または4親等以内の親族が家庭裁判所に「後見開始申立」を行う必要があります。
申立後に必要書類を提出しますが、書類は種類が多く、入手までに時間がかかるものもあります。 手続きを考えている場合は、家庭裁判所のホームページなどで必要書類を確認し、申立前に揃えておきましょう。
その後、面談などを経て本人の判断力や後見人の適性などが確認され、本人の判断力の程度に合わせて補助人・保佐人・後見人のいずれかが任命され、制度の利用が開始されます。
- 任意後見制度の場合
現時点では自分での判断が行えるものの、判断能力が下がったときに備えてあらかじめ任意の相手を後見人とする契約を結んで、 必要になったら後見を開始したいときは「任意後見制度」の手続きを行います。
任意後見制度では、あらかじめ任意後見人になってほしい人と「任意後見契約」を結んでおく必要があります。 そして、実際に支援が必要な状態になったら家庭裁判所に「任意後見監督人選任申立」を行います。
任意後見制度の場合は、本人・配偶者・4親等以内の親族に加えて任意後見受任者も申立てを行えます。申立て後は、後見制度と同じく必要書類の提出等を経て制度の利用が開始されます。
後見人ができることは?
実際に後見制度を利用すると、どのようなサポートを受けられるのでしょうか。後見人にできること・できないことは以下の表の通りです。
後見人ができること |
後見人ができないこと |
|---|---|
|
預貯金の管理契約 介護サービス等の契約 不動産の管理や処分 訴訟行為 相続の手続き など |
身分行為(離婚・結婚・養子縁組等) 事実行為(介護・居宅の掃除等) 保証人になること 手術等に同意すること など |
まず、後見人にできることとしては本人に代わっての財産管理や契約があります。 たとえば必要な介護サービスの契約をするほか、悪徳商法などで本人が結んでしまった契約を取り消せます。
また、施設入居後に家族が介護費用の足しにするために本人の家を売却しようとしたものの、本人が権利者のため売却できないケースも多いようです。 こうした場合も、後見人であれば不動産の管理や処分を行えます。
一方、入院の際などに支払保証人になることや手術の同意を行うこと、婚姻や養子縁組など本人の身分に関わる行為は行えません。
同居する

家族が同居することで高齢者の一人暮らしで起こり得る問題を解決できるかもしれません。
ただし、高齢になった親との同居はバリアフリー化などにかかる費用面だけでなく、家族の精神的・体力的な負担がかなり大きくなると考えられます。 また、高齢者自身も新しい環境に慣れるまで時間を要することもあります。
地域の見守りサービスを利用する
一人暮らしの高齢者に対する見守りサービスを行っている自治体も増えています。 内容は配食・布団丸洗い・買い物代行・緊急通報装置の貸し出し・訪問などさまざまです。利用条件や内容は、自治体窓口に確認してみましょう。
介護サービス・施設を利用する
ここまで大きく分けて3つの対策を挙げてきましたが、成年後見制度や地域の見守りサービスは本人に実際に介護を提供できません。 また、同居の場合も介護が必要になれば家族への負担がさらに増えるでしょう。
上記の制度やサービスを必要に応じて利用しながら、本人への直接的な援助を行う手段としては介護サービスの利用や施設入居も検討していくことをおすすめします。
介護保険では介護度が低い場合も身体機能や認知機能に応じてサービスを選択できます。 また、介護保険のサービスを利用することで介護度が上がっても家族負担を抑えられるメリットもあります。
親に合った施設を探す方法とは?

最後に、実際に介護サービスを利用したいと考えたときにサービス調整や施設探しの相談ができる窓口についてご紹介します。
ケアマネジャーや地域包括支援センターを活用する
地域における高齢者関係の相談窓口としては地域包括支援センターが挙げられます。 要介護認定の申請方法や、生活のなかで困りごとを感じている場合の対処方法などの相談に乗ってもらえます。
また、すでに要介護認定を受けている場合は担当のケアマネジャーにサービス調整や施設入居の相談をしてみるとよいでしょう。 本人の状態を詳しく把握しているため、適切な助言が受けられるはずです。
このように地域のことを把握している窓口で相談すれば、高齢者本人の住所地付近でのサービスや施設に関する情報収集も、家族や本人だけで行うよりもスムーズに進むのではないでしょうか。
安心介護紹介センターを活用する
介護サービスの利用だけでなく施設入居を考えている場合は、施設探しのサポートとして「安心介護紹介センター」をご利用ください。 安心介護紹介センターは、無料で利用できる老人ホーム検索サイトです。
全国の老人ホームを掲載しているため「親が住んでいる地域ではなく自分の住んでいる県で施設を探したい」場合にも便利です。 また、休日でもオンライン相談が可能なため、仕事の時間を削らずに施設探しができます。
検索条件や掲載施設が多いので、希望条件や本人の状態に合った最適な施設選びができるはずです。
どの老人ホーム・介護施設にしたら良いかお悩みの方へ
満足のいく老人ホームの生活は、どの施設に入居するかで大きく異なることがあります。
安心介護紹介センターの入居相談員は、高齢者の住まいにまつわる資格を有しており、多くの老人ホームの中から、ご本人やご家族のご希望に沿ったぴったりな施設を選定してご紹介させていただきます。
施設のご紹介から、見学、ご入居まで無料でサポートさせていただいておりますので、ぜひご利用ください。
![有料老人ホーム・高齢者住宅を選ぶなら[安心介護紹介センター]](/shokai/assets/images/logo-ansinkaigo.93b7d14a045ed3d060ab.svg)








