延命措置にかかる費用は?延命措置のメリットとデメリット、延命措置を希望しない場合にすべきことなどもご紹介します!
- 2024年10月07日 公開

もしものときに延命措置の選択を迫られるケースがあります。その際にはいくらかかるのか、延命措置にはどのようなメリットやデメリットがあるのかを知りたい方もいるのではないでしょうか。
この記事では、延命措置のメリットとデメリットについて、費用や家族の負担といった側面からご紹介します。
この記事の監修者
目次
延命措置ではどのようなことをするのか?
延命措置とは、生命を維持するために行われる医療行為のことです。
まずは代表的な延命措置である「人工呼吸」「人工栄養」「人工透析」について解説します。
人工呼吸
人工呼吸とは、自分の意思で呼吸ができない方や、呼吸が弱く必要な酸素を体に取り込めない方に対して、呼吸を補助する治療です。
患者は、口や鼻からチューブを挿入したり気管に穴をあけて、器具を挿入する気管切開を行ったりして気道を確保したうえで、人工呼吸器につながれます。
ただし、患者の状態によっては必ずしもチューブや気管切開が必要というわけではありません。簡易的なマスク型の「非侵襲的陽圧換気」という人工呼吸器が選択されることもあります。
人工栄養
加齢や脳梗塞などが原因で、飲み込む力(えん下機能)が低下してしまった方が、無理に口から食事をとろうとすると、うまく飲み込めずに誤えん性肺炎を引き起こすリスクがあります。
人工栄養は、えん下機能が低下して食事が口から食べられなくなってしまった方に対して、点滴や栄養剤などを投与する処置です。
人工栄養には、「胃ろう」を造設して胃に直接流動食を注入する方法や、高カロリーの輸液や脱水症状を補正する点滴を投与する方法などがあります。
人工透析
人工透析は、血液中の老廃物の除去や水分量の維持、電解質バランスの調整を行う治療です。
人工透析は、通常慢性腎不全の方に行う治療ですが、しばしば延命措置として行われる場合があります。
延命措置にかかる費用は?

入院して延命治療を受ける場合、1カ月あたりどのくらいの費用がかかるのでしょうか。
入院費用の内訳例をご紹介します。
入院基本料金
どの医療機関に入院しても必ずかかる費用です。
病院の規模や病棟の種類、看護師の配置数などによって金額が異なります。
入院治療費
検査や手術・注射などの治療、リハビリテーションなどにかかる金額です。
日本慢性期医療協会の調査によると、終末期の入院患者一人あたりにかかる医療費は、日額2万8,500円です。
また、同調査によると、治療により改善して退院した方の医療費は、日額2万5,000円となっています。
終末期の方の医療費は、一般的な治療費よりも割高になることがわかります。
差額ベッド代
差額ベッド代とは、一般の病室よりも広さや設備の条件がよい4人部屋以下に入院した場合にかかる料金です。
病院によって金額は異なりますが、中央社会保険医療協議会の資料によると、差額ベッド代の平均額は1日あたり6,354円となっています。
延命措置を選択する方は、人工呼吸器などの医療機器を使用しているため、個室や2人部屋などに入院するケースが多く、差額ベッド代がかかることは珍しくありません。
その他
パジャマやタオルのレンタル費用、テレビ視聴料、おむつ代などもかかります。なお、保険の種類に限らず、食事代は1日あたり460円です。
紹介した金額は平均値であるため、必要な治療やケアによって医療費は大きく異なりますが、健康保険の負担割合が3割の方の入院費用は月額およそ30~50万円です。
延命措置にかかる費用を抑える方法は?

医療費の月額が一定の金額を超えた場合、超過分が払い戻される「高額療養費制度」が利用できます。
病院の窓口で治療費を一旦支払う必要がありますが、収入に応じて設定されている自己負担限度額を超えた料金が、後日払い戻される制度です。
高額療養費制度による、自己負担限度額について例をご紹介します。
一般的な所得の70歳の方
年金収入で生活している一般的な所得の方は、どれだけ延命措置の費用が高額になっても、1カ月の自己負担金額は5万7,600円です。
ただし、食事代や差額ベッド代は医療費に含まれないため、払い戻しの対象にならない点には注意が必要です。
年収約370万~770万円の75歳の方
一定以上の収入がある方は、自己負担限度額が引き上げられます。
たとえば、年収約370万~770万円の方は、「8万100円+(医療費-26万7,000円)×1%」が自己負担限度額です。
この方に1カ月70万円の医療費がかかった場合には、8万100円+(70万円-26万7,000円)×1% = 8万4,430円が自己負担金額となります。
延命措置を行うメリットとデメリットは?
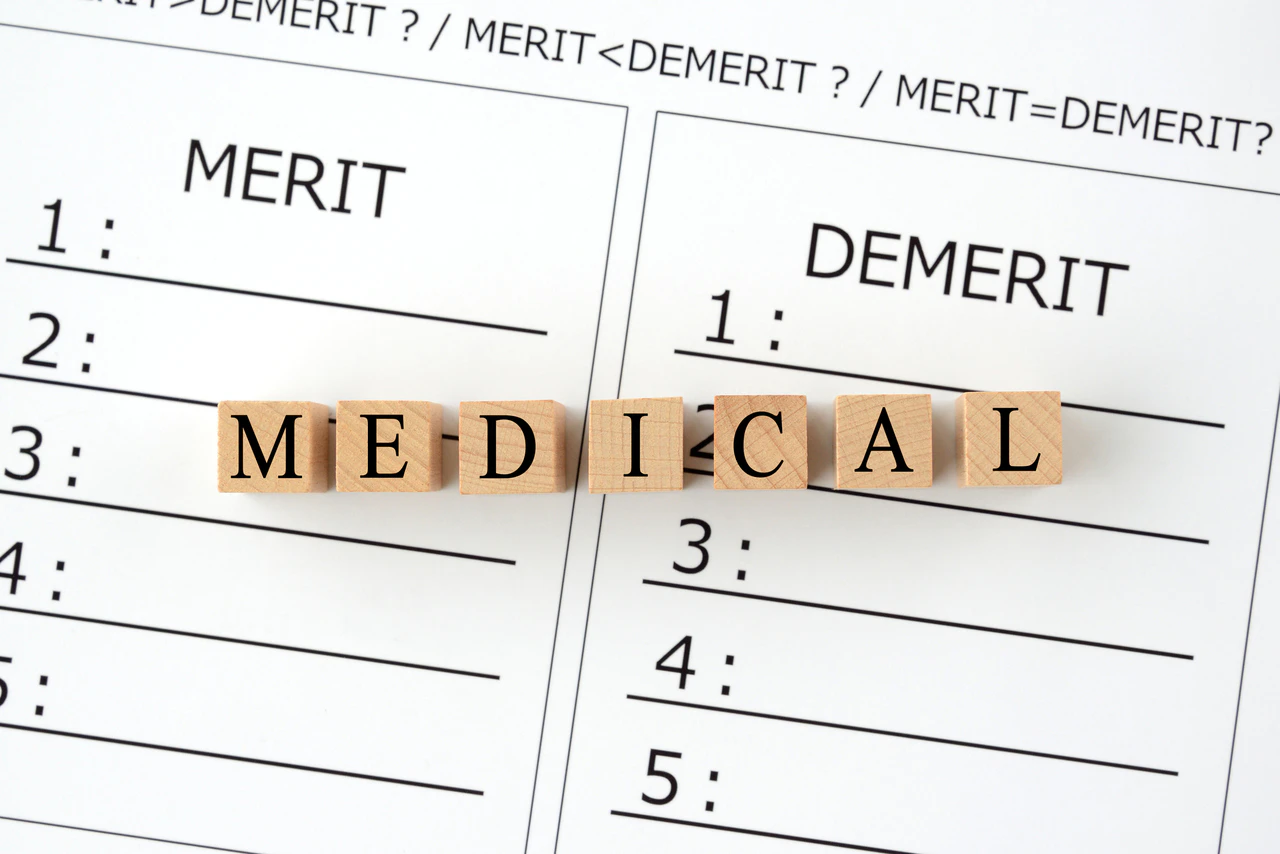
延命措置は、一般的な入院よりも医療費が割高になること、そして医療費は限度額を超えると払い戻しが受けられることについてご紹介しました。
ここからは、延命措置を行うメリットとデメリットについて考えてみましょう。
延命措置を行うメリット
延命措置を行うメリットは、家族の身体的な負担が少ない状態で、お別れまでの時間を確保できることです。
死期を延長できる
延命措置とは、食事がとれなくなった方や呼吸が自分の意思で呼吸ができない方に対し、経管栄養や人工呼吸器の装着によって生命を維持することです。
死期を延ばすことによって、家族が面会をしてお別れをする時間を確保できます。また、本人の所有している財産の整理や相続関係の手続きもできるでしょう。
家族に身体的な負担がかからない
延命措置を受ける方は専門的な治療が必要になるため、医療機関への入院が必要です。
日常生活のサポートが必要な在宅での介護と異なり、家族に身体的な負担はかかりにくいでしょう。
延命措置を行うデメリット
延命措置を行うデメリットは、高額な治療費や治療の長期化によって家族に精神的な負担がかかることです。
費用が高くなる
延命措置は、専門性の高い医療処置が行われるため、入院費用が高額になります。高額療養費制度を利用しても、長期間の入院は大きな負担となるでしょう。
また、前述のように食事代や差額ベッド代は高額療養費制度の対象にならないため、入院期間が延びるほど費用負担が大きくなります。
家族に精神的な負担がかかってしまう
人工呼吸器を使用する場合、麻酔が投与されることが一般的であるため、本人とのコミュニケーションが難しくなります。
意識がないまま機械につながれている状態を見守ることは、家族に精神的な負担がかかるでしょう。
家族の判断で延命治療を途中で止めた場合には、その決定を「これでよかったのだろうか」と悩んでしまう方は少なくありません。
いつ最期の時を迎えるのかを予測できないことも、大きなストレスになるでしょう。
延命措置を行うべきか?

医療技術が進歩している現代では、さまざまな延命治療が可能です。
しかし、過度な延命措置は、治る見込みがない方を「装置によって生かされている」状態にすることを意味します。
本人がそのような治療を希望するのか、事前に確認する必要があるでしょう。
近年は無理な延命措置を望まず、自然な形で死を迎える「尊厳死」を希望する高齢者が多くなっています。
尊厳死では、食事が食べられなくなっても点滴や経管栄養は行わず、呼吸が弱くなっても人工呼吸器を使用しません。
痛みや苦しみを緩和するための投薬やケアは行いますが、無理に命を永らえるような措置をせず、最期の時を迎えます。
延命措置を行うのか尊厳死を希望するのかについて、家族が決めるのは難しい現状があります。家族の意見が分かれたり、なかなか決断できなかったりすることが珍しくないためです。
親が元気なうちから話し合って、どのような最期を迎えたいのかを確認しておくようにしましょう。
尊厳死を希望する意思を確認しておくことで、もしもの場合に本人の意思に反した延命措置が行われることを回避できます。
延命措置を希望しないときにすべきことは?
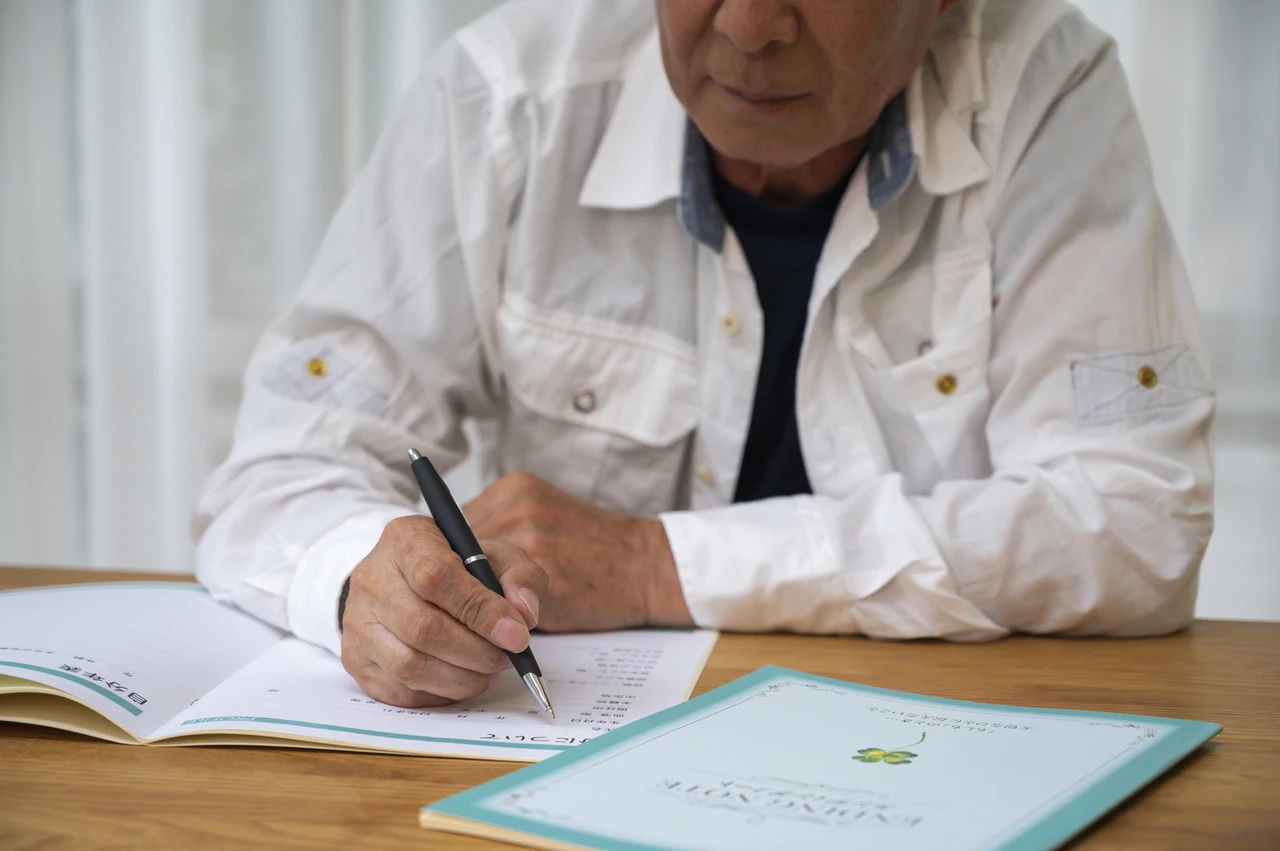
延命措置を希望しない方は、事前にどのような準備が必要なのかについて解説します。
延命措置を希望しないことを証明する書類を作成する
本人の意思を確認したら、以下に紹介する書面を活用しましょう。
また、本人の病状や介護の状況についてわからないことがあれば、医師や看護師、ケアマネジャーなどに相談することも重要です。
リビング・ウィル
リビング・ウィルとは、日本尊厳死協会が作成している「終末期医療における事前指示書」です。
協会に登録している会員は、この指示書を活用して生命維持に対する措置への要望を意思表明できます。
また、リビング・ウィルに付随する「私の希望表明書」では、最期に過ごしたい場所や大切にしたいことなどについて、細かく記しておけます。
尊厳死宣言公正証書
「尊厳死宣言公正証書」として、延命措置を拒絶していることや尊厳死を希望する理由、家族の同意、医療関係者に法的責任を問わないことなどを記載した書面を公正役場で作成できます。
作成に必要な費用や書類については、管轄する公証役場によって異なるため、確認しながら準備を進めましょう。
もしも手帳
もしも手帳は、終末期医療やケアについて、自分の考えを残しておくための手帳です。
元気なうちから、人生の最終段階である「もしも」の時に備えて、どのような最期を希望するのかを考えるときに使用します。
近年、もしも手帳を役所や地域包括支援センターの窓口で配布している自治体が増えています。
リビング・ウィルや尊厳死宣言公正証書のような正式な書式ではありませんが、家族や医療スタッフ、介護スタッフと話し合うツールとして活用してみましょう。
ターミナルケアや看取りの準備を進める
前述のように、延命措置よりも尊厳死を希望する方が増えている現在では、ターミナルケアに注目が集まっています。
ターミナルケアは人生の終末が見えた方に対し、延命を目的とせず、痛みや不安、ストレスなどの苦痛を和らげて安らかに最後を迎えることをサポートすることを重視する治療です。
ターミナルケアは、病院やホスピスで受けられるイメージがありますが、近年は特別養護老人ホームや介護老人保健施設などでも導入されています。
なお、とくに痛みや苦痛のない方には、必ずしもターミナルケアが必要というわけではありません。
住み慣れたサービス付き高齢者向け住宅や介護付き有料老人ホームなどの施設が看取りに対応している場合には、施設に入居したまま終末期を迎えることが可能です。
また、訪問診療や訪問看護、訪問介護などのサービスを利用すれば、自宅でのターミナルケアや看取りも実現します。
病院や施設でケアを行うよりも費用が割安な場合が多い傾向にあります。
しかし、在宅で生活を24時間サポートすることは家族に身体的・精神的な負担がかかるため、終末期は施設を選択する方が多いのが現状です。
ターミナルケアや看取りに対応した介護施設を探すときに活用したい相談窓口は?

ターミナルケアや看取りに対応した介護施設への入居を希望する場合には、まずは担当のケアマネジャーに相談しましょう。
ケアマネジャーが情報を持っていない場合には、地域包括支援センターにも相談できます。
ケアマネジャーや地域包括支援センターは、近隣の介護施設についての情報には詳しいですが、担当エリア内に希望条件に合った施設がない場合は、施設探しが難航しやすくなります。
希望する施設がなかなか見つからない場合には、民間の相談窓口も活用してみましょう。
安心介護紹介センターでは、介護の専門知識を備えたオペレーターが、希望の条件に合った施設を提案します。
全国の介護施設データを持っているため、ケアマネジャーや地域包括支援センターより多くの施設の紹介が可能です。
オンラインで土・日・祝日にも相談が可能なため、介護で忙しい方も自分のスケジュールに合わせて気軽に相談できます。
どの老人ホーム・介護施設にしたら良いかお悩みの方へ
満足のいく老人ホームの生活は、どの施設に入居するかで大きく異なることがあります。
安心介護紹介センターの入居相談員は、高齢者の住まいにまつわる資格を有しており、多くの老人ホームの中から、ご本人やご家族のご希望に沿ったぴったりな施設を選定してご紹介させていただきます。
施設のご紹介から、見学、ご入居まで無料でサポートさせていただいておりますので、ぜひご利用ください。
![有料老人ホーム・高齢者住宅を選ぶなら[安心介護紹介センター]](/shokai/assets/images/logo-ansinkaigo.93b7d14a045ed3d060ab.svg)








