介護離職の原因やデメリットとは?対策方法も併せてご紹介します!
- 2024年10月07日 公開

仕事を持つ人が家族の介護を担うことは、大きな負担になりがちです。仕事と介護を両立できず「介護離職」する人も増えていますが、仕事を辞めずに介護を続ける方法はないのでしょうか。この記事では、介護離職の現状や、離職対策に役立つ制度などを解説します。
この記事の監修者
介護離職とは?
仕事を抱えながら家族の介護を行っている人もいますが、要介護者の状況によっては両立が難しい場合もあります。また、仕事の内容上、業務時間を減らして勤め続けることを選べないケースもあるかもしれません。
その結果、家族の介護を理由として退職をせざるを得ない状況に陥ってしまうこともあるでしょう。これを「介護離職」といいます。
介護離職の問題点や対策について解説する前に、まずは日本における介護離職の現状について確認していきましょう。
厚生労働省「雇用動向調査(2020年)」によれば、令和2年に離職した人の総数は727万2,100人です。そのうち、70万5,000人が介護または看護を理由に離職したとされています。年代別では50代が最多となっている現状があります。
今後は介護を必要とする高齢者数はさらに増えるでしょう。そのため介護離職率も上がることが予測され、政府も介護と仕事の両立を課題として取り上げています。
介護離職になってしまう原因は?

それでは、なぜ介護離職が起きてしまうのでしょうか。ここでは介護離職の具体的な原因について解説します。
介護によるストレスや睡眠不足で仕事と介護の両立が困難になってしまう
介護を受ける側と介護者・家族の人間関係などにより、介護が大きなストレスになる場合があります。また、介護度・介助内容・要介護者の体格などによっては重労働になることもあるでしょう。
さらに、夜間の介護が必要になれば介護者の睡眠時間が削られます。とくに要介護者が認知症の場合、深夜の徘徊が不安で眠れない方もいるのではないでしょうか。
こうしたストレスや力仕事、慢性的な睡眠不足が長期間続くと、仕事と介護の両立が困難になりがちです。その結果、仕事を退職して介護に専念しようと決断する人も少なくありません。
介護休業制度を把握していなかった
介護休業制度とは、家族の介護を目的として長期休暇を取得できる制度です。休業中も賃金の一部が保証されるため、退職する場合と比べて経済的な影響も少ないでしょう。
しかし、介護理由の退職を雇用先に申し出た場合に、介護休業の取得をすすめてくれる会社ばかりではありません。そのため、介護休業制度を知らないまま退職を選んでしまう人もいます。
厚生労働省「平成29年度雇用均等基本調査」によれば、介護と仕事を両立するための制度を設けている企業のなかで、実際に制度が利用されていると答えた企業は3割程度にとどまっています。
介護離職のデメリットとは?

介護のために離職することは決して悪いことではありません。ただし、離職したあとでデメリットに気がつくと対応が困難な場合もあります。ここでは、介護離職にはどのようなリスクがともなうのかについて解説します。
経済的に不安定になる
もともと家族の扶養に入っている人が介護離職をした場合は家計への影響が少ないかもしれませんが、なかには高齢の親と2人暮らしの子どもが介護のために離職せざるを得ないケースもあります。
このような場合は、退職すれば収入がなくなるため経済的に不安定になります。生活費や介護費用の支払いのために貯蓄を切り崩さなければならず、介護者自身の老後の資金も減ってしまうでしょう。
また、介護者が退職したことで介護サービスに十分な費用が掛けられず、結果的に介護者自身の負担が増える可能性も考えられます。
再就職が難しい
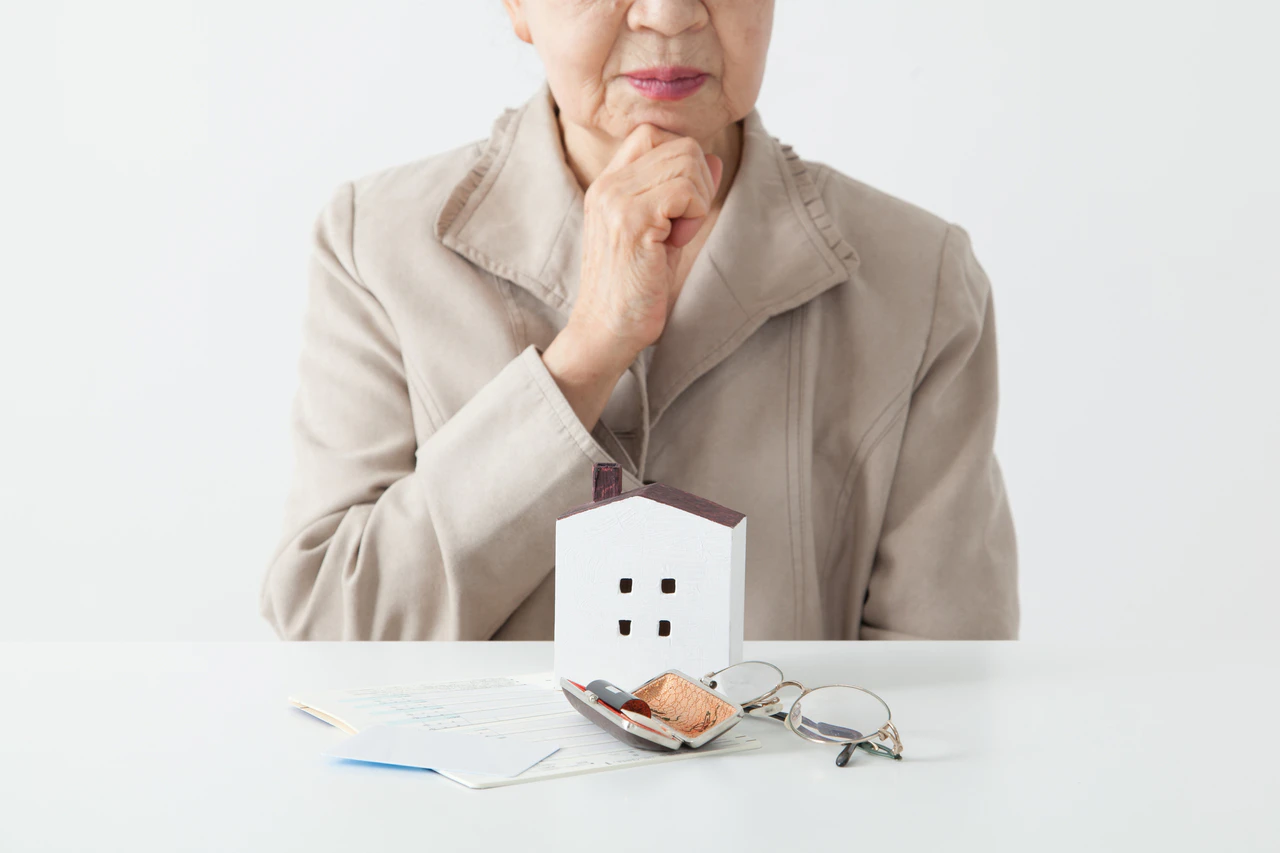
大手転職サイトによる調査では、正規雇用で中途採用された人を年齢階層別で比較すると、50代の採用者数は30代の約半分。一般的な傾向として、年齢が上がるほど再就職は難しくなるといえるでしょう。
しかし、総務省「平成29年就業構造基本調査」によると、介護を担いながら正規雇用で働いている人の年齢階層は全体の46%が50代。次いで40代が24%、60代が13%と、半数以上が50歳を超えています。
つまり、介護離職のリスクを抱える人の半数以上は正規雇用として再就職できる確率が低い年代ということです。また、家族の介護サービスなどを調整しながら自分の転職活動を進めるのも大変なことです。
必ずしも介護の負担が減るわけではない
仕事と介護を両立しているときには「退職して介護に専念すれば負担が減らせる」と考える人が多いのではないでしょうか。しかし、必ずしも退職が介護の負担軽減につながるとは限りません。
むしろ、介護離職をしたあとのほうが負担は増しているように感じるという意外な傾向にあります。離職することで体力・時間の余裕ができたはずですが、なぜ介護の負担が増したように感じるのでしょうか。
それは、介護以外の時間がストレス解消につながっていると考えられるためです。結果、退職して介護に専念することで身体面では楽になっても精神的な負担が増すということが起こり得るのです。
介護離職の問題の対策方法とは?

それでは、介護離職をしないためにはどのような対策を取ればよいのでしょうか。ここからは、仕事・介護の両立に利用できる制度や相談窓口について解説します。
介護離職を防止するための支援制度を利用する
まずは介護を担う就労者のための制度について、対象者や手続き方法をご紹介します。
所定時間外の労働を制限して介護の時間を確保できる
残業などの時間外労働により介護の時間が削られている場合、勤務先に申請を行うことで所定時間外の労働を制限できる制度があります。
1回の申請につき制限できる期間は1カ月以上1年以内。深夜業の場合は1カ月以上6カ月以内とされています。申請回数に法的な定めはないため、制限期間が終わる前に続けて申請を行うことで引き続き所定時間外労働を制限できます。
ただし、労使協定を結んでいる企業では入社1年未満または週の労働日数が2日以下の労働者は申請できません。
申請の際は、制限開始日の1カ月前までに書面等でで申請を行う必要があります。申請があった場合、所定時間外の労働の制限により事業に支障が出ると考えられる場合に限り、事業主は拒否することが認められています。
介護休業や介護休暇で介護に専念できる
法的に定められた「介護をするための休業制度」には、「介護休業」と「介護休暇」があります。休暇取得期間や目的には差があるため、それぞれの概要と違いを確認しておきましょう。
①介護休業
休業開始日の2週間前までに事業主に書面で申請することで、介護を必要とする家族1人に対し通算93日までで3回まで分割しての取得が可能となっています。
休業期間終了後の復職を見据え、介護サービスの選定や介護施設探しなども休業中に進めておくことをおすすめします。
ただしパートなど期間を定めて雇用されている場合、介護休業取得予定日から93日経過しても、介護休業開始日から数えて6カ月は雇用契約が続くことが明らかであれば申請できません。
また、労使協定を結んでいる企業では下記に当てはまる人も申請不可とされています。
- 入社1年未満の労働者
- 週の労働日数が2日以下の労働者
- 介護休業取得希望を申し出てから93日以内に雇用期間が終了する者
②介護休暇
当日の申請も可能ですが、休暇取得に際して雇用主などに希望を伝えることで、年間5日または10日までの介護休暇を取得できます。取得可能日数は、介護を必要とする家族が1人であれば5日、2人以上であれば10日です。
申請は書面に限らず口頭でもよいとされているため、申請方法については事業主などに確認しましょう。日または時間単位で取得できるため、通院の付き添い、ケアマネジャーとの打ち合わせなどの際にも使用しやすい制度です。
介護休業給付で経済的な不安を解消する
介護休業給付を取得した場合、介護休業を開始する前日までの2年間に12カ月以上被用者期間があれば、休業中も賃金の67%が介護休業給付として支給されます。支給を受けるためには、ハローワークへの申請が必要です。
本人が直接申請を行うこともできますが、基本的には事業主を通して申請します。事業主が提出する書類と被保険者自身が準備する書類があるため、申請の詳細は事業主やハローワークに確認してください。
介護休業給付を申請する場合、給付を受けられるのは介護休業が終了し支給が決定されたあとである点には注意が必要です。また、休業期間中に1カ月10日以上勤務をした場合は支給対象外です。
1人の要介護者についての給付回数は原則1回とされていますが、介護休業を3回に分けて取得する場合は休業給付の支給は最大3回です。
介護の相談窓口を利用する

ここまで仕事の負担を軽減する制度について解説しましたが、仕事と介護を両立させるためには介護者の負担軽減も必要です。そのためには、どのような窓口に相談すればよいのでしょうか。
要介護者がすでに介護度を持っている場合には担当のケアマネジャー、まだ介護度を持っていない場合などは地域包括支援センターが主な相談窓口です。介護を行う側の負担感や希望もあわせて相談してみましょう。
そのうえで要介護認定の申請、介護サービスや介護施設に関する情報収集・利用手続きなどを進めることで、仕事と介護を両立できる可能性が高まるはずです。
在宅介護をしながら短期間で施設を選ぶ方法は?

家族の介護施設への入居を考える際、介護や仕事に追われて時間も取れないなかで施設の情報を一つひとつピックアップしていくのは大変です。ここまで紹介した制度で時間を作り、公的な窓口も利用しながら情報を集めましょう。
もし希望に添った施設がなかなか見つからない場合は、ぜひ安心介護紹介センターをご利用ください。安心介護紹介センターは、全国の介護施設をご紹介する無料サービスです。
居住エリア・施設種別だけでなく、介護度・必要となる医療行為などの条件面での検索も可能です。
また、都道府県をまたいだ施設情報も豊富なので、公的機関の窓口と比べて選択肢も増えるはずです。電子メールでの相談にも対応しているため、自宅からの利用も可能です。
介護現場での経験や専門知識を持ったアドバイザーが対応してくれるので、安心して利用できる点も特徴の1つです。休日も相談を受けつけているため、仕事の都合でなかなか相談や施設探しができない方も曜日を気にせず利用できます。 介護に関する悩み事がある場合はぜひお気軽にご相談ください。
どの老人ホーム・介護施設にしたら良いかお悩みの方へ
満足のいく老人ホームの生活は、どの施設に入居するかで大きく異なることがあります。
安心介護紹介センターの入居相談員は、高齢者の住まいにまつわる資格を有しており、多くの老人ホームの中から、ご本人やご家族のご希望に沿ったぴったりな施設を選定してご紹介させていただきます。
施設のご紹介から、見学、ご入居まで無料でサポートさせていただいておりますので、ぜひご利用ください。
![有料老人ホーム・高齢者住宅を選ぶなら[安心介護紹介センター]](/shokai/assets/images/logo-ansinkaigo.93b7d14a045ed3d060ab.svg)








