認知症になった場合は口座が凍結される?凍結されたときの対処法や事前に親の資産を管理する方法をご紹介します!
- 2024年10月07日 公開
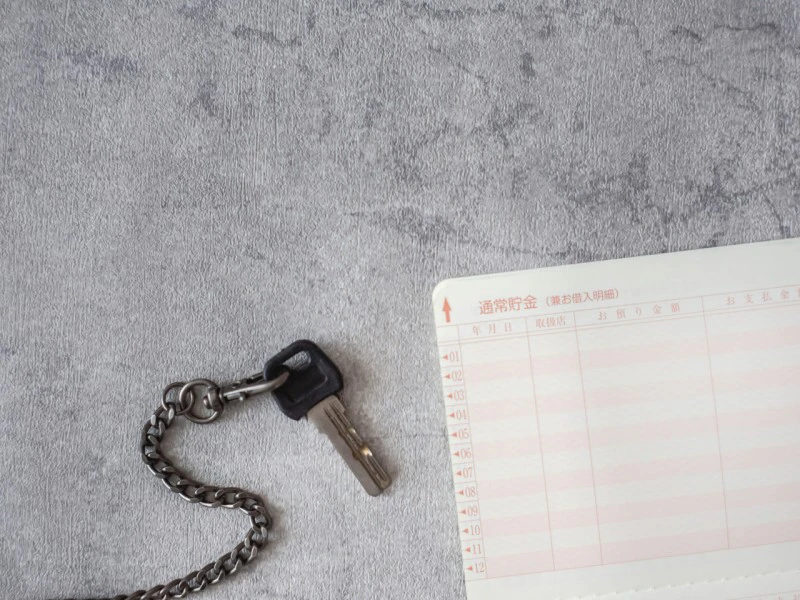
認知症になると、その方の預貯金口座が凍結されます。親の口座から介護費用や生活費を出していた場合、凍結されると支払いができずに困るケースも多いでしょう。この記事では、口座が凍結されたときの対処法や事前に親の資産を管理する方法をご紹介します。
この記事の監修者
目次
認知症になったとき、なぜ口座が凍結されるのか?
認知症になり判断能力が著しく低下すると、その方の銀行口座が凍結されます。その理由は、認知症の高齢者が詐欺や悪質商法などによってお金をだまし取られたり、家族に横領されたりすることを防ぐためです。
認知症の高齢者の資産を守ることが凍結の目的ですが、介護や資産管理をする家族にとって不安や困り事が生じるケースも少なくありません。口座凍結によって入金・預金の引き出し・定期預金の解約や契約内容の変更・公共料金の引き落としなどができなくなるからです。
ここでは、認知症になった際にどの口座が凍結されるのか、いつ実施されるのかについて解説します。
認知症になったときにどの口座が凍結されるのか?
認知症になった方の口座凍結は、大手銀行や地方銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、JA、労働金庫などすべての金融機関で実施されます。
また、普通預金口座や定期預金口座など、認知症になった方の名義であればすべての口座が凍結されるリスクがある点に注意が必要です。
認知症による口座凍結はいつ行われるのか?
認知症による口座凍結は、認知症であると銀行が知ったときや認知症が疑わしい場合に行われる可能性があります。
たとえば、本人が銀行で手続きできなかったり、自分の氏名や生年月日がわからないといった場合に認知症の可能性を疑い、口座を凍結することがあります。
認知症によって口座が凍結されたときの対処法は?

認知症になると口座が凍結され、さまざまな取引ができなくなってしまいます。認知症になった方が保有するすべての金融機関の口座が対象となるため、介護費用や生活費の支払いに悩む方も少なくありません。
口座が凍結されたときに慌てないようにするためには、事前に対処法を把握しておくことが重要です。ここでは、認知症の方の口座が凍結された際の対処法についてご紹介します。
法定後見制度を活用する
認知症によって口座を凍結されたときは、成年後見制度を活用する方法があります。成年後見制度は高齢者の財産を保護するためのもので、認知症になっていない場合に利用できる「任意後見制度」と、認知症になった場合に利用できる「法定後見制度」があります。
たとえ認知症になってしまったとしても、法定後見制度を活用すれば口座の利用制限が解除され、口座名義人である親の代理人として成年後見人が預金の引き出しなどを行えるようになります。
ただし、認知症の方の財産を保護する目的のもと、成年後見人は家庭裁判所が選任するため、必ずしも家族が選ばれるわけではありません。場合によっては弁護士や司法書士、社会福祉士といった法律・福祉の専門家が選ばれることもあり、家族が認知症の親の資産を管理できるとは限らない点には注意が必要です。
また、認知症が進行してからでも成年後見人を立てられますが、利用開始までに数カ月かかることがあります。口座が凍結されたときの対処法として有効ですが、制度についてよく知ってから利用することをおすすめします。
金融機関に問い合わせる
口座を凍結された金融機関に問い合わせることで対処できる場合もあります。認知判断能力が低下している方の財産を守るための口座凍結ですが、それによって医療費や介護費用の支払いが困難になるケースも珍しくありません。家族が本人の利益のために口座のお金を使うケースも多いからです。
そのような背景もあり、2021年2月18日、全国銀行協会は本人やその親族が成年後見制度を利用しておらず、医療費など本人の利益に適合することが明らかな目的でお金を使う場合、家族が本人に代わって預金の引き出しができるようにする新方針を打ち出しました。
しかし、この方針は金融機関に課せられた義務ではなく、あくまでも全国銀行協会に加盟する金融機関が対応をするときに参考にするものです。
そのため、金融機関によっては問い合わせをしても新方針に則った対応をしてくれない可能性もあります。対応の可否も含めて、口座が凍結されて困った際には金融機関に問い合わせることをおすすめします。
口座が凍結される前に家族が親のお金を管理できるようにする方法は?

口座が凍結されたあとでも、成年後見制度の活用や金融機関への問い合わせで対処できることはあります。しかし、手続きが必要になったり対応してもらえないケースがあったりするため、できれば事前に対処したいと思う人は多いでしょう。
ここでは、口座が凍結される前に親のお金を家族が管理する方法を3つご紹介します。認知症になる前の対処であるため、本人の意思を尊重した形を取れるメリットもあります。
任意後見制度を活用する
親がまだ認知症となっていない場合、成年後見制度のひとつである「任意後見制度」を活用することで、親が認知症となってからでも、そのお金を家族が管理できるようになる可能性があります。
任意後見制度は、判断能力のあるうちに本人が後見人を選べる制度です。法定後見制度と異なり、専門家以外に親族を後見人として選べます。
契約内容も本人が決められるのが特徴で、その中に財産の管理も含まれます。任意後見制度で後見人に財産管理を委託しておけば、認知症になっても口座からお金を引き出すなどの管理が可能です。
任意後見制度ではあらかじめ後見人を選べますが、契約が開始するのは判断能力が低下して家庭裁判所に申し立てをしてからです。選定してから契約開始までにタイムラグが生じる可能性があることに注意しましょう。
また、財産管理を委託された場合に本人の財産を管理することはできますが、本人に損害を与えかねないリスクのある資産運用はできません。
家族信託を利用する
財産管理を家族間で行うための制度である家族信託の利用も、口座が凍結される前にできる対処方法のひとつです。
家族信託では「受託者」である子が「委託者」かつ「受益者」である親の財産を管理運用する権利を得られます。契約後に親が認知症になっても、ある程度自由に資産を管理できるのがメリットです。
口座の管理だけでなく、親が不動産を所有している場合は不動産管理や処分もできるのが特徴です。
家族信託では親が認知症になる前から効力があるため、判断能力のあるうちに資産管理を任せられます。そのため、資産運用や不動産の処分などについてあらかじめ相談することが可能です。
メリットも多い一方で、家族信託では「受託者」に権限が集中してしまうことに注意しなければなりません。「受託者」は親の資産に関して大きな権限を持つことになり、その権限を巡って家族間の争いに発展することがあるからです。
家族信託を利用する際には、家族間でよく話し合うことが重要です。また、「委託者」である親と「受託者」になる子が、十分な信頼関係を保つことも必要不可欠です。
生前贈与を行う
親が認知症になる前に生前贈与を行うことで、口座が凍結される前にお金の管理ができるようになります。生前贈与には暦年課税による贈与と、相続時精算課税による贈与の2種類があります。
暦年課税による贈与は、贈与を受ける人ごとに年間110万円以内であれば非課税です。相続時精算課税による贈与では、2,500万円以内であれば税は課せられません。ただし、相続時に相続税が課せられることがあります。
また、相続時精算課税の適用を受けるには、「贈与をした年の1月1日において60歳以上である父母または祖父母」が贈与者、「贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の推定相続人および孫」が受贈者でなければなりません。
認知症になると口座が凍結されてお金の引き出しができなくなるため、生前贈与は認知機能や判断能力が低下していないうちに行う必要があります。
認知症を考慮して財産管理の手続きを行いたいときは?
.jpg?fm=webp)
親が高齢になってくると、いつか認知症になるかもしれない、介護が必要になるかもしれないという不安が出てきます。そして、認知症になると口座が凍結されて財産管理ができなくなるのも不安要素のひとつです。
認知症になる前に親の財産を管理できるようにしたい場合は、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
今回ご紹介したように、口座凍結の対策には「成年後見制度」「家族信託」「生前贈与」といった方法があります。それぞれにメリット・デメリットがありますが、内容を理解したうえで利用することが重要です。
お金に関わることのため、親から資産を受け取るときには相続税や贈与税がかかるケースもあります。契約内容がわからない、税金のことを知りたいなど不安を解消するためにはそれぞれの専門家に相談するのが一番です。
どの老人ホーム・介護施設にしたら良いかお悩みの方へ
満足のいく老人ホームの生活は、どの施設に入居するかで大きく異なることがあります。
安心介護紹介センターの入居相談員は、高齢者の住まいにまつわる資格を有しており、多くの老人ホームの中から、ご本人やご家族のご希望に沿ったぴったりな施設を選定してご紹介させていただきます。
施設のご紹介から、見学、ご入居まで無料でサポートさせていただいておりますので、ぜひご利用ください。
![有料老人ホーム・高齢者住宅を選ぶなら[安心介護紹介センター]](/shokai/assets/images/logo-ansinkaigo.93b7d14a045ed3d060ab.svg)








