「皆さん、認めたがりませんが既に日本は『貧しい国』」社会学者・山田昌弘さんに聴く『少子化対策』失敗の理由とは?
- 2024年08月30日 公開
- 2024年11月28日 更新

バブル崩壊で女性の望む高収入の未婚男性は減少。結婚する男女も減る。少子化は簡単なロジックです。
「パラサイト・シングル」や「婚活」という言葉の生みの親で、「格差社会」の到来にいち早く警鐘をならし、『希望格差社会: 「負け組」の絶望感が日本を引き裂く』『「婚活」時代 』『少子社会日本: もうひとつの格差のゆくえ』の著者として知られる家族社会学者で中央大学教授の山田昌弘さん。
2023年に生まれた日本人は過去最少、「合計特殊出生率」も1.20と過去最低。2035年には出生数は50万人を割るとの予測も。このまま急激な人口減少が続けば、日本経済は大きく縮小し、あらゆる社会システムが維持できなくなるとの声もあります。
『日本の少子化対策はなぜ失敗したのか?』の著者でもある山田教授に、なぜ日本の「少子化」がここまで悪化したのか、その原因について詳しくお話しを伺いました。
中央大学教授
山田 昌弘
やまだ まさひろ
目次

データでは見えてこない日本人の不安の正体
──まず、山田先生が研究されている家族社会学についてお聞かせください。
1989年の出生率が公表されて「1.57ショック」という言葉が作られたのが1990年でした。
それを受けて当時の経済企画庁が、1992年に出した『国民生活白書』のタイトルが「少子社会の到来、その影響と対応」でした。私もこの白書の影響を受けて、経済の変化と家族の変化を結びつける調査研究を始めました。
それ以来、家族や結婚に関して、分析や研究だけでなく、多くの実態調査を行ってきました。
統計データ分析、アンケート調査、それに個人に対するインタビュー調査等も行い、直接、未婚者の生の声を集めているうち、「奨学金を返しながら結婚生活を送るのは不安」「自分が育った以上の環境をこれから生まれる子どもにも与えたい」といった数値データだけでは見えてこない将来生活に対する不安意識が浮かび上がってきたんです。
──個々が抱えている不安の奥深くまで分け入って見えてきたものがあったわけですね。
たとえば、ある未婚女性は「自分は親のお金でピアノを習ったり音楽大学へ進学できたりしたのに、もし、将来、自分の子どもにお金がないからレッスンや音大に行かせられないと言わなければならなくなったらつらい」と、まだ生まれてもいない子どもの心配をしていました。
若い人たちは、そんなことを考えながら、将来の結婚相手はもちろん、結婚の可能性があるつきあう相手も選んでいるんですよ。
「奨学金を借りている人と付き合ってはダメ」低成長時代の恋愛
──『日本の少子化対策はなぜ失敗したのか』の冒頭で取り上げられている「奨学金を借りている人とつきあってはいけない」という言葉もそうですが、いくらなんでもネガティブに考えすぎのような気もしますが?
30年以上前に20代だった今の中高年世代にはこの状況は理解しにくいかもしれません。その頃はまだ学費もそれほど高くはなかったし、借用する奨学金の金額も、借りている学生も少なかった。
さらに、30〜40年前までは経済成長があった時代ですから奨学金の返済もそれほど負担にならなかった。まず前提となる経済状況が今と当時では、まるで変わってしまているんです。
「奨学金を借りている人と…」という親御さんの言葉も、ちょうど奨学金破産問題が世間を騒がせていた時期だったこともありますが、今は親が子の恋愛相手に関して、とくに結婚後に『金銭面で苦労させたくない』『みじめな思いをさせたくない』と心配する時代になってるんです。

『貧しい国・日本』の結婚を「リスク」と考える若者たち
──たしかに、バブル崩壊までは給料は毎年上がるものというのが常識であり、将来に対しても何とかなるだろうと楽観的でした。
現在は全く逆の経済状況です。ところが、みなさん、あまり認めたがりませんが、すでに日本は『貧しい国』になってしまっているんです。
しかも、現実には多くの国民が貧困と隣り合わせなのに、大半の人の意識が“中流”のまま。これも少子化の大きな要因になっています。
逆を言えば、貧困に苦しむ人が増えているにもかかわらず、それを表に出さない人が多い。いわゆる“世間体”を気にしているのです。
日本人のプライドは“人から下に見られないこと”にあるため、“世間並み”の生活を送れなくなることがもっとも世間体的に悪い。
ここで言う「世間体」を保つとは、身近な人たちから文句を言われないような生活、行動を保つこと。とにかく、家族や親戚、学校や職場の仲間、友人などから「経済的なマイナス評価」を受けないことが、日本社会に生きる多くの人々にとって最優先事項になっているんです。
多くの若者が抱える『中流生活からの転落』という不安
だから子どもに世間並みの生活を提供できなければ、それは「世間体」に反する。つまりそれは『中流生活からの転落』を意味し、親として最大の恥だと考えてしまうのです。
だから、出産する子どもの数を絞るだけでなく、そもそもそのような環境を提供できないのであれば結婚そのものを望まなくなっているんです。
そういう“世間並みの生活”から転落する可能性を避けようとする強い意識を、私は「中流転落不安」と呼んでいます。
「中流転落不安」が、結婚だけでなく男女交際まで控えさせ、結婚したとしても、子どもを希望数以上産み育てることの妨げになっているんです
──ところで、いったい、どういう生活が“人並み”であり“中流”だと思われているのでしょうか?
一通り家電製品が揃っていて、地方だったら持ち家と車があって、子どもが習い事をしたい、塾へ行きたいと言えばそれも叶えてあげて、大学に行きたいと言えば親の負担で行かせることができる、そんな生活です。実際、かつての日本では、大多数の国民が実現していました。
今の若い人たちは、それができていた「親世代の生活レベル」を中流だと思っている。したがって、結婚をしてその親以上の生活が見込めなくなるなら、それはリスクだと判断したとしても無理はないんです。

「世間に評価される我が子」を重要視する親たち
──そういった子どもへの愛着はどこから生じているのでしょうか?
前近代的社会では、子どもは労働力であり、老後の生活の世話をしてくれる存在でした。それが近代社会になると子どもは労働力ではなくなり、核家族化も進んで子どもに老後の扶養や世話を期待することが難しくなった。
そうして西洋先進国では福祉国家が成立し、老後の世話や扶養が社会化され、子どもに頼る必要性も薄れていったんです。
そのため、欧米では主として親にとって子育ては、「楽しみ」であったり「自分を成長させるもの」という捉えられ方をされています。
さらに、欧米社会では子どもが成人すれば「親の責任は果たした」とみなされる。大学進学等にかかる費用も、アメリカやイギリスでは、原則、子どもがアルバイトで学費を貯めたり、返済不要の奨学金を得たり、学生ローンを組んだりして自力で調達し、それでも足りない分を親から借りたりするのが一般的なんです。
一方、日本では親が子どもの成長を楽しむことより、子どもを「よりよく育てること」つまり「育てた子どもが社会的に評価されるか」を重要視している。
子どもとのコミュニケーションなどの「子育ての楽しみ」よりも、「経済的に支え、よい教育を受けさせること」に価値を見出しているため子どもにお金をかけざるを得ない状況になっている。
そして、そこにもさきほどの世間体意識が反映しています。最低でも自分の周りの親戚とか同じ学校を出た人のグループの中で遜色のない程度に育てなければいけないというプレッシャーがかかっていますから、なかなか「子どもを多く持ちたい」というマインドにはなりにくいわけです。
女性の自己実現を阻む「企業社会の差別意識」
──30〜40年前に比べれば女性も社会に進出して活躍しています。少子化が問題になったときも「仕事をやり続けたい女性が、結婚や出産をためらっている」ことがその原因とされ、欧米と同じように子育てと仕事を両立できるように保育所の整備や育児休業の充実、さらに夫の子育て参加の推奨などが行われてきた経緯があります。しかし、それらはいずれも結果につながっていません。いったいそれらの施策のどこが間違っていたのでしょう?
日本社会においても、欧米のフェミニズムの影響を受けて男女平等意識はある程度浸透しました。
しかし、女性も成人したら経済的に自立し、収入を得るために働くべきだという考え方は実際のところ思ったほどには浸透していない。そして「仕事=自己実現」という意識も薄い。
一方、女性が仕事をするのが必要だし当然だとされ、職場での女性差別がなく、昇進などでも差別されない仕事環境のある欧米では「女性が仕事を続けたいから結婚はしない、子どもを持たない」というロジックは妥当なので、子育てと共働きを両立させるための支援策が少子化対策に有効だったわけです。
しかし、日本では既婚女性がフルタイムの仕事をすることが当然という状況にはありません。仕事で自己実現欲求を満たしている女性は決して多くありません。
なぜなら、非正規雇用や一般職をはじめとした昇進が期待できない立場にある多くの未婚・既婚女性には、そもそも仕事を継続したいから子どもを産まないというロジックは当てはまらないからです。
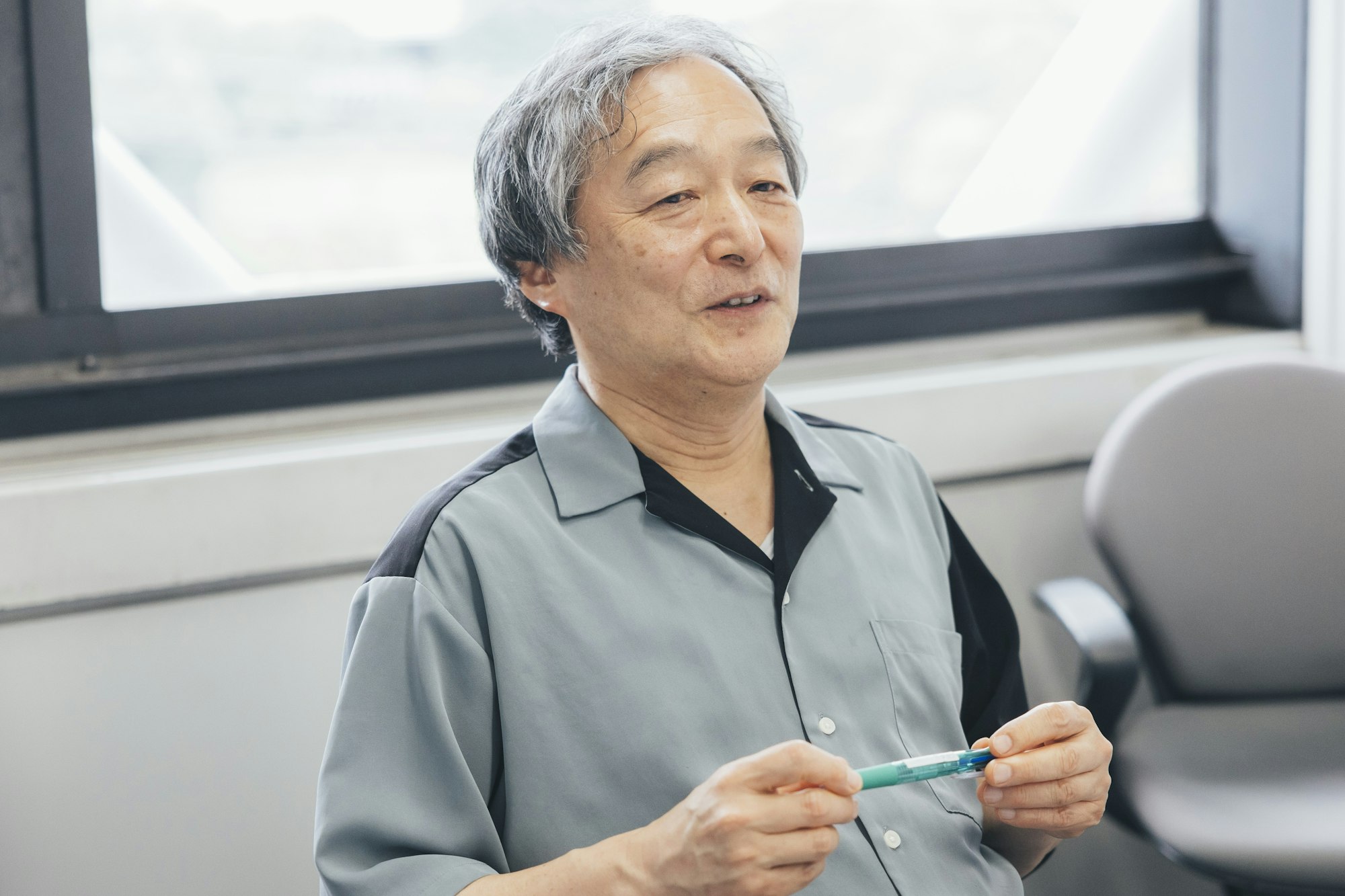
バブル崩壊後の大学生たちは「働きたくない」の大合唱
──子育ての共働きの両立支援は意味がなかったと?
そうは言いません。少子化対策としては空振りに終わったにせよ、既婚女性が「子どもの教育費」や「住宅ローン返済」のためにパートに出て働くにも保育所の整備などは必要ですから。
私が言いたいのは、まず、女性差別のない環境を整え、やりがいのある仕事に就く女性を増やし、それから両立支援を行うというのが正しい順序だったということです。
とはいえ、実際のところ、最近の学生に話を聞いても、女子は「働きたくない」の大合唱ですよ。
企業に就職して朝から晩まで死ぬような思いをして働いて、管理職になったらもっとつらい思いをする。職場には男女差別も残っている。そんなことで苦労するくらいなら、早々に収入の高い男性と結婚して主婦になった方がいいという声の方が断然大きい。
彼女たちは上の世代を見て、理想と現実を秤にかけて冷静にそう判断しているのかもしれません。
しかし、バブル崩壊以降、そういった女性の望む条件を満たす高収入の未婚男性は減る一方です。その結果、結婚する男女が少なくなって子供の数も減った。少子化というのは簡単なロジックなんですよ。
【インタビュー後編はこちら】「中国や韓国にとって日本は『少子化対策』失敗の反面教師」社会学者・山田昌弘さんに聴く中流転落社会ニッポンの未来とは?
(取材・執筆/木村光一 撮影/加藤春日)
この記事の執筆者
![有料老人ホーム・高齢者住宅を選ぶなら[安心介護紹介センター]](/shokai/assets/images/logo-ansinkaigo.93b7d14a045ed3d060ab.svg)



