ショートステイとは?利用するときにかかる費用や利用日数、手続き方法などをご紹介します!
- 2024年10月07日 公開

ショートステイは、在宅介護を受けている高齢者が一時的に介護施設に宿泊できるサービスです。しかし利用するにはどのような条件があるのかがよくわからない方も多いでしょう。そこで今回はショートステイの利用条件や費用、メリット・デメリットなどを解説します。
この記事の監修者
目次
ショートステイとは?
普段は自宅で被介護者の介護をしていても、介護者の体調や都合により介護を行えない日もあるでしょう。そのような場合に利用できるサービスがショートステイです。
ショートステイは被介護者が一時的に介護施設に利用して食事や介護などを受けるサービスのことで、最短で1日から、最長で30日間利用可能です。
ショートステイには、以下の3種類があります。
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 介護保険適用外のショートステイ
それぞれの特徴について見ていきましょう。
短期入所生活介護

まずは「短期入所生活介護」と呼ばれるサービスについて、提供されるサービスの範囲や対象となる施設についてご紹介します。
短期入所生活介護のサービス
短期入所生活介護では、食事や入浴、機能訓練、レクリエーションなど介護スタッフによる介護サービスを受けられます。基本的に医療ケアは提供されませんが、人員配置によってはインスリン投与などにも対応できる施設もあります。
短期入所生活介護となっている施設
短期入所生活介護を受けられる施設は、大きく「単独型」と「併設型」の2種類に分けられます。
単独型は、ショートステイの方のみが利用する施設です。
一方、併設型は老人保健施設や介護療養型医療施設など長期利用する方も暮らしている施設で、空いているベッドをショートステイに利用しています。
併設型の場合、長期利用をする方の状況によってはショートステイに利用できるベッドの数が変動するため、単独型よりも予約が取りにくい傾向にあります。
短期入所療養介護

次に「短期入所療養介護」について、提供されるサービスの範囲や対象となる施設をご紹介します。
短期入所療養介護のサービス
短期入所療養介護では食事や入浴など介護スタッフによる生活支援に加えて、医師・看護師による医療ケア、理学療法士や作業療法士といった専門職によるリハビリなどのサービスを受けられます。
短期入所療養介護となっている施設
老人保健施設や介護療養型医療施設のほか、病院でも短期入所療養介護のサービスを提供している場合があります。
介護保険適用外のショートステイ
.jpg?fm=webp)
最後に、介護保険が適用されないショートステイのサービス内容や対象となる施設をご紹介します。
介護保険適用外のショートステイのサービス
介護保険適用外のショートステイでも「短期入所生活介護」とほぼ同様の日常生活支援・介護サービスを受けられます。
こうした介護保険適用外のショートステイは介護認定を受けていない方でも利用できるメリットがありますが、サービスの利用料金はすべて自己負担となってしまうことがデメリットです。
介護保険適用外のショートステイとなっている施設
介護保険適用外のショートステイは一部の有料老人ホームなどで提供されていますが、提供状況や料金は施設ごとに異なります。
なお、ここからはショートステイのなかでも介護保険が適用される短期入所生活介護・短期入所療養介護の特徴や費用面について解説していきます。
ショートステイを利用するための条件は?

ここまでご紹介した3種類のショートステイのうち、「短期入所生活介護」や「短期入所療養介護」を利用できるのはどのような条件を満たしている方なのでしょうか。ここではショートステイの利用条件について解説します。
「要支援1~2」や「要介護1~5」の要介護認定を受けた65歳以上の高齢者
短期入所生活介護や短期入所療養介護は介護保険サービスのため、「要支援1~2」または「要介護1~5」の要介護認定を受けた65歳以上の高齢者であれば利用可能です。
40~64歳で特定疾病により要介護と判断された人
65歳未満であっても、40~64歳で以下の特定疾病により要介護と認定された場合は、介護保険サービスを利用できます。
特定疾病に指定されている疾患
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺
- 大脳皮質基底核変性症
- パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害
- 糖尿病性腎症
- 糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
ケアマネジャーがケアプランを作成している

介護保険サービスを利用するには、ケアマネジャーが作成した「ケアプラン」が必要です。ショートステイに関しても例外ではありません。
ショートステイを利用する本人の心身の状況に応じて施設を選定したうえで、ケアプランにはショートステイを利用する必要性や、本人・家族の介護に対する意向などが記載されます。
ただし「厚生労働省老人保健福祉局企画課長通知第25号」によると、ショートステイの利用においてケアプランの作成義務がある「相当期間以上」とは「おおむね4日以上」連続して利用する場合を指すようです。
そのため、ショートステイの利用が3日以内の場合はケアプランを作成するのは「義務ではない」と解釈でき、ケアに必要な情報提供のみが行われてケアプラン作成が省かれる場合もあります。
介護保険の適用範囲内でショートステイを利用できる日数は?

ショートステイは最長で30日間連続で利用できますが、介護保険の適用範囲内で利用する場合は介護度ごとに利用限度単位数が異なるため注意が必要です。
以下、ショートステイの1泊2日を1,000単位と仮定して介護度ごとの利用限度単位数から利用可能日数の目安をまとめたので、参考にしてください。
介護度 |
日数 |
|---|---|
要支援1 |
5日 |
要支援2 |
10日 |
要介護1 |
16日 |
要介護2 |
19日 |
要介護3 |
27日 |
要介護4 |
30日 |
要介護5 |
30日 |
ショートステイの費用は?

ショートステイにかかる費用は、大きく分けて以下の3種類です。
- 基本料金
- サービス加算料金
- 滞在費やオプション料金
このうち、基本料金とサービス加算料金には介護保険が適用されますが、滞在費・オプション料金は自己負担となるので注意が必要です。
基本料金は、主に食事・入浴介助などの「介護サービス費」を指します。介護保険が利用できるショートステイの基本料金は、おおよそ下記の4つの要素で決まります。
- 介護度
- 提供されるケアの内容(短期入所生活介護/短期入所療養介護)
- ショートステイの運営形式(単独型/併設型)
- 居室のタイプ(従来型個室/多床室/ユニット型など)
サービス加算料金は機能訓練や送迎などショートステイの利用に付随するサービスにかかる費用です。費用がかさめば負担にはなりますが、「加算が多い=サービスが充実している」ということでもあります。
滞在費やオプション料金には食費、利用中に必要となる日用品の購入費などが含まれます。費用の相場は1日当たり4,000円~8,000円と差があるため、利用前にどのような費用がかかるかをよく確認しておきましょう。
ショートステイの部屋の種類
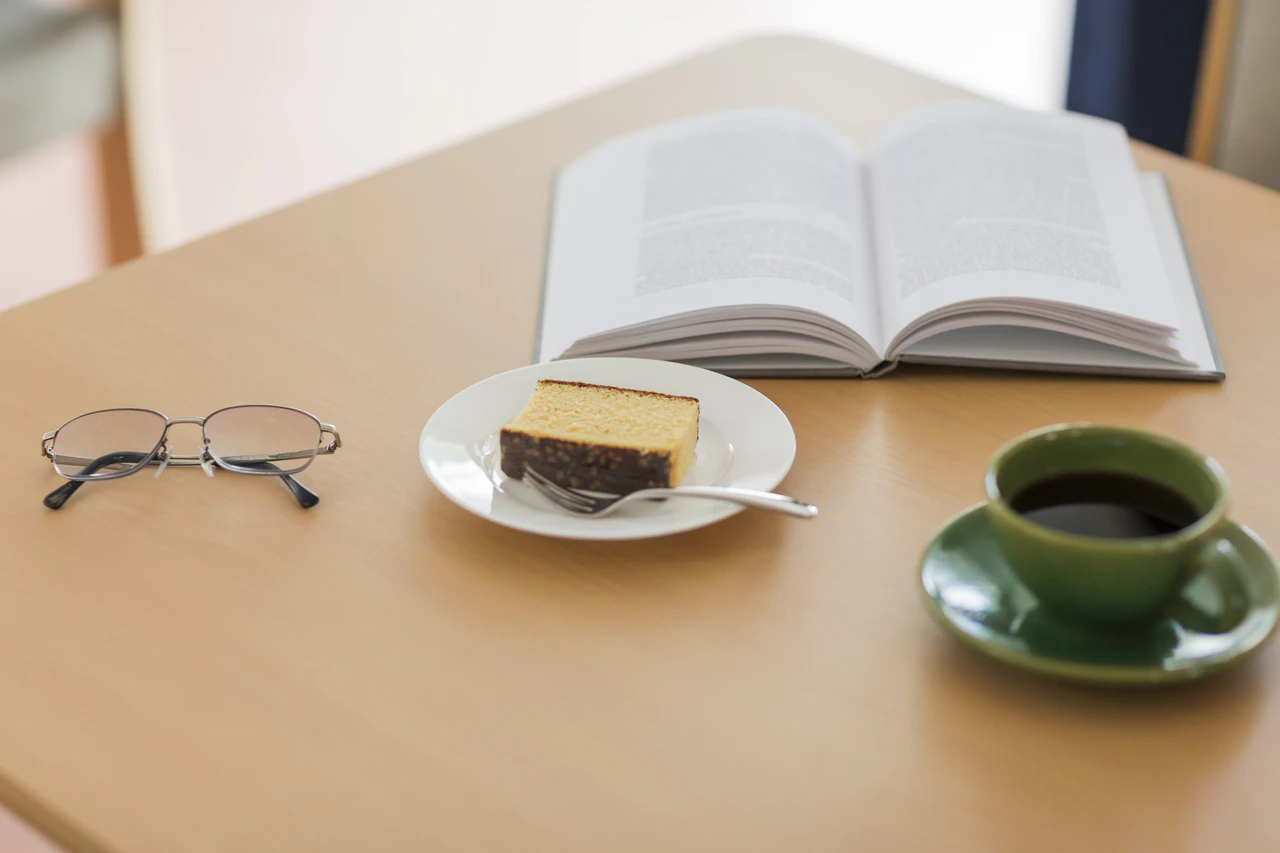
ショートステイで利用できる部屋の特徴や違いは以下の表のとおりです。
部屋の種類 |
部屋の特徴 |
|---|---|
多床室 |
1部屋を2~6名で利用する |
従来型個室 |
利用者1人に1部屋があてがわれる |
ユニット型個室 |
居室(個室)に加えて共用スペースがある |
ユニット型個室的多床室 |
設備は「ユニット型個室」とほぼ同じだが、 |
ショートステイ(短期入所生活介護)の1日当たりの基本料金

ここからは、介護度に応じた1日当たりの基本料金の目安をご紹介します。なお、ここでご紹介する金額は自己負担割合が1割の場合です。
短期入所生活介護の場合
|
要支援1 |
要支援2 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 |
446円 |
555円 |
596円 |
665円 |
737円 |
806円 |
874円 |
従来型個室 |
446円 |
555円 |
596円 |
665円 |
737円 |
806円 |
874円 |
ユニット型個室・ユニット型個室的多床室 |
523円 |
649円 |
696円 |
764円 |
838円 |
908円 |
976円 |
短期入所療養介護の場合
|
要支援1 |
要支援2 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 |
610円 |
768円 |
827円 |
876円 |
939円 |
991円 |
1,045円 |
従来型個室 |
577円 |
721円 |
752円 |
799円 |
861円 |
914円 |
966円 |
ユニット型個室・ |
621円 |
782円 |
833円 |
879円 |
943円 |
997円 |
1,049円 |
ショートステイのメリットとデメリットは?

ここからは、実際にショートステイを利用するメリットとデメリットを解説します。
ショートステイのメリット
介護者の負担をかなり減らすことができる
在宅介護には、高齢者自身が住み慣れた自宅での生活を続けられる大きなメリットがあります。しかし、介護を担う家族にとっては介護に関わる時間が長くなり、負担が大きくなってしまうことも事実です。
こうした在宅介護で家族が自分の時間を確保できるサービスとしては、通所介護(デイサービス)がよく知られています。しかし、通所介護では日中しかカバーできず、夜間~早朝時の負担は変わりません。
一方、ショートステイであれば旅行や遠方での冠婚葬祭など「家族が数日間家を空けなければならない」場合にも対応でき、介護者の心身の負担を大きく減らせると考えられます。
要介護者が介護施設に利用する前に施設での生活を体験することができる
高齢者にとって新しい環境に馴染むには時間がかかり、心身に負担がかかります。そのため、介護施設に入居すると不安感が強まり、それに伴って心身のバランスが崩れることも珍しくありません。
しかしショートステイを利用すれば、事前に施設での生活を体験できます。「一時的に泊まるだけ」「もし嫌だったら検討し直せる」という心の余裕があることで、施設への理解もスムーズになるはずです。
要介護者が手厚い介護サービスを受けられる
ショートステイでは、運営する施設の種別に応じて介護や看護など専門性の高いスタッフが24時間体制でケアを行います。そのため、在宅介護と比べて利用者は手厚い介護を受けられるでしょう。
ショートステイのデメリット
ショートステイには以下のデメリットもあるため、利用に際してはメリットとデメリットを踏まえたうえで検討することをおすすめします。
人気が高く、予約を取りづらい
介護保険が適用されるショートステイは安価で手厚い介護サービスを受けられるため、人気が高く、希望の日程で予約を取りにくい点はデメリットといえるでしょう。
「どうしてもショートステイを利用したいが予約が取れない」場合は、介護保険適用外のショートステイを合わせて検討することをおすすめします。
要介護者が生活にストレスを感じてしまう場合もある
新しい環境での生活は高齢者にとって負担が大きく、認知機能の状態によっては「一時的な利用」ということが理解できない場合もあるでしょう。
たとえ短期間とはいっても、自宅とは異なる場所で集団生活を送りながら宿泊することは被介護者にとってストレスとなってしまう可能性がある点もデメリットのひとつです。
どのような目的でショートステイを利用するべきか?

ここまで、主にショートステイを利用する条件や費用、実際に利用する場合のメリット・デメリットを確認してきました。ここからは、介護者に焦点を当ててどのような場合にショートステイの利用を検討すべきかをご紹介します。
介護者が介護に疲れてしまったとき
ショートステイについて家族は「特別な事情や重要な用事がなければ利用してはいけないのではないか」と考えてしまうかもしれません。しかし、介護に体力的・精神的な疲労を感じたときなどにも利用をおすすめします。
介護者の家族が体調を崩したとき
在宅介護を行う家族は、体調不良を抱えていても責任感から介護を優先してしまうこともあるでしょう。しかし、ショートステイを利用しながら自身もしっかり療養することで、無理なく介護を続けられる可能性が高まります。
仕事で介護の時間が取れないとき
家族の介護のために退職する「介護離職」には、収入減を失うという経済的なリスクがあります。ショートステイを利用することで仕事に必要な時間を確保できる状況であれば、一度利用を検討してみてはいかがでしょうか。
病状の悪化により要介護者の介護が難しくなってきたとき
これまで在宅介護を続けてきた家庭でも、被介護者の病状が悪化することで介護が困難になる場合があります。いきなり施設へ利用することに抵抗を感じる場合は、まず負担軽減を目的にショートステイを検討してみましょう。
介護施設への利用を検討しているとき
介護施設への利用を検討する際、実際の施設での生活のイメージが湧きにくく、利用後に後悔することにならないかどうかなどの不安を感じることもあるでしょう。しかしショートステイを活用すれば介護施設での生活を実際に体験できるため、利用後のミスマッチを防ぐことが可能です。
ショートステイを利用するときの手続きとは?

ここからは、実際にショートステイを利用する際の具体的な手順や手続きについて解説します。
①ショートステイの施設を検討する
ショートステイは運営している施設によって提供されるケアの内容や受けられるサービスが変わります。そのため、利用目的や要介護者の状態に合った施設を選ぶことが重要です。
介護施設についての情報収集は時間がかかるため、担当のケアマネジャーから介護施設の候補を紹介してもらうことをおすすめします。その際は、利用する日程や目的・希望などをしっかり伝えましょう。
②ケアマネジャーがショートステイの利用を申し込む
ショートステイの利用を申し込むのは介護者ではなく、ケアプランを作成するケアマネジャーです。その際、事業者側に被介護者の介護・医療情報を伝え、必要書類も提出します。
③入所判定会議での検討
介護施設に空きがあり申し込みを済ませたとしても、すぐに利用できるわけではありません。提出した書類や本人の状態などを踏まえて施設側で入所判定会議が行われ、そこで利用の可否が決定されます。
④入所
判定会議で利用の許可が下りたあとは、事業者と利用日程を詰めたうえで契約を行います。ここまで行程を進めることで、初めてショートステイを実際に利用できるようになります。
どの老人ホーム・介護施設にしたら良いかお悩みの方へ
満足のいく老人ホームの生活は、どの施設に入居するかで大きく異なることがあります。
安心介護紹介センターの入居相談員は、高齢者の住まいにまつわる資格を有しており、多くの老人ホームの中から、ご本人やご家族のご希望に沿ったぴったりな施設を選定してご紹介させていただきます。
施設のご紹介から、見学、ご入居まで無料でサポートさせていただいておりますので、ぜひご利用ください。
![有料老人ホーム・高齢者住宅を選ぶなら[安心介護紹介センター]](/shokai/assets/images/logo-ansinkaigo.93b7d14a045ed3d060ab.svg)








