ショートステイの利用期間はどれくらい?要介護度ごとの限度日数や長期間のショートステイの注意点をご紹介します!
- 2024年10月07日 公開

ショートステイは自宅で生活する要介護状態の方が利用できる短期入居サービスですが、介護度によって利用限度日数が定められている点に注意が必要です。
この記事では、介護保険制度で制限されている利用日数や、30日ルールの数え方について詳しく解説します。
この記事の監修者
ショートステイの利用期間は?
ショートステイとは、自宅で療養生活を送る高齢者の方が施設に短期間入居して介護を受けるサービスのことです。
ショートステイの利用期間についての決まりは大きく2つあります。
「介護認定期間の半分以内の日数」であること、そして「30日ルール」です。それぞれの決まりについて詳しく見てみましょう。
介護認定期間の半分以内の日数
ショートステイを利用できる期間は、介護認定期間の半分とされています。介護認定期間とは「要介護認定が下りた日から、その認定が有効な期限までの日数」のことです。
厚生労働省は、介護認定期間は原則6カ月とすることと定めています。
しかし、要介護者の状況によって自治体が認定期間を3~48カ月の間で設定することが認められています。介護認定期間は、介護保険被保険者証の有効期限と交付年月日から確認できます。
ショートステイは認定期間の半分以内の日数しか利用できない決まりがあるため、介護認定期間が6カ月間(180日)の方は、認定期間内に最大90日までショートステイの利用が可能です。
30日ルール
原則として、ショートステイは連続して最大30日までしか利用できないルールがあります。30日ルールについては、次のトピックで詳しく解説します。
30日ルールでの日数の数え方は?

連続してショートステイを利用する際には、30日ルールを守る必要があります。このルールにおける「30日の数え方」について、よくある疑問にお答えします。
月またぎの利用の場合は日数がリセットされるのか?
30日ルールは、月をまたいでも日数がリセットされることはありません。
つまり、同じ月内でも月をまたいでいても、連続して30日を超えるショートステイの利用は認められていないのです。ショートステイを連続で利用する際は、原則30日以内で調整する必要があります。
別の事業所のショートステイに入所した場合は日数がリセットされるのか?
たとえ30日目に他の施設に移ったとしても、介護保険制度上では同じショートステイのサービスを継続して利用しているとみなされます。
そのため、介護保険制度が適用されなくなってしまい、利用料金を全額自己負担で支払わなければならなくなります。
ショートステイを長期間利用する方法は?
利用者の身体状況や自宅の介護環境によっては、30日を超えてショートステイを利用したいと考える方もいるでしょう。
いわゆる「ロングショートステイ」を利用するには、いったいどのようにすればよいのでしょうか。
ショートステイを長期間利用する方法は、以下の4つです。
- 自治体から認可を得る
- 31日目を全額自己負担にする
- 一度自宅に帰宅する
- 他のサービスに入所する
それぞれについて見ていきましょう。
自治体から認可を得る
担当のケアマネジャーがショートステイを長期間利用したい理由を記載した届出書を自治体に提出し、承認された場合は30日を超える利用が可能です。
31日目を全額自己負担にする
ショートステイの31日目の利用料金を全額自己負担とした場合は、30日以上連続の利用とはみなされなくなります。
そのため、32日目を1日目と数えて再び介護保険が適用され、新たに30日間ショートステイを利用できます。
一度自宅に帰宅する
一度自宅に帰宅すれば、30日ルールがリセットされます。たとえば、30日目に帰宅して翌日を自宅で過ごすことで、再び30日間のショートステイが利用可能になるのです。
他のサービスに入所する
ショートステイを30日利用したあとに、小規模デイサービスなどの「おとまりデイサービス」や、地域包括ケア病棟への「レスパイト入院」などを利用すれば、日数がリセットされてショートステイを再び30日間利用できます。
おとまりデイサービスとは、日中にデイサービスを利用し、夜間はその施設に宿泊、翌日もそのままデイサービスを利用するという介護サービスです。
日中と夜間のサービスを繰り返し利用して、数日間デイサービス施設に宿泊できます。夜間の料金は施設によって異なりますが、数千円程度です。
おとまりデイサービスの利用を希望する場合は、担当のケアマネジャーに相談してみましょう。
レスパイト入院とは、自宅で介護を行っている家族の負担を軽減するために、家族が休憩(レスパイト)できるよう、要介護者の入院を受け入れる制度です。
あくまでも「入院」であるため、何かしらの疾患のある方が利用対象です。
受け入れ先の病院によって入院の条件は異なるため、利用を希望する場合はかかりつけ医にレスパイト入院が可能かどうかを確認する必要があります。
要介護度ごとのショートステイの利用限度日数とは?
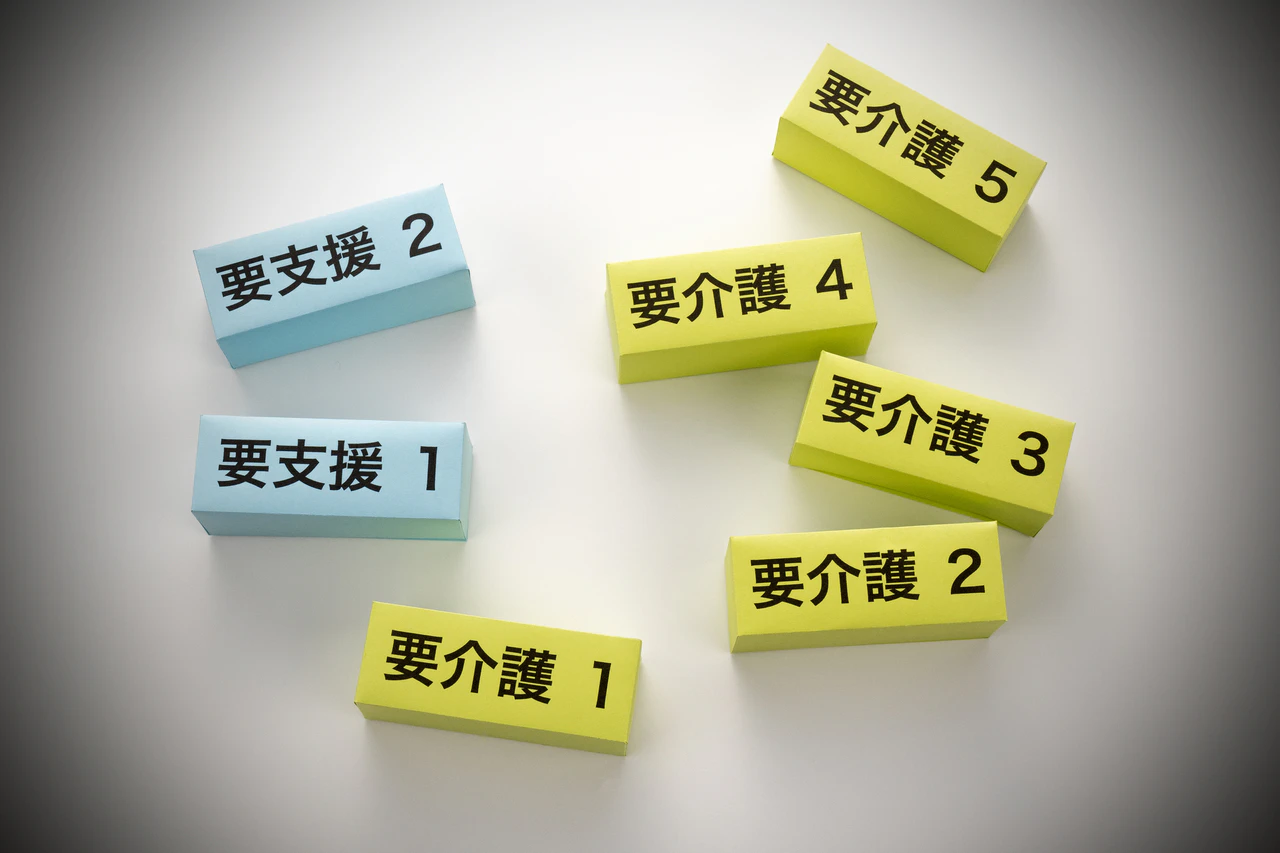
介護保険のサービスは、介護度によって1カ月に利用できる限度が定められています。
もっとも介護度の低い「要支援1」の方が利用できる介護保険サービスの単位数は5,032単位である一方で、重度の要介護状態である「要介護5」の方の利用限度単位数は36,217単位です。
そのため、1カ月あたりに利用できるショートステイの日数も介護度によって異なります。
介護度別の限度単位数を元に求めたショートステイの利用可能日数は以下の表のとおりです。
限度日数を超えた分は介護保険制度が適用されずに利用料金が全額自己負担となってしまうため、表を参考にショートステイの利用日数を検討してみてください。
要介護度 |
日数 |
|---|---|
要支援1 |
6日 |
要支援2 |
11日 |
要介護1 |
17日 |
要介護2 |
20日 |
要介護3 |
28日 |
要介護4 |
30日 |
要介護5 |
30日 |
ロングショートステイでの留意点とは?

そもそもショートステイとは、数日~1週間ほどの期間での利用を想定とした介護サービスです。
そのため、ロングショートの利用者が施設のベッドを埋めてしまうと、本来の目的での利用が難しくなってしまいます。
介護者が急な病気の場合や、自宅での介護が難しくなってしまった場合など「どうしてもショートステイを利用しなければならない状況でない限り、長期間の利用は避けるべき」と認識しておいたほうがよいでしょう。
また、ロングショートを利用することによって介護度ごとに定められた利用限度単位数を越えてしまうと、全額自己負担となってしまう点にも注意が必要です。
長期間のショートステイは介護施設へ正式に入居する場合と同程度の自己負担額になる可能性があります。
そのため、ショートステイを長期間利用したい方は、介護付き有料老人ホームなどへの入居を検討することをおすすめします。
どの老人ホーム・介護施設にしたら良いかお悩みの方へ
満足のいく老人ホームの生活は、どの施設に入居するかで大きく異なることがあります。
安心介護紹介センターの入居相談員は、高齢者の住まいにまつわる資格を有しており、多くの老人ホームの中から、ご本人やご家族のご希望に沿ったぴったりな施設を選定してご紹介させていただきます。
施設のご紹介から、見学、ご入居まで無料でサポートさせていただいておりますので、ぜひご利用ください。
![有料老人ホーム・高齢者住宅を選ぶなら[安心介護紹介センター]](/shokai/assets/images/logo-ansinkaigo.93b7d14a045ed3d060ab.svg)








